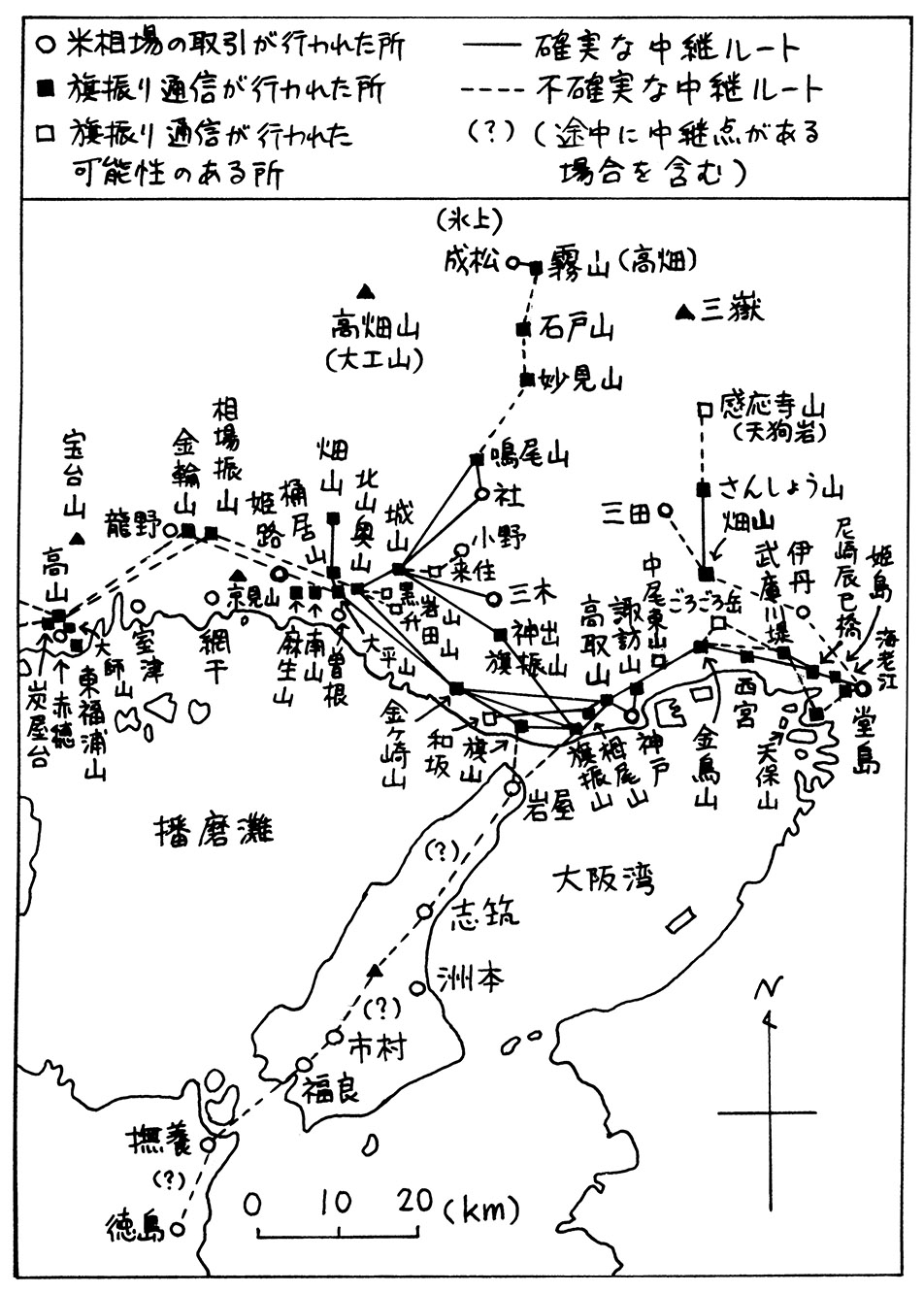
兵庫県内の旗振り通信ルート『歴史と神戸』2004
屋嶋城城門遺構整備事業を担当した高松市教育委員会の渡邊 誠氏に烽火台について確認すると、「かつて、坂出市城山,高松市石清尾山,屋嶋城の3地点で烽火リレーをしたことがあります。屋島では樹木の緑がバックになって煙が確認できましたが、他は雲とか白い建物がバックになるので、煙がまったく確認できませんでした。」と話された。烽火は昼間に火を燃やし、高く上がった煙で信号を送ると考えていたが、京都・大文字の送り火のように夜間であれば、遠くからでも確認しやすい。朝鮮半島からの侵攻が始まったことを烽火台で火を燃やして次の烽火台に伝える。先の烽火台の火が確認できたら、火を燃やして次の烽火台に伝える。この作業を繰り返して中継していく様子を遠くから見たら、まさに烽(とぶひ)と呼ぶに相応しいのであろう。火をつけて大きな炎となって燃え上がるまでを約5分とすると、1時間で10地点ぐらいは中継できる。机上の計算では、8時間もあれば対馬から大和まで連絡が可能となり、朝鮮半島からの船団が襲来したことを一晩で知らせることができることになる。
こう考えた時、畿内の入り口にあたる明石は、舟船を監視するのに絶好の地点となる。都へ向かう船団は、明石海峡にさしかかると、6時間ごとに転流する潮流の満潮時刻を確認し、東へ潮が流れる時間帯に合わせて通過しなければならない。満潮時・干潮時に明石海峡を流れる3~5ノット(時速5.6~9.3km)の潮流に逆らっては航行できない。ということは、この海上交通の要衝に、外国から攻めてくる船団の監視施設を置かない手はなく、実際、徳川幕府も西国の外様大名の進出に備えて明石城を築き明石海峡を警戒させている。古代においても明石が重要な防衛拠点に組み込まれていたはずで、古代山城が確認されていないことから、少なくとも烽火台があったのではと考えた。その位置について、上ノ丸遺跡(明石市上ノ丸1丁目)と太寺廃寺跡(明石市太寺1丁目)の2カ所から、奈良時代の古い軒瓦が見つかり、周辺からは掘立柱建物跡も確認されていることに注目した。時期が断定できそうな古い軒丸瓦が、どちらも、わずか1点であるが見つかっている。この瓦の年代について井内古文化研究室の井内 潔氏は、「663年の白村江の戦いを基点にして、文様的には古い要素を備えていますが、作り方を見ていると新しいように思えます。大きくは7世紀後半、もう少し瓦がたくさん見つかれば検討できて時代が確定できるのですが。」といわれている。664年に明石でも烽火台が設置され、防人が駐屯するために建物が建てられた、物見台のような施設も存在していたと考えてはいるが、資料不足で都合のよい推論の域をでない。

単弁八葉蓮華文軒丸瓦 太寺廃寺

単弁八葉蓮華文軒丸瓦 上ノ丸遺跡
烽火台は、朝鮮半島からの船団襲来の情報を知らせることはできるが、舟船・軍隊の数、関門海峡・来島海峡の通過日時など侵攻状況の詳細を伝えることができない。この時期に古代山陽道は、幅10mの直線道としてつくられたといわれている。なぜ、山陽道は一直線であったとするのかという疑問をもっていたが、井内氏から、「この道は九州から大和・奈良まで緊急事態を知らせるために馬を走らせました、中継地点として駅家も設置されたのでしょう。」という回答を聞き納得した。この時期の山陽道については、文献にはみえず、明石市内の発掘調査から道路跡が確認されてはいるが、その年代や点を線で結んで市内のルートを決定づけるまでには到っていない。大宰府と都とを短時間で結ぶことだけを主眼において整備された道路は、やがてより利便性の高いルートへと変更され、近世山陽道へと姿を変えていったのであろう。