それは、五世紀以後後進地区としての東国に向って強力に浸透した皇威と、それに随伴する中央諸豪族が皇威を負うて地方に臨んだために、文化も生産力も低く孤立的・封鎖的傾向を多分にもっていた弱小国造の性格を端的に示すもので、千葉国造自体がいち早く朝廷に帰順し、まず彼の本拠たる後世の千葉郷の地を奉献した前後において、中央豪族の勢力もまた領内各地に己の田荘(たどころ)を設置したためであろうと思われる。
中央の諸豪族の中で忌部、中臣、平群、大伴、物部、蘇我などの諸氏は最も有力で、初めは朝廷に仕えて地方の統治にあたったが、後には私威をたくましくして各地に土地人民を専有し、あるいは地方豪族の権威を圧して、そこに新たなる隷属関係を結び、あるいは地方豪族の出自をして己の氏族に関係あるかのごとくに擬するなど、いろいろな方法を用いて勢力の拡大につとめたのである。忌部氏が四国の阿波を経て海路房総に植民地を獲得したと伝え、物部氏の系統が広く太平洋沿岸各地に分布し、中臣氏が常陸、下総に強力な地盤を築いたというのも、結局中央勢力の地方進出に随伴したできごとであって、中央と地方との関係が密接になっていくにつれて、屯倉、御名代、御子代などの増加と、中央の大氏族の下に地方の豪族が吸収されていく度合がたかまっていくのである。
恐らく房総に古くから根を張っていた多(おお)、出雲二大氏族に出自を有する多くの国造たち(註1)も、こうした情勢下にその称号のみを保留し、実質上の支配を朝廷ないしは中央豪族に譲って、国家の統制に服したのであろう。
一方中央豪族の強大化はやがて氏族間の闘争となって現れる。もっともこの傾向はすでに仁徳天皇(五世紀前半)以後の皇位継承問題に端を発し、五世紀中葉反正、允恭両朝にもかなり顕著であるが、六、七世紀になるとはなはだ激烈となる。すなわち、欽明天皇の御世、大伴、物部、蘇我の三氏が鼎立したが、大伴氏は金村の任那日本府経営の失政から間もなく没落し、物部、蘇我両氏の反目となって展開する。排仏崇仏の争を初め、敏達天皇の崩後、物部氏の擁立する穴穂部皇子と蘇我氏のおす皇弟橘豊日皇子(用明天皇)との対抗、続いて物部守屋の穴穂部皇子の擁立と炊屋姫(かしぎやひめ)(推古天皇)を奉ずる蘇我馬子との争が起こり、穴穂部皇子は弑され、ついで物部氏の滅亡(五八七年)となる。こうして最後に残った最強の豪族蘇我氏はいよいよ隆盛となり、馬子の子蝦夷、孫入鹿と引継がれてその驕傲専権は益々はなはだしくなった。ここに至って氏族制度の弊害は極点に達し、ついに大逆事件の発生(五九二年)をみるに至ったのである。『日本書紀』によると、崇峻天皇五年(五九二年)十月「山猪(いのしし)を獻るもの有り。天皇猪を指して詔して曰く、何れの時にか此の猪(しし)の頸を断(き)るが如く、〓(あ)が嫌(ねた)しとおもう所の人を断(き)らむと、多(さは)に兵仗(つわもの)を設けたまひ、常より異(け)なること有り。十日蘇我馬子宿禰、天皇の詔(みことの)りたまひし所を聞きて、己を嫌ひたまうことを恐れ、儻者(やからびと)を招(まね)き聚(あつ)めて天皇を弑(しい)せまつらむことを謀る。(中略)、十一月三日馬子宿禰群臣(まへつぎみたち)を詐りて曰く、今日東国の調(みつぎ)を進(たてまつ)ると。乃ち東漢直駒(やまとのあやのあたいこま)をして天皇を弑したてまつらむ。」とある。この記事から今問題とするところは、一、天皇と蘇我氏との反目が極点に達したこと、二、両者共に従兵を集めて警戒を厳にしたこと、三、東国の調が事件に重大な関係をもっていることである。
右は六世紀末葉蘇我氏の権力と富とが天皇一族に対抗し得る程に強大化し、国家の政情が著しく動揺していたことを示すもので、それにはもちろん蘇我氏と結托する東漢(やまとのあや)氏や高向(たかむく)氏のような帰化豪族の支援もさることながら、蘇我氏の勢力が著しく地方に進出し、その支配下に立つ豪族がほしいままに土地人民を占有し、また互いに争奪兼併を行い、ややもすれば、屯倉など皇室の直轄の田園すら蚕食する者があったという、二大勢力の支配権をめぐる深刻な対立の上に発生した事件でもあった。それゆえこの事件の終了後間もなく、推古女帝の摂政となった聖徳太子は「一に曰く、和(やわらぎ)を以て貴しと為し、忤(さから)ふこと無きを宗と為せ。人皆党(たむら)あり、亦達(さと)れる者少し。」といい、「一二に曰く、国司(みこともち)、国造、百姓(おおみたから)に斂(おさ)めとること勿(なか)れ。国に二君非(な)く、民に両主無し。率土(くにのうち)の兆民王(おほむたからきみ)を以て主(あるじ)と為す。所任官司(よさせるつかさみこともち)は皆是れ王臣(きみのみやつこ)なり、何ぞ敢て公(おほやけ)と与(とも)に百姓に賦め斂(と)らむ。」と宣し(六〇四年)、暗に蘇我氏の野望を封ずると共に国政改革の大綱を宣したのである。
東国の国造の中には、天皇、太后、皇后、皇子の封民(御名代、御子代、私部、大私部など)、ないしは屯倉の首長すなわち伴造となって朝廷と密接な関係を結ぶ者がことに多いことはすでに述べたが、六・七世紀のころになると、東国が皇室の軍事的・経済的基礎として重要な役割をにない、始めは蝦夷地征討の拠点として、後には皇室警護、国家防衛などのために果たした役割は大きい。特に房総における檜前舎人部直(ひのくまのとねりべのあたい)(上海上国造)は宣化天皇の、他田(おさだ)舎人部直(下海上国造)は敏達天皇のそれぞれ宮殿をまもるために、子弟を舎人として京に送る義務を持ち、長く臣従を誓ったことは、前者の子孫が『正倉院文書(註2)』に、後者の後裔が『三代実録(註3)』にその名をつらねていることによっても知られるが、千葉国造の苗裔はすでに述べたように、『日本後紀』に外従五位下大掾の顕貴に列し、大私部直善人の名を記録する(註4)。これはもちろん彼一代の材幹によって築き上げられた栄位栄職ではなくて、彼の家柄が遠く律令制定以前から皇室に忠誠をもって仕えてきた余恵であろうことはいうまでもないことである。とにかく以上によって当時の皇室が東国の地盤を重視していたことを知るのであるが、それは更に七世紀の前半、皇室対蘇我蝦夷、入鹿父子との闘争に際しては、両者共に東国の兵に期待するところが多かった。すなわち皇極天皇紀二年に入鹿が山背大兄王を斑鳩宮(いかるがのみや)に襲ったときに、奴三成(やっこみなり)は数十の舎人と防戦につとめ、また三輪文屋君が、「茲より馬に乗りて東国に詣(いた)りて、乳部(みぶ)を以て本と為(し)て師(いくさ)を興して還(かへ)り戦はば、其の勝ちなむこと必(うずな)し。」とすすめていること、王自殺の翌年に入鹿が造った畝傍山の東の邸宅の警戒に「東方〓従者(あずまのしとりべ)」五〇人をもってしていることなどによって知られる。聖徳太子の抱かれた国家改革の理想は山背大兄王を経て中大兄王にひきつがれ、同四年正月十二日蝦夷、入鹿父子誅滅となって実現されたが、このとき両勢力の中心となって働いた従兵は、恐らくこれら東国出身の者たちであったであろう。
このことは、大化改新に至る蘇我氏専権のほぼ半世紀余の間に東国が蘇我氏の勢力によって、かなり大きな政治的影響を受けたことを示唆するものであって、たまたま市内の一面に「延喜式内」の古社蘇我比〓(そがひめ)神社を中心として蘇我町を存し、後述するように、都川を隔てて北に位すると考証すべき、千葉国造の本拠千葉郷を配することは、前記「東国の調」が崇峻天皇の大逆事件に重大な関係があったことと共に、この半世紀間の動向を物語るものとしてすこぶる興味あることといわねばならない。
(武田宗久)
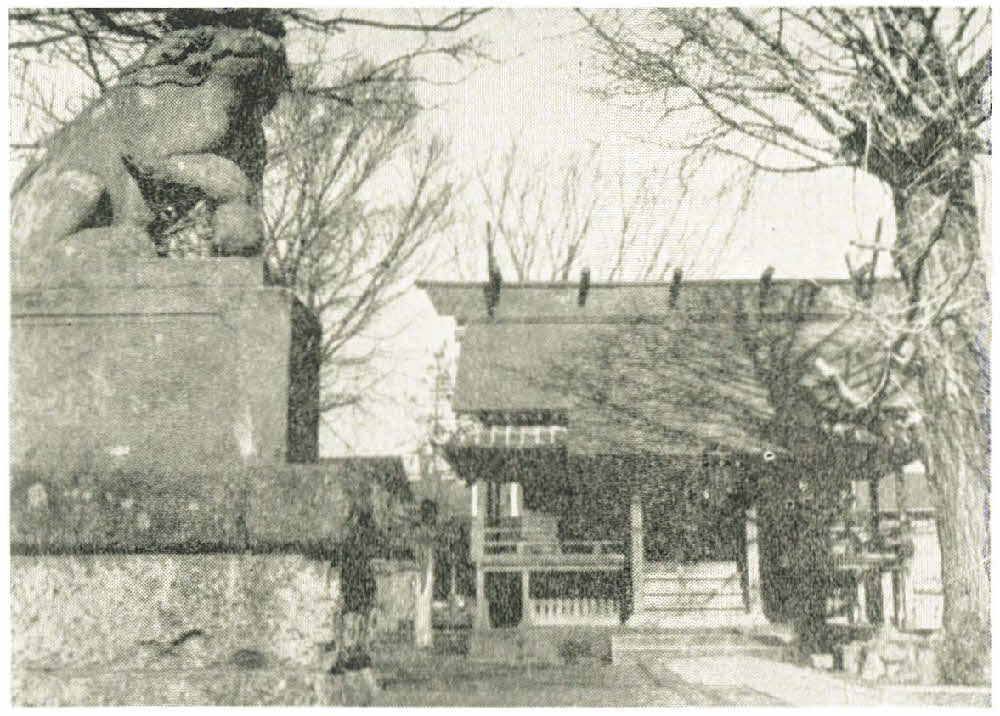
2―156図 蘇我比〓神社 (『千葉市の文化財』)
【脚註】
- 粟田寛『国造本紀考』巻二 文久元年
- 他田日奉部神護解(正倉院文書正集四四)『大日本古文書』巻三、一四九―一五〇ページ所載 明治三五年
- 『三代実録』仁和元年三月一九日条
- 『日本後紀』延暦二四年一〇月、大同元年正月、同四年三月条