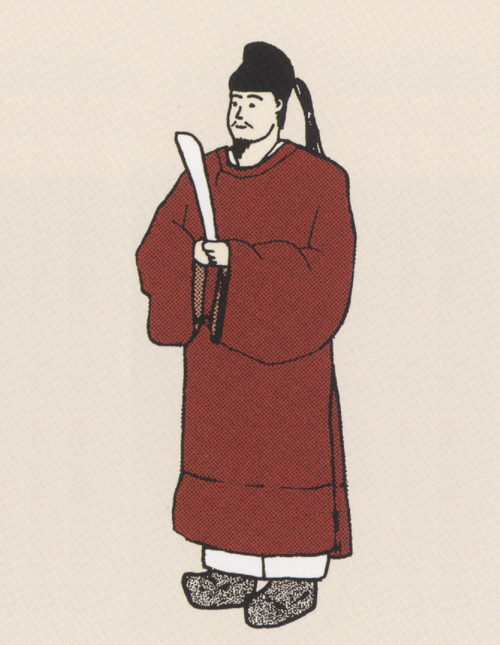
今から約1300年前、国家の仕組みが整備されるなか、全国は約60の「国」(今でいう県)に分けられ、その国ごとに役所がおかれました。
「備後国府」とは、「備後国」を治める役所が置かれた場所のことです。国府には、都から派遣された「国司(こくし)」が儀式を行う「政庁(せいちょう)」を中心に、事務を行なう庁舎や、ものを造る工房、税を収める倉庫、役人の宿舎、食事を用意する調理場など多くの施設が建ち並んでいました。備後国府では約600人の人々が働いていたと云われています。
備後国府は、奈良・平安時代の約500年の間、備後地域の政治・経済・文化の中心地として栄えていました。
平安時代中頃に編纂された『倭名類聚抄(わみょうるいじゅうしょう)』には、「備後国のなかには14の郡、62の郷、3つの駅家が置かれ、国府は芦田郡(あしだぐん)におかれていた」と記録されていますが、具体的な位置などは示されていませんでした。
昭和57(1982)年から、広島県により、備後国府の場所を探す発掘調査が府中市で行われ、出口町から府中町・元町・鵜飼町までの芦田川北岸の山寄せ一帯に、国府に関連する遺構(いこう)や遺物(いぶつ)が発見されました。
そして、その成果を引き継いで、府中市教育委員会が元町を中心に調査を進めた結果、「ツジ遺跡(いせき)」や「元町東遺跡(もとまちひがしいせき)」が国府の中心部に近い地区ではないかと推定されています。