海老川河口の船橋港もそうした中世の港のひとつであり、鎌倉道の発着点であったと考えられます。中世の船橋港に関する史料はごく乏しいのですが、次のような興味深いものがあります。
一つは茨城県新利根村逢善寺の記録『檀那門跡相承資』というもので、これは下総船橋に住む右京律師澄賢という僧が、法流継承の資格を得るために、祈とうをし百日の護摩を修した後、船3艘に贈進の品物を積んで船橋から浅草の寺に向った旨の文面があります。康暦2年(1380年)付けの内容です。
二つめは松戸市本土寺の『本土寺過去帳』で、これには「左衛門太郎フナハシ海賊ニテ被打」の記事があります。船橋の海賊に殺害されたと解釈されている文言です。年月の記載はありませんが、ある研究書によると、文明から明応ころ(1469年~1501年)と想定されるとのことです。ここに見られるような海賊とは、平常は商品取り引きや漁業等にも従事し、時には略奪行為もするというものであったと考えられます。
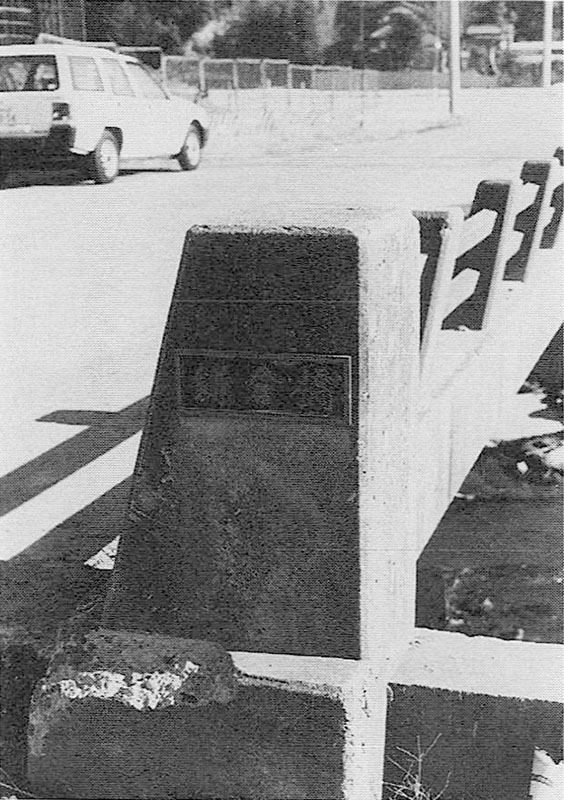
小室町と白井町清戸との境に位置する鎌倉橋。中世の船橋港に至る道だったのでしょうか
ただし、中世の船橋港の位置については異説もあります。当時の港は海老川河口ではなく、潟のようになっていた天沼の西側であったとする説です。すなわち、現在のJR船橋駅北方の天沼公園西側あたりと見る説です。発掘調査によって中世の汀線が判明すれば、この説も有力かもしれません。

昭和25年の天沼。中世には潟のようであったという説もあります(写真・黒川雅光氏)
船橋大神宮周辺や本町の一部は、早くから集落が成立し、室町時代前期には神保郷内の村々より発達した地区であったと考えられますが、史料的に少ないため、その解明は今後の考古学的成果によらなければなりません。