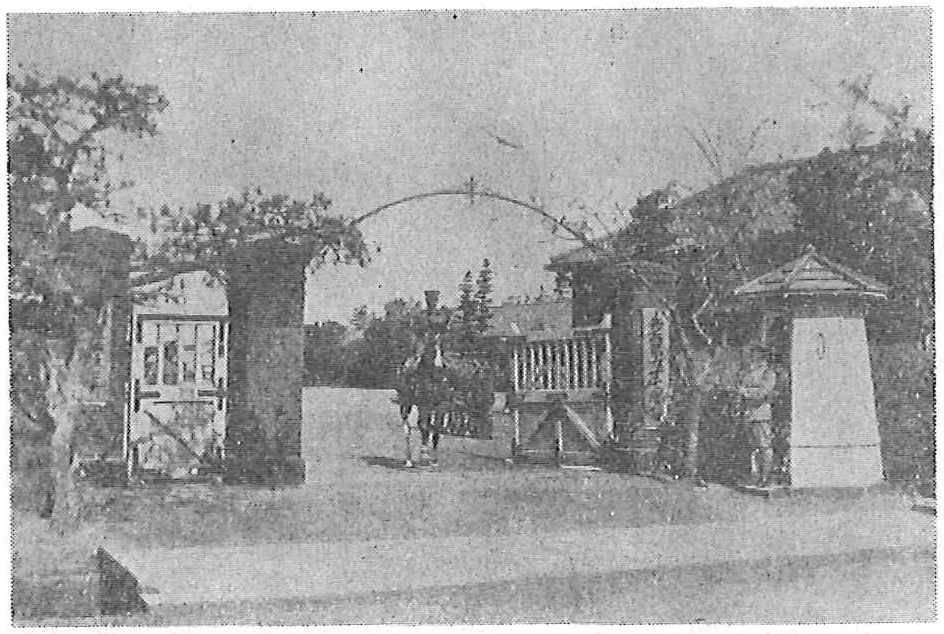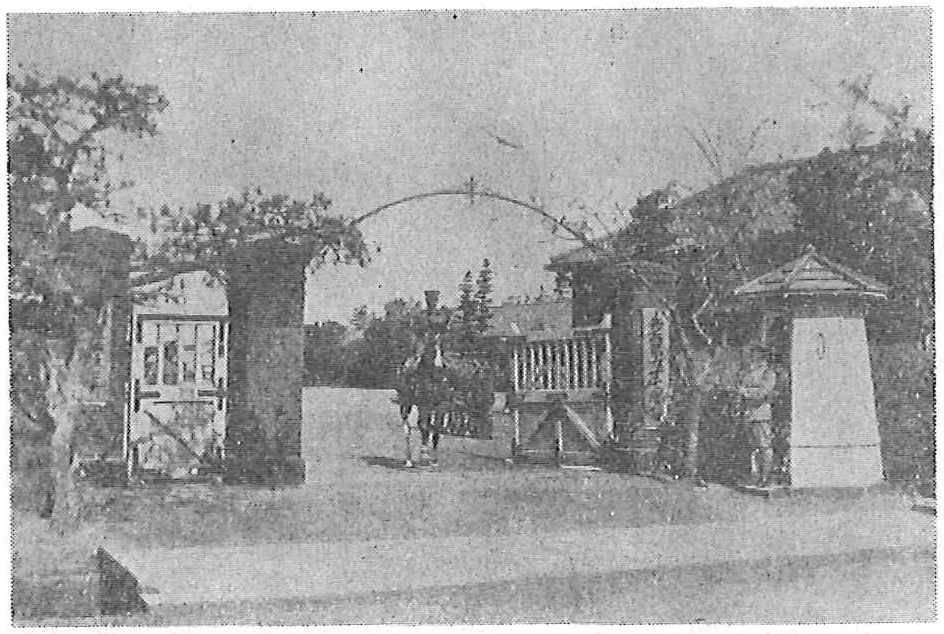日露戦争後、軍備の拡張が行なわれると、明治四十年十月九日に歩兵第六十七聯隊が浜松に設置された。静岡・豊橋には各歩兵部隊があるのに浜松にはない。【三方原】「軍隊の存在はその消費によって町もうるほひ、また治安の維持にも役立つ」という県会議員中村忠七などの誘致運動もあって、陸軍当局も「浜松は天竜川・浜名湖・太平洋で囲まれ背後に広大な三方原をもっており新設部隊の環境には格好の地である」として、岐阜や沼津をさしおいて浜松設置決定となったといわれる。町会もあげてこれを歓迎している。徴兵区域は榛原・志太・周智・小笠・磐田・引佐・浜名の七郡で、翌四十一年三月豊橋で編成された部隊は町民歓迎のうちに富塚村(現在当市城北三丁目、静岡大学工学部)の新兵舎に入り、浜松では記念行事がつづき新設部隊歓迎一色にぬりつぶされた。【四十年】同年末には編成を完了し、豊橋の第十五師団(最初第三師団)に所属した。初代聯隊長は陸軍中佐江木精夫。日露戦争の直後であり、カーキ色の軍服姿の軍人を町民は畏敬の念をもって迎え、また広い練兵場はその地名をとって和地山練兵場といわれ、凧揚会場としても親しまれた(大正八年『歩兵第六十七聯隊史』)。【高台方面発展】浜松中学校の開校によって、ようやく賑やかとなってきた高台方面はこの聯隊設置によって、ますます発展をみせるようになっていく。これは浜松の軍事都市化の第一歩でもあった。
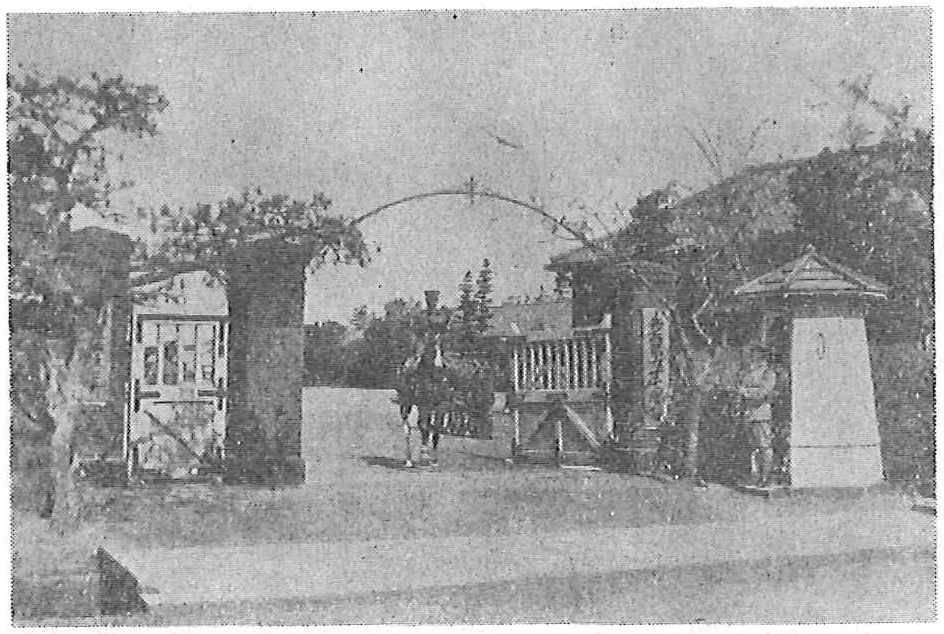
歩兵第六十七聯隊 正門(現在静岡大学工学部,城北三丁目)