東小学校にプールが完成したのは昭和三年、小学校では市内で初めてのことで、そのほかの小学校には全くなかった。この状態は戦後も長く続き、小中学校では浜名湖や天竜川、都田川などに児童・生徒を引率して水泳訓練をしていた。夏休みになると貸切バスで舘山寺の海岸に行って、数日間水泳訓練を行い、最終日に遠泳をして終わるという学校が多かった。ある学校では、都田川の木の橋から児童を突き落として岸まで泳がせるという手荒い方法で訓練していた。村櫛小学校では水泳訓練の後、戦前から続いていた鷲津から村櫛までの大遠泳をしていた。河輪小学校では天竜川で水泳訓練をしたが、その様子が河輪小学校『百年のあゆみ』に「川の流れのゆるやかな所を選んで、赤旗を縄で囲み、天然プールが出来上る。流れに逆らいながら五十メートル泳ぐ。犬かきでも、クロールでも何でもよい。到着したら帽子に赤線一本がもらえたのである。ぼくも、どうやら一本もらえた。」と出ている。豊西中学校では創立直後から焼津まで出掛けて海洋訓練を二泊三日で行うようになり、それを引き継ぎ笠井中学校ではこの焼津での三泊四日の海洋訓練(三年生全員)をプールが完成する昭和三十四年まで続けた。
昭和二十年代にプールを持っていたのは、小学校では南・吉野・鴨江、中学校では北部・南部ぐらいであった。鴨江小学校の場合は昭和二十九年八月に長さ二十五メートル、幅八メートル(五コース)のプールが完成したが、その費用は地元負担が八十万円、市の補助が四十万円の計百二十万円であった。このプールは学童の平均身長を勘案して深さを七十五センチから一メートルとしたもので、安全に泳げるようにした画期的なものであった。当時は市の補助はわずかで、その多くが地元負担であったので、住民への寄付依頼や児童・生徒、保護者による廃品回収などで、プールの建設資金を積み立てていたのである。昭和三十年代に入ると、多くの学校でプール建設が進んだが、昭和三十一年八月に完成した浅間小学校のプール(図3―19)は総工費二百四十八万円余のところ、市費はわずか五十万円のみで、残りはPTAが主体となって拠出したという(浅間小学校『創立拾五周年記念誌』)。当時、市内の小学校三十八校中、プールがあるのは浅間小学校を入れて八校であった。プールが出来た学校では、夏の体育の授業は水泳が中心となっていった。


図3-19 浅間小学校のプールと落成祝歌
【講堂】
学校では大勢の児童・生徒を集めて行う始業式・終業式・卒業式などの儀式や学芸会・映画会などで使う講堂が必要である。戦前は豊かな市町村では立派な講堂を持つ小学校がある反面、教室を二つ、三つ一緒にしてにわかづくりの講堂をつくる学校もあった。郊外の小学校ではこのような施設で儀式や様々な会を開催していたが、戦災校や新制中学校ではどこも適当な施設がなかった。始業式や修業式は運動場で、雨が降れば教室で放送を通して行っていた。戦災を受けた小学校で講堂が建てられたのは早くても昭和二十年代後半、佐藤小学校に大きな講堂が完成したのは昭和三十年で、自慢の講堂では付近の住民もよく映画を楽しんだという。中心部の東小学校にこれまでにない立派な講堂が完成したのは、三十四年九月であった。学校の行事はもちろん、広く一般の会合などにも利用された。郊外の小中学校でも昭和二十年代後半から三十年代前半にかけて多くの学校で講堂が建てられた。笠井中学校に昭和二十八年に造られた講堂は二階建てで、映写室を備え、ステージの左右には照明室もあった。講堂の床面は傾斜が付けられて、後ろの席からもステージがよく見えるように出来ており、一般の人々も数多く利用したため、入口には切符売場まであった。積志中学校にも同三十一年に素晴らしい講堂が出来た。一方、中心部の小中学校には講堂のある学校はあまり無く、卒業式の式場探しは頭痛の種であった。講堂や広い教室のない所では中庭やテニスコートに椅子を並べて式を挙行した学校もあった。昭和四十年代に入っても蜆塚中学校ではプールの中で卒業式を行っていたほどである。昭和四十二年三月十八日に蜆塚中学校のプールで行われた卒業式の写真はなんと『静岡新聞』の一面のほとんどを使う形で掲載された。写真の説明には「講堂がないため、ことしもプールで卒業式を行なった」と出ていた。元城小学校でも昭和四十三年度まで青空卒業式であったという。このような学校に講堂を兼ねた体育館が完成するのは昭和四十年代中ごろ以降である。
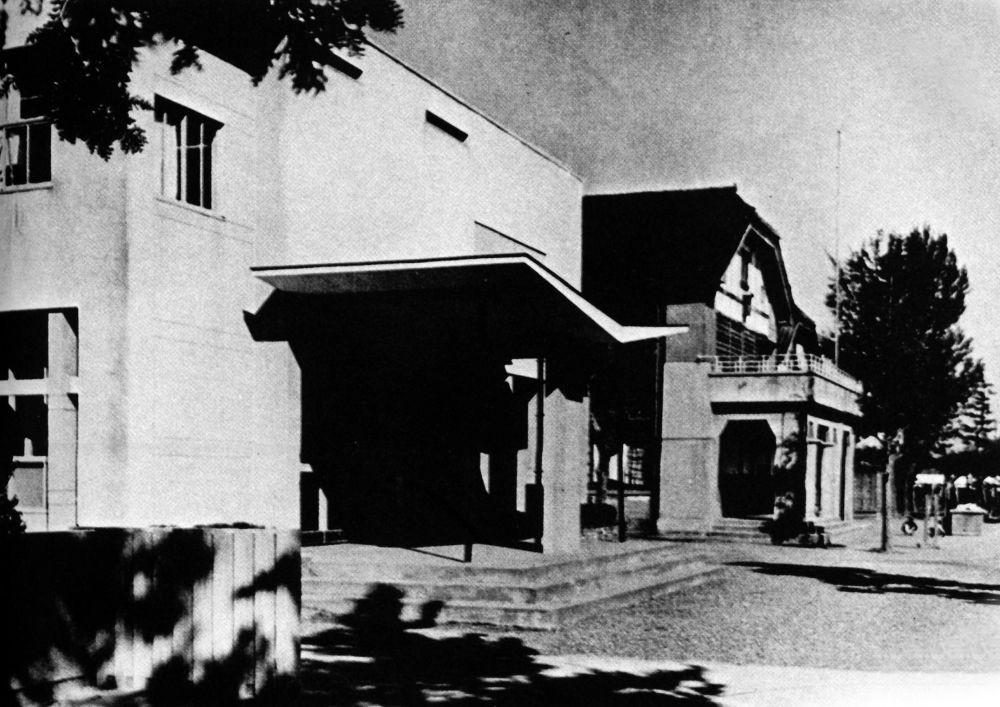
図3-20 佐藤小学校の講堂