ゆすらによる『みづうみ』の編集は二年で終わった。ここで、彼のかかわったこのほかの文化活動について触れておく(雑誌『地方文化』の発行については第二章第九節第二項参照)。
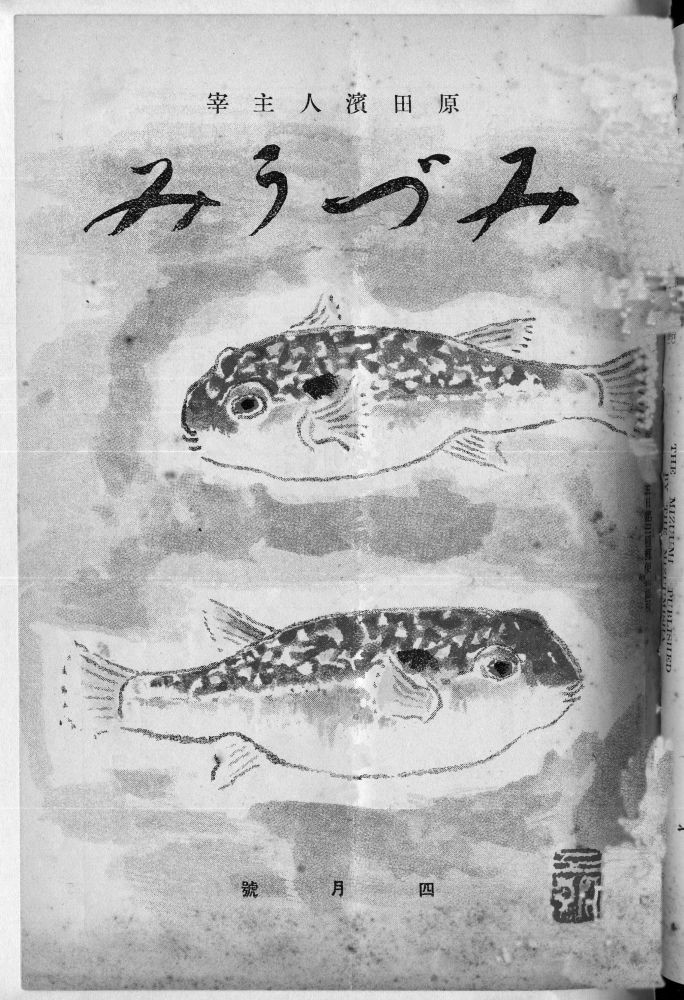
図3-74 『みづうみ』昭和二十五年四月号
【『新しき村』 松本長十郎】
ゆすらが、武者小路実篤を主宰とする雑誌『新しき村』の編集を手掛けるようになったのは昭和二十六年八月からである。戦前から武者小路の思想に共鳴していた彼は、戦後自宅を新しき村浜松支部とし、休刊していた雑誌『新しき村』を復刊させた。その陰には、浜松在住で新しき村の会員であった松本長十郎の協力があった。雑誌は毎号武者小路の絵が表紙を飾り、内容的にも充実していて全国から反響があったが、ゆすらによる編集は三年間で終わった。また、ゆすらは浜松地方の文化の向上のために講演会を企画し、前述の武者小路や安部能成・天野貞祐・湯川秀樹ら一流の人々を講師として招いてこれを成功させている。これまで見てきた、鈴木ゆすらの超人的な努力による幅広い文化活動は高く評価されるべきである。
【『巖滴』】
昭和二十七年から『みづうみ』の編集は濱人の手に戻された。この間の注目すべき事柄として、濱人の第二句集『巖滴』(昭和二十五年十一月)の刊行がある(第一句集『濱人句集』は昭和十八年刊)。出版社は冨山房。A6判、一頁五句組のかわいらしい句集。昭和十八年春から二十三年秋ごろまでの作八百六十九句を収める。巻頭には「天下の句得させ給へと初詣」なる堂々たる一句が据えられている。跋文を石井庄司が書き、句集について、また「物心一如」を説いた濱人俳句の特質について、的確に解説している。濱人は第一句集と同じく、この集においてもタイトルと表紙絵を武者小路実篤に書いてもらっているが、おそらく鈴木ゆすらの斡旋によるものであろう。この第二句集の刊行を踏まえて、大橋葉蘭を中心に『定本濱人句集』が刊行されるのは、昭和三十八年のことである。
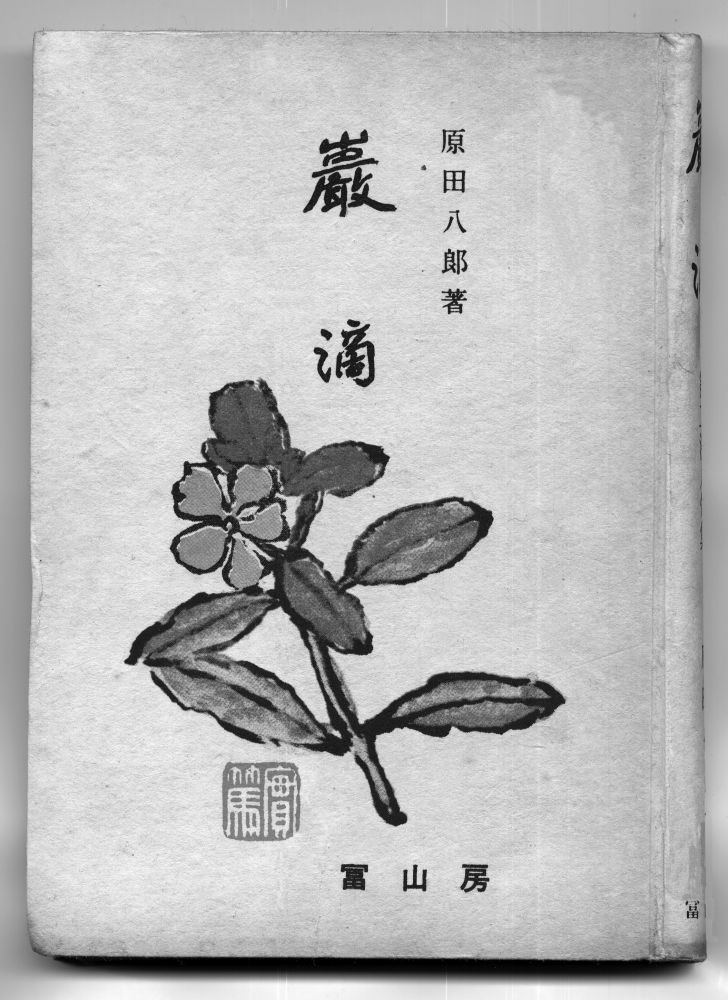
図3-75 『巖滴』