川上嘉市の歌集『行路』の刊行は昭和二十三年、『操人形』の刊行は同二十六年である。日本楽器製造株式会社社長、貴族院議員・参議院議員を務めた川上嘉市は言うまでもなく実業界の人であり政治家であったが、一流の文化人で芸術家でもあった。その文章、短歌、絵画のどれをとっても素人の域をはるかに超えた一流の芸術作品となっている。彼の歌歴については『行路』の「後記」に詳しい。昭和七年、川上は大阪の工業家代表二十四名と共に満州視察の旅に上る。その帰途、大連において天然痘を発病。神戸の検疫所病院に収容され、二十五日間の療養生活をここで過ごす。この時、彼は付き添いの看護婦に代筆させ、生まれて初めての歌を日記の中に書き込ませた。その時のことを、彼は次のように記している。
私はこれまで、作歌入門一冊も読んだ事がなく、手許に歌集一冊も持ち合せてゐなかつたので、どうして歌を作るか見当がつかなかつた。だが自分の考へ付いたのは、短歌は作者の感動を三十一文字に纏めて、己の感動をそのまゝ、読者に伝へ得れば、それでよいのでは無いかといふ事だつた。(中略)故に読者を自分と同じ感境に引張つて来る為には、あたりの風物なり状景なり、作者の心境なりを、巧に描き出さなければならない。かうした技巧がつまり歌を生むのでは無いだらうか。と、私はこんな事を考へて、その要領で百余首の歌を詠んだのであつた。
【『茅海雑詠』】
この時の歌百十首をまとめた歌集が『茅海雑詠』で、「はしかき」に「昭和七年五月二十九日 青々庵にて 川上嘉市」とある。四十七歳の時のことである。この後、彼は佐佐木信綱の『心の花』に加わり、斎藤瀏の『短歌人』にも入会する。こうして、戦前次の二冊の歌集が編まれた。これらには多数の絵画が含まれているので、彼自身は歌画集と名付けている。
【『一擲のつぶて』】
『一擲のつぶて』=昭和九年五月一日発行。昭和八年三月九日~十月十九日、令嬢(溶子)と共に欧米旅行をした時の歌、二百九十八首を収める。
【『妻をいたむ』】
歌画集『妻をいたむ』=昭和十三年九月一日発行。昭和十三年五月九日、妻恭子を失った(享年四十九歳)時の歌、百三十七首を収める。
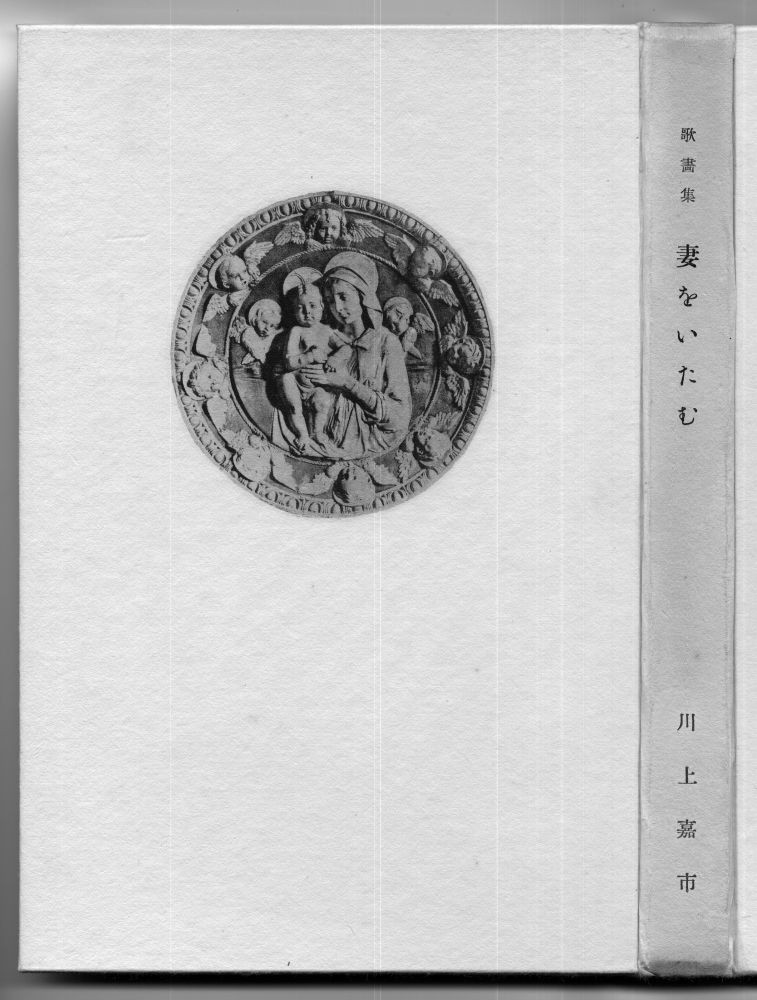
図3-79 歌画集『妻をいたむ』
戦後は、次の二冊の本格的な歌集の出版となる(共に戦時詠的な作品は除かれている)。
『行路』=昭和二十三年二月二十五日発行。昭和十八年~二十二年の歌四百八十五首を収める。
『操人形』=昭和二十六年七月三十日発行。昭和十三年~二十五年の歌で、『行路』に入れなかった歌九百二十二首を収める。
川上は、『行路』の後記の中で、歌人に対する注文を幾つか上げ、「歌はやはり抒情を主とすべきものでは無いか」「もつと人生と思想を盛り込むことが出来ないか」と述べている。次の作品(『操人形』)などに彼の短歌観がよく表れている。
新(にひくに)国を建てむのぞみの遠くして脚(きやくか)下危ふく年明けにけり
天にとゞろく世紀の大き聲なくて地(つち)にどよもす雜音のうづ
安からずひとりひそかに曉のともしの下に國をおもへど
八千萬人の重さはかなしへなへなの一人の腰には堪ふべくあらぬ
及ばずと知りつゝわれにぎし荷を擔ひて老の腰張らむかも
彼の短歌作品は、昭和二十八年に刊行された『川上嘉市著作集』(第二項参照)第九巻と第十巻に収められている。ただし、二冊とも戦前の歌を含むが、戦前に刊行された前記三歌集の作品は収められていない。『新編史料編四・五』には、それぞれ川上の太平洋戦争直前の歌と直後の歌を数首ずつ収めてあるので参照されたい。
【岩崎覚 今田鎌太郎文庫】
ここで、川上との関連で岩崎覚について触れておきたい。岩崎は、実業人であり、また、歌人であった。明治四十年、浜名郡南庄内村(現浜松市西区協和町)に生まれている。浜松師範学校第二部を卒業後、小学校教師となり、再び浜松師範学校専攻科に入学。このころ、川上嘉市の次男の家庭教師となる。後に小学校教師に戻るが昭和十四年、三十二歳の時日本楽器製造株式会社に入社、川上嘉市社長の秘書となった。昭和二十五年、同社を退社してからは本田技研工業株式会社、日本電気時計株式会社(後ジェコー株式会社)、花崎繊維株式会社の要職を歴任する。後年、蔵書の大部分を浜松市立中央図書館に寄贈、彼の亡父の名を冠して今田鎌太郎文庫と名付けられた。岩崎は、実業界に身を置きつつ、佐藤佐太郎の門下として短歌の道にも励んでいる。自身作成の年譜によれば、私立名古屋中学校(名古屋学院)に在学中、歌集『青杉』により土田耕平を識り、短歌を作ることを覚えたとあり、また二十六歳の時、歌集『寒光』を上梓したとあるが詳細は不明である。ともあれ、川上と岩崎とは、共に実業人であり歌人であったということを含めて、人間的に極めて親密な関係にあった。
戦後、浜松放送局で聴取者から短歌作品を募集し、歌人に批評を加えてもらうという番組を企画した時、岩崎が選者となった。その歌評を冊子にまとめたものが残っているが(『新編史料編五』 九文学 史料6)、岩崎の批評は実に的確かつ懇切丁寧である。彼の短歌作品として、前記『今田鎌太郎文庫目録』(岩崎覚氏略歴)に添えられた三首を引用しておく。
生ける日に縁薄かりし吾が父の名をし留めて文庫の名とす
実業にかかはりながら本を読むことに畢れる吾の一生か
喜寿越えて生命生きつつ恋ひやまずちちのみの父よははそはの母よ
【おもかげぐさ】
昭和十三年五月、川上の妻恭子が亡くなったとき、岩崎は「おもかげぐさ」なる追悼文を書いた。川上の歌画集『妻をいたむ』の付録として、同書に収められているが真情溢れる名文である。また、岩崎は地元の幾つかの小中学校の校歌、関係した会社の社歌の作詞を手掛けている。