日本は戦争では敗けないものだと教え込まれていた。こんな原則や定義は元々成り立つはづのない妄想ですが、然しそれはあく迄も真理だと信じられていました。その日本が美事に敗けた。日本人は今更の如くに自分達の祖国である日本の姿を見直そうと思いついた。それには神話伝統とは別に、具象の事実を根拠とした科学的研究にまたなければならない。即ち於是考古学の使命が深く認識されるに到つたのであります。
【伊場遺跡 高柳智 樋口淸之 國學院大學伊場遺跡調査隊 伊場遺跡保存会】
伊場遺跡は、第二章第九節第九項で既述のように太平洋戦争末期に、浜松市内を襲った艦砲弾の幾つかが市内の伊場の地に落下し、地下約二メートルの泥土を水田上に散乱させ、その中に含まれていた弥生式土器片を西部中学校の一生徒が採集したことがきっかけとなり発見された。昭和二十四年二月のことである。以上のような偶然による発見が、本格的に発掘され調査研究されることになった要因は、右跋文に見るような、時代的な背景があったと見なければならない。発掘は、発見者である西部中学校の高柳智教諭の努力により、國學院大學考古学資料室主任樋口淸之教授を隊長とする國學院大學伊場遺跡調査隊によって行われた。この報告書の第一章「調査経過とその成果」(高柳智執筆)によれば、調査は試掘と第一期(昭和二十四年五月一日~八日)、第二期(同八月二十日~九月一日)、第三期(同十二月一日~十日)、第四期(昭和二十五年七月二十三日~八月一日)の四期に分かれる。この間、第二期調査の開始と同時に、坂田浜松市長を会長として市内の文化人や教育関係者などからなる伊場遺跡保存会が発足している。浜松市は、調査費を負担するなど全面的にバックアップした。この発掘調査に保存会の果たした役割は大きなものがあった。報告書は、前記第一章のほか、序章、第二章「遺跡の地理的考察」、第三章「遺跡の状態」、第四章「文化遺物」、第五章「自然遺物」、第六章「結語」の全七章からなり、土器の実測図など多数の挿図と地形図などの図版が添えられている。この遺跡の意義について、隊長を務めた樋口教授は「結語」の末尾に次のように記している。
弥生式文化東漸の一ポイントとして、位置的にも、内容的にも重要な意義を持つことゝ、古墳時代から平安初期に汎る地方庶民生活の実態の一部を知り得た点に於て、そして空白に近い当浜松市の古代文化を明かにし得る資料である点に於て、まことに重要な意義と貴重な内容を示す遺跡であることを最後に重ねて強調したいと思うのである。
『伊場遺跡』の刊行は、昭和二十八年九月であるが、翌二十九年三月二十二日に遺跡は静岡県の史跡に指定された。
遺跡の発掘調査は、この國學院大學考古学資料室による調査を第一次として、昭和五十五年まで十三次の調査を重ねることとなる。この内、第二次(昭和四十三年)以降第七次(同四十八年・四十九年)までは、国鉄浜松駅高架化事業と深くかかわっており、第八次(同五十年)以降は保存用地内の遺構の調査が中心となる。この間、昭和四十八年に遺跡は県の史跡指定を解除された。それに対して、遺跡の保存を求める側から、指定解除処分取り消しを求める訴えが出されたが、一・二審とも訴えは却下され、平成元年(一九八九)六月に最高裁判所で上告棄却の判決が下された。
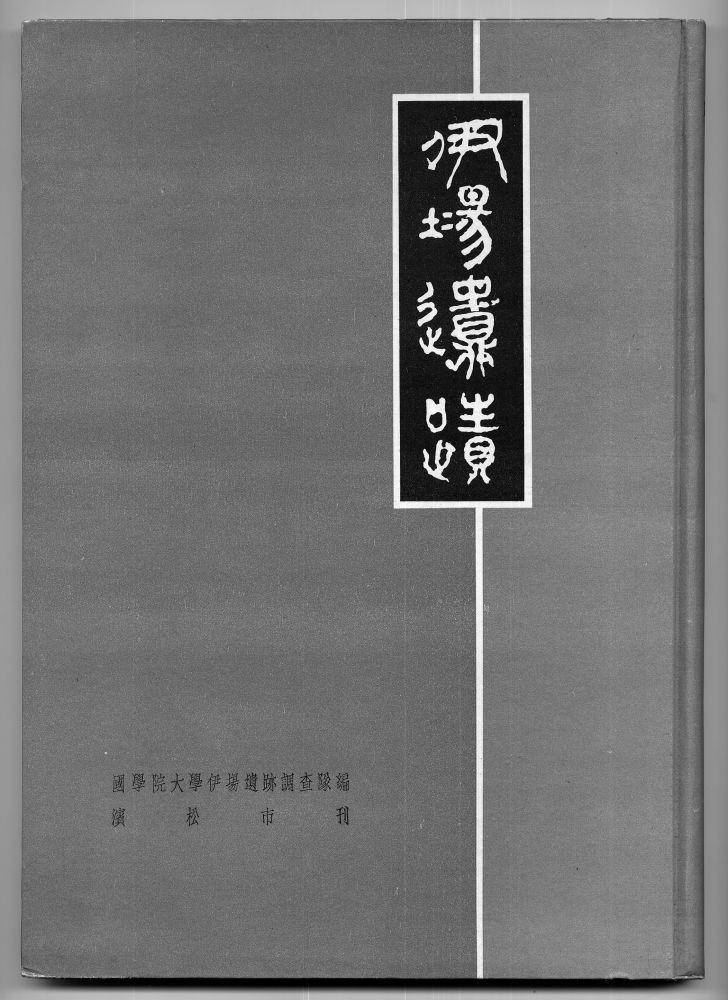
図3-90 『伊場遺跡』