戦前から戦後にかけて、遠州の国学研究に心血を注ぎ続けた小山正の戦後における最初の業績は、『内山真龍の研究』(昭和二十五年九月二十日、内山真龍会発行)の刊行である。小山は、すでに昭和十三年『賀茂真淵伝』という大著を完成させ世に問うている(『新編史料編四』九文学 史料38)。これは、真淵について師承、伝記、思想、門人から没後の追慕に至るまで、あらゆる角度から調査追究して成った壮大な事業であり、以後の真淵研究の最も基本的で重要な参考文献の一つとなったものである。
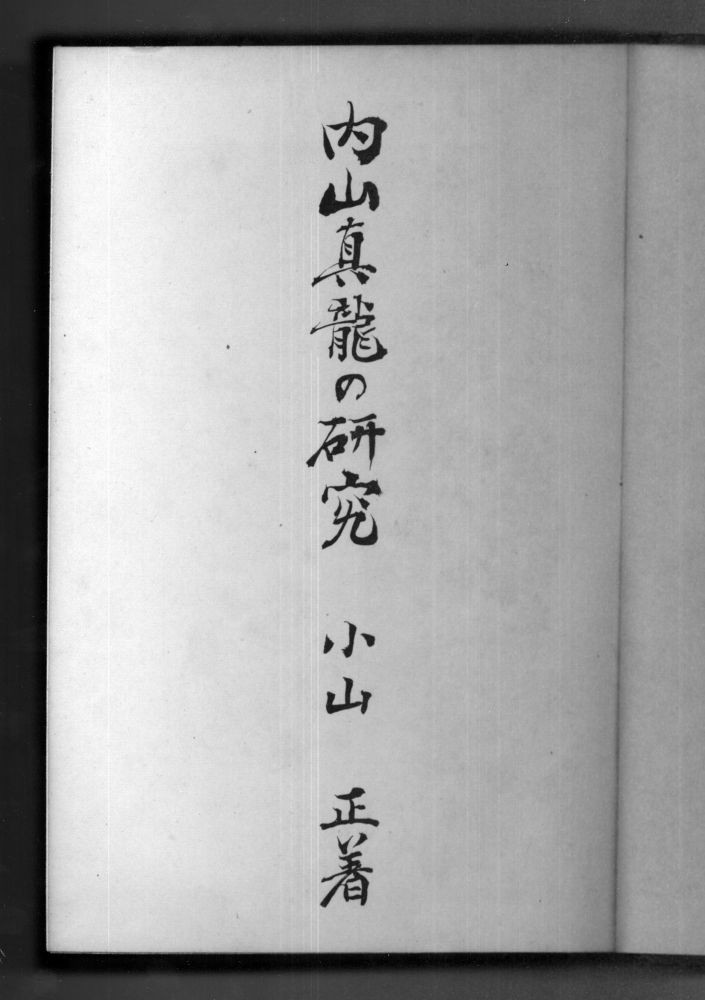
図3-91 『内山真龍の研究』(標題紙)
さて、『内山真龍の研究』は、真淵の遠江における有力な弟子の一人として、東遠の栗田土満と並称される豊田郡大谷村(現浜松市天竜区大谷)の内山真龍についての研究書である。内容は、
第一篇 真龍の生育(伝記)
第二篇 研究(古学研究、仏教研究、著述等)
第三篇 同学との関係(本居宣長ほか六名の国学者との関係)
第四篇 交友(遠江国と他国に分け、二百二十余名につきその略歴と真龍との交友関係を記す)
第五篇 門人―教育者真龍(龍門の七子以下、百三十一人の弟子につき略歴を記す)
第六篇 余説(名主としての真龍 他)
第七篇 真龍年表
『賀茂真淵伝』(約千頁)には及ばないものの、本文七百二十頁の労作である。様々な角度から真龍を取り上げて考察を加え、真龍の全体像を浮き上がらせている。その交友・門人関係に取り上げられた三百余名についての記述は、遠江国学の広がりとその内容を知る上に貴重な史料である。自序に次のようにあり、この研究が『賀茂真淵伝』に引き続いて、すでに戦前において大部分なされていたことが知られる。
私が真龍の研究を思ひ立つたのは大正の末頃であるから彼此二十年余、而し、この間、昭和十三年九月に賀茂真淵伝千余頁春秋社を出し、太平洋戦争で職務上身辺多事、それから戦後三年ばかり他の研究に没頭してゐたので、省みて研究の最も進捗したのは昭和十三年秋から十五年に掛けてであつた。それを去夏以来整理に掛り、やうく完稿するに至つた。
本書には、『賀茂真淵伝』の時と同じく、佐佐木信綱が懇切なる序文を寄せている。
【『石塚龍麿の研究』】
小山はこの六年後の昭和三十一年三月、『石塚龍麿の研究』を完成させる。龍麿の国語学上の偉大な業績については、改めて記すまでもないが、特に上代特殊仮名遣いに関する研究はまさに画期的であり不滅の業績である。この書は、大きく次の三編に分けられている。
第一篇 伝記関係
第二篇 その学
第三篇 龍麿関係書簡と龍麿集
第二篇は、第一 著述、第二 仮字研究等五つの章に分かれ、この内最も重要な第二は、古言清濁の研究と仮字用格の研究に分かれる。これは、龍麿の代表的な著述『古言清濁考』と『仮字用格(かなづかひ)奥能山路』の二著についての解説である。前者は、本居宣長の『玉勝間』に取り上げられ、高く評価されたことで有名であるが、特に後者は、大正六年、橋本進吉博士によって世に紹介された画期的な業績である。「今の五十音中、エキケコソトヌヒヘミメヨロの十三音は音ごとに仮名が二部に分れて居り、互に混ずることなく、その濁音も亦同様である」とする、その研究内容は、橋本博士が『国語仮名遣研究史上の一発見』として、独自に研究しまとめられたものだが、龍麿はすでに江戸時代の終わりごろにおいて、その事実に気付いていたことを『仮字用格奥能山路』は示している。小山は、この章において龍麿の音韻研究を詳細に解説し、彼の説を受け継いだ三河の国学者草鹿砥宣隆の『古言別音抄』と、八木美穂の『仮字袋』の二著を紹介し解説している。語源・語法・語釈等の研究、また古典・古歌の研究上画期的な意味を持つ石塚龍麿の業績は、遠州地方に住んでいる者として忘れてはならないが、小山の仕事もまた高く評価されてしかるべきである。自序において、小山は「学祖真淵の門人は真龍、真龍の門人は龍麿であるから、本書は前二著と併せて三部作ともいふべき関係にある」と述べている。
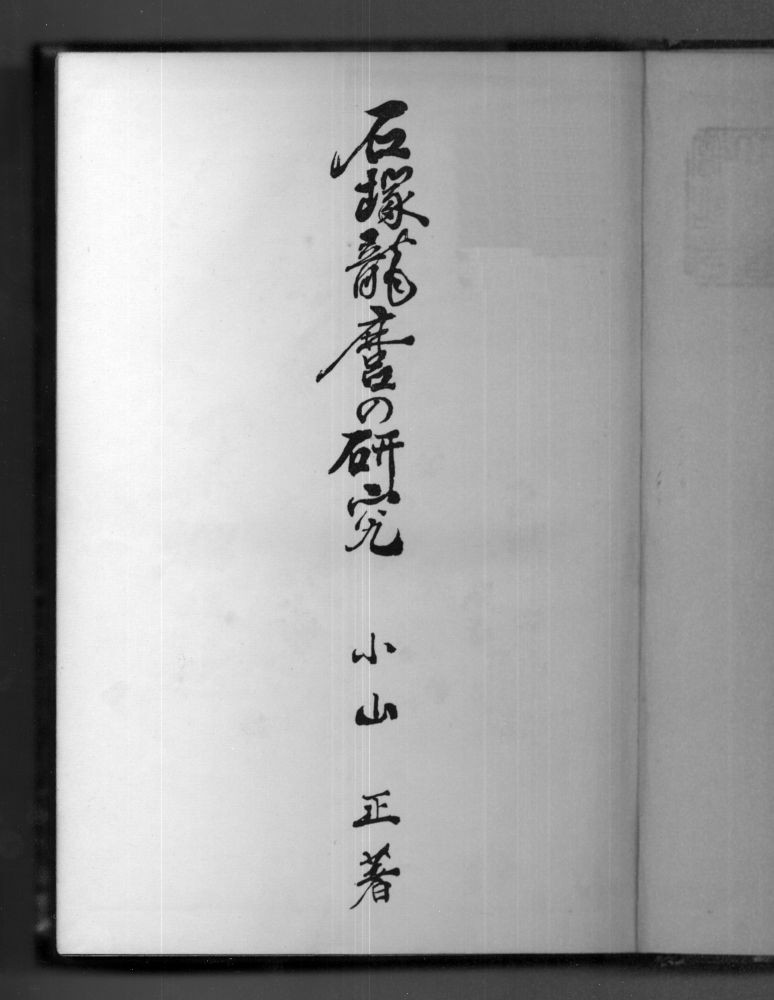
図3-92 『石塚龍麿の研究』(標題紙)
【『八木美穂傳』 『高林方朗の研究』】
小山の研究は、この三部作に終わることなくさらに続けられ、後に幕末国学者『八木美穂傳』(昭和三十五年六月刊)と水野忠邦国学の師『高林方朗の研究』(昭和三十八年九月刊)という二冊にまとめられることとなる。