敗戦後、半年も経たぬうちにアララギ派歌人柳本城西によって復活した手書きの回覧雑誌『犬蓼』の、その当時のことについては『浜松市史』四 第三章第九節第一項に記した。同誌はその後も途切れることなく月々に発行が続けられた。ただし、そこには城西の並々ならぬ苦労があったようである。昭和三十四年一月号巻末にある城西執筆の「餘白録」には、毛筆で次のように記されている。
△昭和三十四年一月号であるが、歌稿いつもながら思はしく集らず、印刷屋の方も亦かかる小さなものは歯牙にもかけてくれず後廻しになり勝でおくれ続けて仕方がない。
△本号作者十一人、詠草五十三首。紙谷君や堀畑さんなど出して呉れないので寂しいが太田君と野島さんとが久しぶりで出詠ありいささか心強き感なきにあらず
文中に「印刷屋云々」とあるのは、当時、城西のグループは、回覧雑誌『犬蓼』(年間に十二冊)に掲載した作品と文章を基に、年に一度活版印刷による雑誌『犬蓼』を出していたので、前年(昭和三十三年)分の同誌の発行について述べているのである。ともあれ、約半世紀の伝統を持つ回覧雑誌『犬蓼』は、ひとえに柳本城西という『アララギ』生え抜きの老歌人の熱意と執念によって続けられていたことがうかがわれるのである。柳本城西の亡くなったのは昭和三十九年二月二十九日。享年八十六。城西の手による『犬蓼』は、前年の昭和三十八年九月号(五百九十七号)が最後であるが、同三十九年八月に、犬蓼短歌会会員により『犬蓼』五百九十八号が、城西の追悼号として出されている。これをもって、回覧雑誌『犬蓼』は五十六年間の歴史を閉じたことになる。
【歌集『犬蓼』】
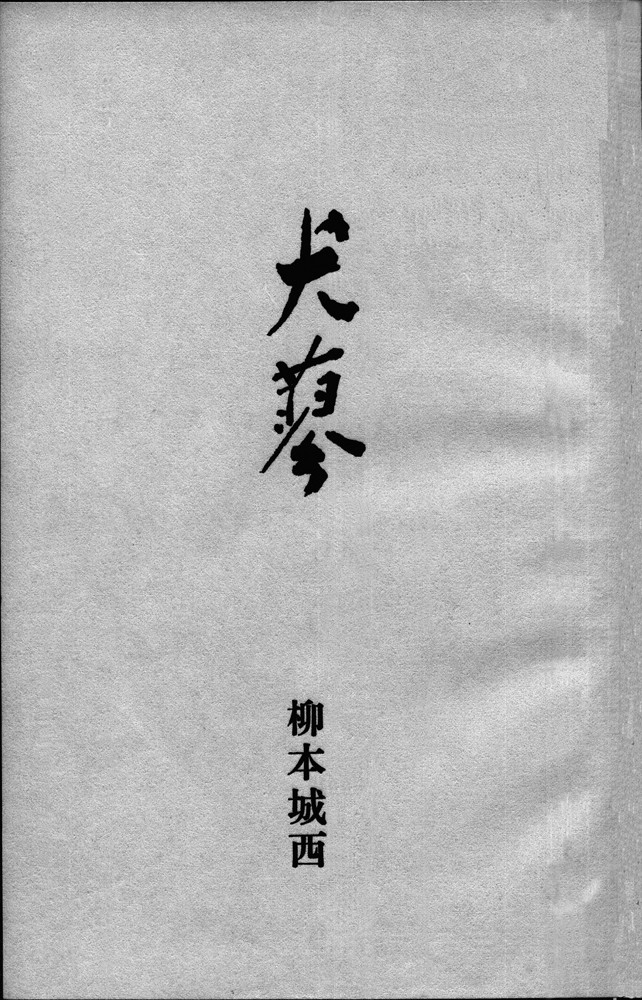
図2-53 歌集『犬蓼』(標題紙)
城西は、生前歌集刊行を望まなかったようであるが、死の翌年の昭和四十年、夫人満子の手によって歌集『犬蓼』が刊行された。発行所は白玉書房、本文二百二十八頁。城西の作歌活動は明治三十六年(二十五歳)頃から始まり、伊藤左千夫の指導を受けているが、歌集には明治四十二年以後の作品で、『アララギ』に掲載された歌のみ千五百二十八首が年代順に収められている。大正十三年と昭和二十年の歌がないのは関東大震災と太平洋戦争とが関係していよう。巻頭に土屋文明が序文を寄せている。その末尾近くに次のようにある。
翁の歌風は、その人柄から来るものと見えて、常におとなしく正直で、淡々としてひとり己の道を行くといふ風であつた。本歌集は、アシビ、アカネは省略し、アララギ初頭からの作品を、雑誌の掲載のものは総て網羅することにしたので、見方によつては、アララギの歌風が、地方在住の忠実なるアララギ会員に、如何に反映したかを知る資料ともなるのではないかと思ふ。
明治四十二年といえば『アララギ』が刊行されて二年目のことである。文明が述べている通り、歌集『犬蓼』は、確かにアララギの歌風、また、結社の性格を知る上に貴重な資料であることは間違いないと思われる。歌集には亡くなる前年、昭和三十八年までの歌が収められている。その昭和三十八年の作十六首の冒頭の五首を引用しておく。
秋あつき日の照る庭に黒揚羽黄蝶こもごも来ては飛び去る
すべりひゆまだ残りゐて花咲けり薔薇の茂れる蔭にかくれて
小松原の寺に娑羅の樹ありといふふらりと出でてたづね来りぬ
彼岸前早くも娑羅は落葉して大き伽藍のただ閑かなり
新聞紙捲きて出で来し蜘蛛打てば脚を落して逃げ去りにけり
手堅いアララギ風の写生歌であるが、三首目、五首目などにはどこかユーモアを感じさせるところもあり、自在な境地のうかがえる作品となっている。
『犬蓼』のその後であるが、前記のように昭和三十九年八月五百九十八号をもって終刊となった。しかし、同号の出された八月に妻の満子によって『回冊第一号』として再開され、これは加山俊を中心に昭和五十二年十二月の第百六十号まで続けられた。最終号巻末の名簿には二十三名の名前が見える。
【浜松アララギ 新樹の会】
なお、『犬蓼』のグループは、会としては「浜松アララギ」と称しており、回覧雑誌廃止後も加山を中心に短歌活動は続けられた。その後、数年の中断を経て、平成六年一月に、『犬蓼』のメンバーの一人であった前田道夫を中心に二十余名が集まり、「新樹の会」として再出発し今日に至っている。柳本城西によって浜松の地に根付いた『アララギ』の歌の流れは現在も脈々として続いている。前田には歌集として『きらめく翅』(平成四年、亡羊社刊)がある。
【『浜松歌人』 山田震太郎】
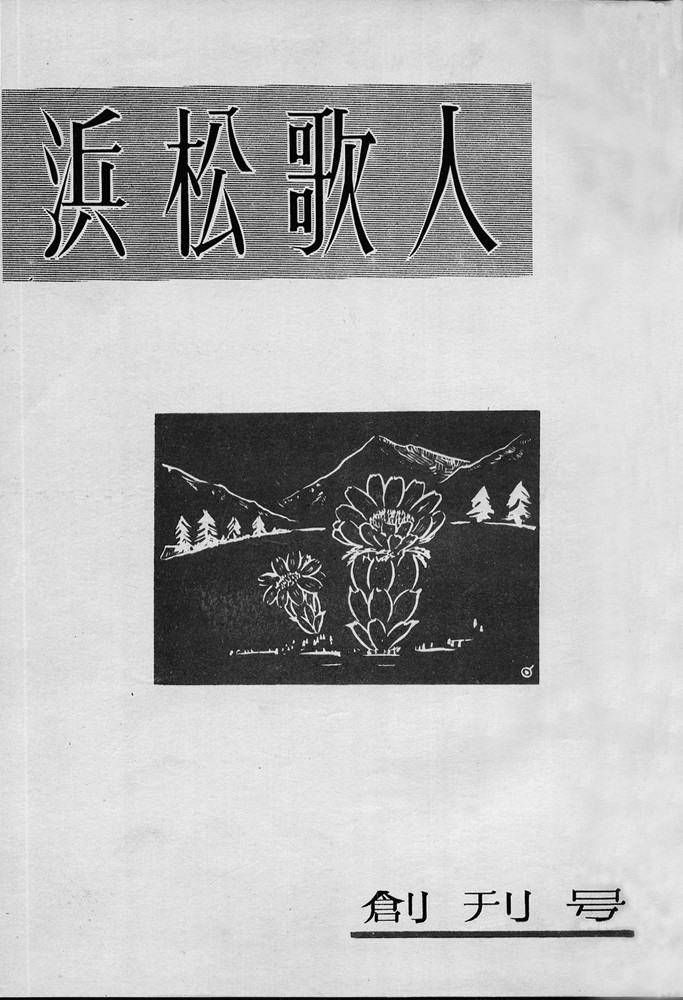
図2-54 『浜松歌人』創刊号
浜松の地に季刊(年四回)の短歌誌『浜松歌人』が誕生したのは昭和四十年の十二月のことである。巻末に執筆者住所録があって十六名の名前があるが、これは出詠者の数でもある。奥付には編集者として近藤秀明の名が記されていて、巻頭には近藤の「発刊の言葉」、巻末には山田震太郎の執筆による「後記」がある。「後記」によれば、創刊の五年前の県歌人協会西部短歌会の後、歌会形式の浜松歌人会が生まれ、その会のメンバーを中心にこの歌誌は生まれている。後記には多分に、山田個人の思いが込められている印象が強いが、創刊の背景に見通しのつかないベトナム戦争への不安等、当時の時代の空気のあったことは間違いないであろう。「明日死んでも悔いのない作品」などという言葉もあって、同誌に寄せる山田の熱い思いが感じられる。「会規その他」に、「『浜松歌人』は結社誌ではありません。随って会員間には何らの階級区別もありません。」とあるのも注目されるところである。山田は近藤芳美に師事し、近藤主宰の短歌結社「未来」の創立当初(昭和二十六年)からの会員であった。
【『神の目の藍』】
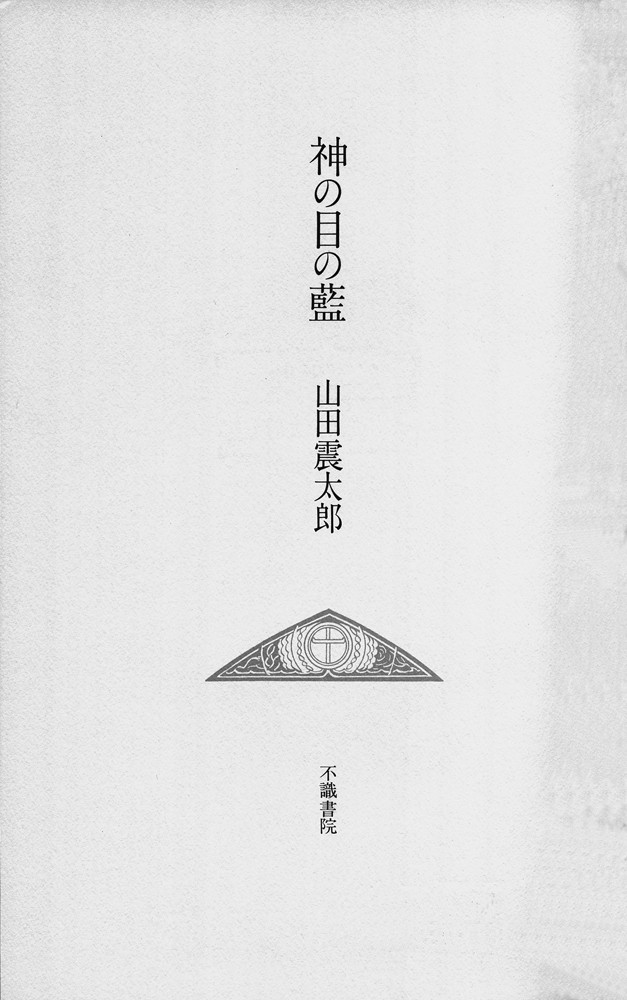
図2-55 『神の目の藍』(標題紙)
その後同誌は、季刊誌として三十余年間ほぼ順調に発行が続けられ、平成十二年五月号(№122)をもって終刊となった。この間、昭和五十九年三月号(№62)から、編集発行人が近藤秀明から山田震太郎に代わっている。同誌の存続については、近藤や山田の努力と熱意によるところが大きかったことが想像される。結社誌でも同人誌でもなく、いわば地域誌として会員のそれぞれが個として短歌に関わるかたちで、同誌が三十余年間にわたって存続したことは高く評価されて良い。近藤には、歌集『虚実集』(昭和四十七年六月刊)、山田には歌集『神の目の藍』(昭和六十年六月刊)、『沙漠の星より』(平成二十三年十一月刊)がある。歌集『神の目の藍』から山田の歌三首を引いておく。
くたくたに頭疲れてわれは見る遠州灘の神の目の藍
水汲みにはげしく呼吸(いき)をつかいたる埴輪のおんなの立つや夕ぐれ
ころがりてまた転がれるたましいが火炎の中に昨夜よりおらぶ
【短歌誌『翔る』】
なお、山田は平成八年一月短歌結社・翔短歌会(後に翔る短歌会と改称)を創立、同三月短歌誌『翔る』(隔月刊)を創刊している。
【村木道彦】
昭和三十九年から四十年にかけて、七冊のみが刊行された短歌の月刊誌『ジュルナール律』誌上に作品を発表、一躍歌壇の注目を集めた村木道彦は、当時慶應義塾大学の四年生であった。村木はその後、歌集『天唇』(昭和四十九年)を出すが、以後は長らく作歌を中断することとなる。現代歌壇へいわば彗星(すいせい)のように現れ消えていったのであるが、その短歌作品は不滅の光を放っている。彼の歌に触れることなく現代短歌が語られることはない。『岩波現代短歌辞典』で、三枝浩樹は村木について次のように解説している。
「ジュルナール律」に「緋の椅子」一〇首を発表、中井英夫、塚本邦雄らの激賞を受け、衝撃的なデビューを果たす。仮名文字の多用、植物的な感性、そして政治的な時代にあえてノンポリティカルでありつづけた村木の歌にはほかのどこにも見られない不思議な沈黙と憂愁がかたどられていた。佐佐木幸綱(ゆきつな)より少し遅れて登場した世代を代表する一人として注目された。
【『天唇』】

図2-56 『天唇』
さて、その村木道彦が、実は浜松と深い関係にあることは意外に知られていない。昭和四十年に慶應義塾大学を卒業した村木は、高校の国語教師として静岡県に赴任する。最初の勤務校は県立浜松工業高校。次いで、県立浜松西高校に移る。前に記した歌集『天唇』の上梓は同校に在職中のことであった。現在、同集を手にすることはほとんど不可能に近いが、国文社から出されている現代歌人文庫の中の一冊『村木道彦歌集』には『天唇』の作品すべてが収められており、さらに未刊歌集の作品、歌論、また中井英夫、塚本邦雄らの村木道彦論が掲載されていて、ほぼ村木の全貌をうかがうことが出来る。
ここでは特に秀歌として名高い「緋の椅子」の一連十首(『ジュルナール律』昭和40年2月号に掲載)の中の五首を引いておく。
水風呂にみずみちたればとっぷりとくれてうたえるただ麦畑
するだろう ぼくをすてたるものがたりマシュマロくちにほおばりながら
あわあわといちめんすけてきしゆえにひのくれがたをわれは淫らなり
黄のはなのさきていたるを せいねんのゆからあがりしあとの夕闇
めをほそめみるものなべてあやうきか あやうし緋色の一脚の椅子
その後の村木であるが、静岡県西部の幾つかの県立高校に勤務。この間、昭和五十二年をもって作歌を中断するが、平成二十年に至って実に三十四年ぶりに第二歌集『存在の夏』(ながらみ書房)を刊行した。
なお、平成十七年に改定された浜松市立高校の校歌は村木の作詞によるものであることを付記しておく。