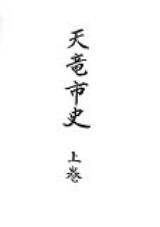 | 『天竜市史 上巻』 天竜市役所 昭和五十六年 |
| 【自然環境編】 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 【原始・古代編】 第一章 第二章 【中世編】 第一章 第二章 第三章 【近世編】 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 【文化編】 第一章 第二章 第三章 |
| 目次 | ■■ | ページ | 画像 | |||
| 自然環境編 | ■■ | ■■ | ■■ | |||
| ■■ | 第一章 天竜市の位置 | ■■ | 一 |  | ||
| ■■ | ||||||
| ■■ | 第二章 地形 | ■■ | 一 |  | ||
| ■■ | ||||||
| ■■ | 第三章 地質構造 | ■■ | ■■ | ■■ | ||
| ■■ | ■■ | 第一節 断層 | ■■ | 二 |  | |
| ■■ | ■■ | 第二節 三波川変成岩帯 | ■■ | 五 |  | |
| ■■ | ■■ | 第三節 貫入岩 | ■■ | 六 |  | |
| ■■ | ■■ | 第四節 秩父古生層 | ■■ | 一〇 |  | |
| ■■ | ■■ | 第五節 四万十帯 | ■■ | 一一 |  | |
| ■■ | ■■ | 第六節 二俣地溝帯 | ■■ | 一二 |  | |
| ■■ | ■■ | 第七節 万瀬地溝帯 | ■■ | 一四 |  | |
| ■■ | ■■ | 第八節 洪積層(赤土) | ■■ | 一四 |  | |
| ■■ | ■■ | 第九節 沖積層 | ■■ | 一六 |  | |
| ■■ | ||||||
| ■■ | 第四章 気候 | ■■ | ■■ | ■■ | ||
| ■■ | ■■ | 第一節 気候帯 | ■■ | 二〇 |  | |
| ■■ | ■■ | 第二節 日本の気候 | ■■ | 二四 |  | |
| ■■ | ■■ | 第三節 天竜市の気候 | ■■ | 二八 |  | |
| ■■ | ■■ | 第四節 気候の変動 | ■■ | 三二 |  | |
| ■■ | ||||||
| ■■ | 第五章 動植物 | ■■ | ■■ | ■■ | ||
| ■■ | ■■ | 第一節 天竜市の森林 | ■■ | 三七 |  | |
| ■■ | ■■ | 第二節 照葉樹林 | ■■ | 三七 |  | |
| ■■ | ■■ | 第三節 照葉樹林帯の農耕文化 | ■■ | 三九 |  | |
| ■■ | ■■ | 第四節 茶とみかん | ■■ | 四八 |  | |
| ■■ | ■■ | 第五節 けもの | ■■ | 四九 |  | |
| ■■ | ■■ | 第六節 とり | ■■ | 四九 |  | |
| ■■ | ||||||
| ■■ | 第六章 生活の場としての天竜市 | ■■ | ■■ | ■■ | ||
| ■■ | ■■ | 第一節 すみか | ■■ | 五四 |  | |
| ■■ | ■■ | 第二節 農業の基本形態 | ■■ | 五九 |  | |
| ■■ | ■■ | 第三節 道と川 | ■■ | 六一 |  | |
| ■■ | ■■ | 第四節 天災 | ■■ | 六四 |  | |
| ■■ | ||||||
| 原始・古代編 | ■■ | ■■ | ■■ | |||
| ■■ | 第一章 原始の天竜市域 | ■■ | ■■ | ■■ | ||
| ■■ | ■■ | 第一節 人類の登場と天竜市 | ■■ | 六七 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 人類の化石 浜北人 先土器時代 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第二節 農業以前の天竜市 | ■■ | 七二 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 土器と弓矢の発明 天竜市最古の土器 縄文時代の区分 中期縄文文化 後期縄文文化 晩期縄文文化 その他の遺跡と遺物 縄文時代のくらし 縄文時代の生活圏 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第三節 水田農業の開始と天竜市 | ■■ | 一三一 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 農業社会への転換 農業社会の発展 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ||||||
| ■■ | 第二章 古代の天竜市域 | ■■ | ■■ | ■■ | ||
| ■■ | ■■ | 第一節 光明山古墳 | ■■ | 一三九 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 古墳の成立 光明山古墳 古墳時代の遺跡と遺物 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第二節 天竜市の古墳群 | ■■ | 一五三 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 市内の古墳と副葬品 古墳群とその時代背影 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第三節 律令制と天竜市 | ■■ | 一七〇 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 律令制 奈良・平安時代の遺跡と遺物 律令制下の天竜市域 律令制の崩壊 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第四節 山香郡の分置と天竜市域 | ■■ | 一九四 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 山香郡の分置 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第五節 山香荘の成立と荘域 | ■■ | 一九六 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 山香庄 年貢・公事・夫役 浜松荘・阿多古郷 磐田郡山香郷 農民の生活と支配機構 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ||||||
| 中世編 | ■■ | ■■ | ■■ | |||
| ■■ | 第一章 鎌倉・室町時代 | ■■ | ■■ | ■■ | ||
| ■■ | ■■ | 第一節 鎌倉時代の北遠地方 | ■■ | 二〇七 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 鎌倉幕府の成立 遠江守安田義定 承久の乱 天野氏の山香荘入部 鎌倉幕府の滅亡 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第二節 南北朝時代の北遠地方 | ■■ | 二二一 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 建武の新政 南朝と遠江 二俣郷 守護大名今川氏 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第三節 室町時代の北遠地方 | ■■ | 二三五 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 室町幕府 斯波氏の遠江支配 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ||||||
| ■■ | 第二章 戦国時代 | ■■ | ■■ | ■■ | ||
| ■■ | ■■ | 第一節 戦国時代の北遠地方 | ■■ | 二四五 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 応仁の乱 今川義忠の活動 今川・斯波両氏の対立 今川氏親の遠江進入 斯波義雄 今川氏に対する国人の動向 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第二節 二俣城主 | ■■ | 二五七 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 二俣城主の性格 瀬名一秀 朝比奈時茂 二俣昌長 松井貞宗 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第三節 引馬城主の所領 | ■■ | 二七三 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 阿多古地方 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第四節 今川氏の領国支配 | ■■ | 二七五 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 戦国大名今川氏 今川家臣団と軍事力 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第五節 今川氏の民政 | ■■ | 二八四 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 今川仮名目録 土地と農民支配 農民の負担と階層 戦国時代の農村 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第六節 徳川・武田両氏の対立と今川氏の滅亡 | ■■ | 二八九 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 桶狭間戦 遠州忩劇 二俣城の攻防 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第七節 徳川支配下の北遠地方 | ■■ | 三〇六 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 大久保忠世の二俣城入城 徳川信康 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第八節 堀尾氏の北遠支配 | ■■ | 三二〇 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 堀尾氏の北遠支配と転封 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ||||||
| ■■ | 第三章 中世の城・館 | ■■ | ■■ | ■■ | ||
| ■■ | ■■ | 第一節 城郭 | ■■ | 三二九 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 中世の城郭 二俣城 鳥羽山城 笹岡城 高岡城 光明城 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第二節 居館 | ■■ | 三三六 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 中世の館 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ||||||
| 近世編 | ■■ | ■■ | ■■ | |||
| ■■ | 第一章 幕藩制確立期の天竜市域 | ■■ | ■■ | ■■ | ||
| ■■ | ■■ | 第一節 政治情勢 | ■■ | 三四一 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 慶長の支配関係 徳川頼宣の北遠支配 大坂の役出陣 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第二節 検地と支配機構 | ■■ | 三五二 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 慶長の総検地 寛文・延宝の検地 新田開発 寺社領安堵 朱印地と除地 天領と代官 郷宿と郡中総代 女・鉄砲改め | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第三節 年貢と諸役 | ■■ | 三七九 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 本途物成 永定免 小物成と立物二割出 山銭・山札銭・山手米 駒役 鉄砲役 網役 黐役 川船運上 高掛り三役 国役 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ||||||
| ■■ | 第二章 近世村落の様相 | ■■ | ■■ | ■■ | ||
| ■■ | ■■ | 第一節 村政のしくみ | ■■ | 四〇一 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 村の構造 村役人 五人組 宗門改め 村の重要な書類 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第二節 人々のくらし | ■■ | 四一八 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 生活環境 獣害と鉄砲 火の用心 衣・食・住 総人口と世帯数 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ||||||
| ■■ | 第三章 天竜川の開発と農林業の発展 | ■■ | ■■ | ■■ | ||
| ■■ | ■■ | 第一節 天竜川の榑木輸送 | ■■ | 四四七 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 榑木と日明御綱場 日明での榑木処分 榑木御綱役 榑木山番役 榑木筏役 山形屋 御綱留の廃止 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第二節 天竜川の舟運 | ■■ | 四六六 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 角倉船の出現 天竜川の通船 物資の輸送 鹿島十分一番所 塩見渡入会渡場 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第三節 焼畑農業と商業的農業 | ■■ | 四八九 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 焼畑農業 商業的農業 茶 椿 阿多古紙 農閑余業 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第四節 林業の発達と推移 | ■■ | 五〇八 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 近世初期までの林業 育成林業 民間材の流通 柿板と青山善右衛門 商業融資の活発化 材木取引資金 江戸城御用材 天竜林業の特色 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第五節 入会山と山論 | ■■ | 五三八 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 光明山山論 大谷山・大沢山入会山争論 阿蔵山入会山論 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ||||||
| ■■ | 第四章 幕政改革と村々の動き | ■■ | ■■ | ■■ | ||
| ■■ | ■■ | 第一節 正徳・享保期の改革 | ■■ | 五五一 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 村役人制度の改革 百姓代の出現 増免反対運動 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第二節 寛政・天保の改革 | ■■ | 五六四 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 天明期の私領替え 寛政の改革 天保の改革 弘化期の私領替え | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第三節 村方騒動 | ■■ | 五七四 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 長沢村騒動 大栗安村騒動 巡見使入用騒動 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ||||||
| ■■ | 第五章 江戸時代の飢饉と災害 | ■■ | ■■ | ■■ | ||
| ■■ | ■■ | 第一節 飢饉と貯穀の奨励 | ■■ | 五八九 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 享保の飢饉 天明の飢饉 二俣村の打ちこわし 天保の飢饉 慶応の飢饉 貯穀の奨励 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第二節 水害と川除御普請 | ■■ | 六一一 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 江戸時代の水害 川除御普請 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第三節 袴田喜長と鳥羽山の掘割 | ■■ | 六二四 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 二俣村名主袴田甚右衛門 水害になやむ二俣村 鳥羽山堀割第一期工事 第二期工事 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第四節 大火と大地震 | ■■ | 六三五 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 大火に怯える村々 安政の大地震 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ||||||
| ■■ | 第六章 幕藩制社会の動揺 | ■■ | ■■ | ■■ | ||
| ■■ | ■■ | 第一節 村落構造の変化 | ■■ | 六四一 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 分付百姓の自立 村入用の変化 農村分解の進行 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第二節 農民闘争の展開 | ■■ | 六五六 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 無礼塩一件 弘化期の塩出入一件 船明村庄屋の不正 増助郷と代助郷 熊村の無宿人騒動 鹿島分一一揆 二俣蓑かぶり一揆 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第三節 幕末社会の不安と動揺 | ■■ | 六八七 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 異国船渡来と開国貿易 米価の高騰 長州征討と御用金賦課 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第四節 江戸幕府倒壊前後の情勢 | ■■ | 六九五 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 「ええじゃないか」乱舞 中泉代官領から府中藩へ 遠州報国隊と勤王家 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ||||||
| 文化編 | ■■ | ■■ | ■■ | |||
| ■■ | 第一章 江戸時代の文化 | ■■ | ■■ | ■■ | ||
| ■■ | ■■ | 第一節 江戸時代の天竜市域の文化 | ■■ | 七〇五 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 天竜市域の文人 俳諧 和歌 寺小屋 娯楽 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ||||||
| ■■ | 第二章 内山真龍の学問と研究 | ■■ | ■■ | ■■ | ||
| ■■ | ■■ | 第一節 背景 | ■■ | 七三三 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 内山真龍 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第二節 血縁地縁社会の俳諧志向 | ■■ | 七三五 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 青年期の真龍 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第三節 賀茂真淵への入門 | ■■ | 七三八 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 賀茂真淵と真龍 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第四節 賀茂真淵の指導 | ■■ | 七三九 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 明和二年の真龍 賀茂真淵の学風 歌文の指導 記紀会読会 真淵の真龍観 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第五節 渡辺蒙庵への入門 | ■■ | 七五一 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 蒙庵の講義と誘掖 真龍の交友 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第六節 田中道麿への問学 | ■■ | 七五七 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 田中道麿と真龍 道麿書状にみる真龍の学問 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第七節 著作活動 | ■■ | 七六六 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 著作一覧 出雲風土記解 遠江国風土記伝 新撰姓氏録注 国図 日本紀類聚解 真龍に託された課題 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第八節 真龍の今日的意義 | ■■ | 七九九 |  | |
| ■■ | ||||||
| ■■ | 第三章 信仰 | ■■ | ■■ | ■■ | ||
| ■■ | ■■ | 第一節 神社 | ■■ | 八〇三 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 中世までの神社 江戸時代の神社政策 社領 祭礼 社殿 市内の神社 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第二節 寺院 | ■■ | 八一八 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 山岳信仰と仏教 天竜市内寺院の開創 江戸時代の仏教政策 市内寺院一覧 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第三節 民間信仰 | ■■ | 八四三 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 光明山信仰 秋葉山信仰 秋葉街道 講 石仏と小祠 自然信仰 市内の石仏・小祠一覧 | ■■ | ■■ | ■■ |
| ■■ | ■■ | 第四節 おこないと高踊 | ■■ | 八七一 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | おこないと田楽 懐山のおこない 神沢のおこない 詞章の検討 市内各地の伝承 熊平の高踊り 遠州大念仏 | ■■ | ■■ | ■■ |