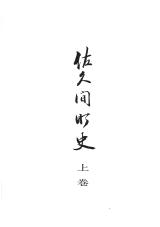| 目次 | ■■ | ページ | 画像 |
| 序 佐久間町長 北井三子夫 | ■■ | ■■ |  |
| 佐久間町史の発刊を祝う 佐久間町議会議長 北村久太郎 | ■■ | ■■ |  |
| 佐久間町史の完成を喜ぶ 元佐久間町長 山田保夫 | ■■ | ■■ |  |
| |
| 総説 佐久間町の自然 | ■■ | 一 |  |
| ■■ | 第一節 佐久間町の地形概観 | ■■ | 三 |  |
| ■■ | 第二節 佐久間町の地質概要 | ■■ | 六 |  |
| ■■ | ■■ | (1)中央構造線と赤石裂線 | ■■ | 六 |  |
| ■■ | ■■ | (2)内帯(領家帯) | ■■ | 八 |  |
| ■■ | ■■ | (3)外帯(三波川変成帯) | ■■ | 八 |  |
| ■■ | ■■ | (4)外帯(秩父帯と光明帯群) | ■■ | 八 |  |
| ■■ | ■■ | (5)第三系と第四系 | ■■ | 九 |  |
| ■■ | 第三節 中央構造線の研究史 | ■■ | 九 |  |
| ■■ | 第四節 鹿塩構造帯 | ■■ | 一二 |  |
| ■■ | ■■ | (1)鹿塩構造帯の研究史 | ■■ | 一二 |  |
| ■■ | ■■ | (2)鹿塩圧砕岩類 | ■■ | 一六 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (イ)火成岩源圧砕岩(ポーフィロイド様岩) | ■■ | 一六 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ロ)細粒緻密珪質岩 | ■■ | 一七 |  |
| ■■ | 第五節 領家変成帯(内帯) | ■■ | 一九 |  |
| ■■ | ■■ | (1)領家変成帯の研究史 | ■■ | 一九 |  |
| ■■ | ■■ | (2)領家帯の岩石 | ■■ | 二二 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (イ)黒雲母ホルンフェルス | ■■ | 二二 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ロ)花崗岩類 | ■■ | 二三 |  |
| ■■ | 第六節 三波川変成帯(外帯) | ■■ | 二七 |  |
| ■■ | ■■ | (1)三波川変成帯の研究史 | ■■ | 二七 |  |
| ■■ | ■■ | (2)天竜川地域の三波川変成帯について | ■■ | 三三 |  |
| ■■ | 第七節 赤石裂線以東の中古生界 | ■■ | 三九 |  |
| ■■ | ■■ | (1)当地における分布 | ■■ | 三九 |  |
| ■■ | ■■ | (2)赤石裂線の研究史 | ■■ | 四〇 |  |
| ■■ | 第八節 佐久間町南西部に分布する第三系 | ■■ | 四一 |  |
| ■■ | 第九節 気候と土地利用 | ■■ | 四六 |  |
| ■■ | ■■ | (1)気候 | ■■ | 四六 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (イ)気候の概観 | ■■ | 四六 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ロ)気温 | ■■ | 四九 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ハ)降水量 | ■■ | 五五 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ニ)風・日照その他 | ■■ | 六一 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ホ)町内各地の気候の差 | ■■ | 六三 |  |
| ■■ | 第十節 土地利用 | ■■ | 六九 |  |
| ■■ | ■■ | (1)土地利用の概観 | ■■ | 六九 |  |
| ■■ | ■■ | (2)平地・緩傾斜地 | ■■ | 七〇 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (イ)谷底平地 | ■■ | 七〇 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ロ)河岸段丘 | ■■ | 七三 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ハ)山腹緩斜面 | ■■ | 七五 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ニ)山頂緩斜面 | ■■ | 八二 |  |
| ■■ | ■■ | (3)日射と土地利用 | ■■ | 八二 |  |
| ■■ | ■■ | (4)土地利用の現況 | ■■ | 八五 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (イ)集落 | ■■ | 八五 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ロ)耕地 | ■■ | 九二 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ハ)森林 | ■■ | 九六 |  |
| ■■ | 第十一節 植物と動物 | ■■ | 九九 |  |
| ■■ | ■■ | (1)植物相 | ■■ | 一〇一 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (イ)佐久間町のシダ植物 | ■■ | 一〇三 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ロ)佐久間町の木本植物 | ■■ | 一〇三 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ハ)特記すべき植物 | ■■ | 一〇六 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ニ)植物目録 | ■■ | 一〇八 |  |
| ■■ | ■■ | (2)動物相 | ■■ | 一三一 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (イ)昆虫類 | ■■ | 一三一 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ロ)甲殻類 | ■■ | 一三一 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ハ)魚類 | ■■ | 一三二 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ニ)両生類 | ■■ | 一三二 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ホ)爬虫類 | ■■ | 一三三 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ヘ)猟と哺乳類・鳥類 | ■■ | 一三三 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ト)特記すべき動物 | ■■ | 一三五 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (チ)動物目録 | ■■ | 一三八 |  |
| |
| 第一章 半場遺跡と平沢遺跡 | ■■ | 一五九 |  |
| ■■ | 第一節 半場遺跡とその時代 | ■■ | 一六一 |  |
| ■■ | ■■ | (1)はじめに | ■■ | 一六一 |  |
| ■■ | ■■ | (2)半場遺跡 | ■■ | 一六二 |  |
| ■■ | ■■ | (3)南野田遺跡 | ■■ | 一八三 |  |
| ■■ | ■■ | (4)その他の遺跡 | ■■ | 一八六 |  |
| ■■ | ■■ | (5)先史時代の生活 | ■■ | 一九一 |  |
| ■■ | ■■ | (6)縄文時代における佐久間地域の特質 | ■■ | 二〇四 |  |
| ■■ | 第二節 平沢遺跡とその時代 | ■■ | 二一二 |  |
| ■■ | ■■ | (1)縄文文化から弥生文化への転換 | ■■ | 二一二 |  |
| ■■ | ■■ | (2)平沢遺跡 | ■■ | 二一七 |  |
| ■■ | ■■ | (3)その他の弥生時代遺跡 | ■■ | 二二四 |  |
| ■■ | ■■ | (4)弥生時代の生活と佐久間地域の特質 | ■■ | 二二六 |  |
| ■■ | 第三節 光明寺古墳と大森古墳のころ | ■■ | 二三二 |  |
| ■■ | ■■ | (1)古墳時代のあらまし | ■■ | 二三二 |  |
| ■■ | ■■ | (2)古墳時代の佐久間地方 | ■■ | 二三四 |  |
| |
| 第二章 秋葉寺と山香荘 | ■■ | 二三七 |  |
| ■■ | 第一節 大化前代の佐久間 | ■■ | 二三九 |  |
| ■■ | 第二節 律令制下の佐久間 | ■■ | 二四〇 |  |
| ■■ | 第三節 山香郡と秋葉寺 | ■■ | 二四三 |  |
| ■■ | ■■ | (1)律令体制の衰退 | ■■ | 二四三 |  |
| ■■ | ■■ | (2)山香郡の分立 | ■■ | 二四五 |  |
| ■■ | ■■ | (3)式内社と秋葉寺 | ■■ | 二四九 |  |
| ■■ | 第四節 長講堂領山香荘 | ■■ | 二五六 |  |
| ■■ | ■■ | (1)山香荘の成立 | ■■ | 二五六 |  |
| ■■ | ■■ | (2)年貢公事と兵士役 | ■■ | 二五八 |  |
| ■■ | ■■ | (3)荘園の構造と農民生活 | ■■ | 二六二 |  |
| |
| 第三章 天野氏と奥山氏 | ■■ | 二六五 |  |
| ■■ | 第一節 天野氏の入部 | ■■ | 二六七 |  |
| ■■ | ■■ | (1)鎌倉幕府と地頭制度 | ■■ | 二六七 |  |
| ■■ | ■■ | (2)天野氏の系譜 | ■■ | 二六八 |  |
| ■■ | ■■ | (3)天野氏の発展 | ■■ | 二七二 |  |
| ■■ | ■■ | (4)地頭天野氏の在地支配 | ■■ | 二七五 |  |
| ■■ | 第二節 下地中分と争論 | ■■ | 二七九 |  |
| ■■ | ■■ | (1)領家方と地頭方 | ■■ | 二七九 |  |
| ■■ | ■■ | (2)分割相続と所領争い | ■■ | 二八八 |  |
| ■■ | ■■ | (3)代官屋敷と神社 | ■■ | 二九二 |  |
| ■■ | ■■ | (4)地頭と農民 | ■■ | 二九五 |  |
| ■■ | 第三節 南北朝動乱期の北遠 | ■■ | 二九八 |  |
| ■■ | ■■ | (1)南北朝の内乱 | ■■ | 二九八 |  |
| ■■ | ■■ | (2)内乱期の北遠 | ■■ | 二九九 |  |
| ■■ | ■■ | (3)尹良親王伝説 | ■■ | 三〇八 |  |
| ■■ | ■■ | (4)奥山氏のおこりと所領争い | ■■ | 三一二 |  |
| |
| 第四章 戦国動乱と在地領主 | ■■ | 三一九 |  |
| ■■ | 第一節 遠江の動乱 | ■■ | 三二一 |  |
| ■■ | ■■ | (1)守護と国人 | ■■ | 三二一 |  |
| ■■ | ■■ | (2)天野・奥山の動向 | ■■ | 三二五 |  |
| ■■ | ■■ | (3)今川勢力の進展と天野氏 | ■■ | 三三〇 |  |
| ■■ | 第二節 戦国大名と在地領主 | ■■ | 三三三 |  |
| ■■ | ■■ | (1)今川氏の遠江支配 | ■■ | 三三三 |  |
| ■■ | ■■ | (2)天野安芸守と小四郎 | ■■ | 三三八 |  |
| ■■ | ■■ | (3)軍事動員と軍役 | ■■ | 三四九 |  |
| ■■ | ■■ | (4)大名権力と在地領主 | ■■ | 三五四 |  |
| ■■ | 第三節 在地領主と農民 | ■■ | 三六四 |  |
| ■■ | ■■ | (1)天野被官衆 | ■■ | 三六四 |  |
| ■■ | ■■ | (2)奥山氏と佐久間 | ■■ | 三七一 |  |
| ■■ | ■■ | (3)百姓と名職 | ■■ | 三七五 |  |
| ■■ | ■■ | (4)農民支配の動揺 | ■■ | 三八一 |  |
| ■■ | ■■ | (5)禅宗の布教と農民文化の源流 | ■■ | 三九二 |  |
| ■■ | 第四節 動乱期の北遠 | ■■ | 四〇三 |  |
| ■■ | ■■ | (1)今川氏の衰退 | ■■ | 四〇三 |  |
| ■■ | ■■ | (2)家康の遠江侵入と北遠 | ■■ | 四〇九 |  |
| ■■ | ■■ | (3)青崩越と三方原の戦 | ■■ | 四一二 |  |
| ■■ | ■■ | (4)犬居攻めと長篠の戦い | ■■ | 四一八 |  |
| ■■ | ■■ | (5)天野氏の遠州退去と奥山惣十郎 | ■■ | 四二四 |  |
| |
| 第五章 公門庄屋と公門百姓―幕藩体制社会の成立と佐久間― | ■■ | 四二九 |  |
| ■■ | 第一節 中世の残像 | ■■ | 四三一 |  |
| ■■ | ■■ | (1)天保八年「大井村高反別村差出明細帳」 | ■■ | 四三一 |  |
| ■■ | ■■ | (2)「正中二年癸亥十月朔日」―私年号の周辺― | ■■ | 四三五 |  |
| ■■ | 第二節 幕藩権力の浸透過程―北遠地方を中心にみた― | ■■ | 四四一 |  |
| ■■ | ■■ | (1)天野氏没落のあとさき | ■■ | 四四一 |  |
| ■■ | ■■ | (2)徳川家康の北遠支配 | ■■ | 四四九 |  |
| ■■ | ■■ | (3)秀吉政権の北遠支配 | ■■ | 四五八 |  |
| ■■ | 第三節 家康政権の展開―代官片切の登場や船役朱印状― | ■■ | 四六二 |  |
| ■■ | ■■ | (1)代官片切権右衛門の登場 | ■■ | 四六二 |  |
| ■■ | ■■ | (2)船役朱印状の周辺―天竜川の舟運開発― | ■■ | 四七〇 |  |
| ■■ | 第四節 中野七蔵の死―近世村落への道標 | ■■ | 四七五 |  |
| ■■ | ■■ | (1)大坂冬夏の陣 | ■■ | 四七五 |  |
| ■■ | ■■ | (2)遠州代官中野七蔵の北遠経営 | ■■ | 四八二 |  |
| ■■ | 第五節 近世村落の素顔 | ■■ | 四八八 |  |
| ■■ | ■■ | (1)「控百姓」の問題 | ■■ | 四八八 |  |
| ■■ | ■■ | (2)郷士の成立の事情 | ■■ | 五〇四 |  |
| ■■ | ■■ | (3)組庄屋 | ■■ | 五一二 |  |
| |
| 第六章 村落生活の諸相 | ■■ | 五三三 |  |
| ■■ | 第一節 山と川と生活と | ■■ | 五三五 |  |
| ■■ | ■■ | (1)山肌に開く生活 | ■■ | 五三五 |  |
| ■■ | ■■ | (2)河谷に開かれた生活 | ■■ | 五四〇 |  |
| ■■ | 第二節 人々のくらしと生産基盤 | ■■ | 五五三 |  |
| ■■ | ■■ | (1)田と畑 | ■■ | 五五三 |  |
| ■■ | ■■ | (2)農業生産と租税収取 | ■■ | 五五九 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (イ)農業生産の動向 | ■■ | 五五九 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ロ)租税集取の展開―夏成と冬成― | ■■ | 五六六 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ハ)小物成や立物二割出 | ■■ | 五七一 |  |
| ■■ | 第三節 生活の展開 | ■■ | 五七八 |  |
| ■■ | ■■ | (1)生産生活と消費生活 | ■■ | 五七八 |  |
| ■■ | ■■ | (2)飢饉と貯穀 | ■■ | 五八七 |  |
| |
| 第七章 天竜川榑木輸送の展開と林業の発達―木材生産地への道程― | ■■ | 六〇五 |  |
| ■■ | 第一節 天竜川の舟運 | ■■ | 六〇七 |  |
| ■■ | ■■ | (1)角倉了以と「舟役朱印状」 | ■■ | 六〇七 |  |
| ■■ | ■■ | (2)天竜川舟運開発の原点 | ■■ | 六一〇 |  |
| ■■ | 第二節 天竜川榑木輸送とその展開 | ■■ | 六一三 |  |
| ■■ | ■■ | (1)信州伊那郡の「榑木」と「榑木成村」 | ■■ | 六一三 |  |
| ■■ | ■■ | (2)日明「御綱場役」の村々 | ■■ | 六二六 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (イ)白口、小藤 | ■■ | 六四五 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ロ)御榑木御綱普請 | ■■ | 六四九 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ハ)本綱と袋綱 | ■■ | 六五八 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ニ)榑木の流着 | ■■ | 六六五 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ホ)小屋 | ■■ | 六六八 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ヘ)人足と扶持 | ■■ | 六七〇 |  |
| ■■ | ■■ | (3)榑木輸送の変質 | ■■ | 六七八 |  |
| |
| 第八章 林業の発達と鹿島十分一騒動 | ■■ | 六九七 |  |
| ■■ | 第一節 木材生産地への道 | ■■ | 六九九 |  |
| ■■ | ■■ | (1)勝木家年々覚書 | ■■ | 六九九 |  |
| ■■ | ■■ | (2)池田舟橋宛物 | ■■ | 七〇二 |  |
| ■■ | ■■ | (3)植林奨励策の展開 | ■■ | 七一〇 |  |
| ■■ | 第二節 木材流通の展開とその障害 | ■■ | 七三〇 |  |
| ■■ | ■■ | (1)天保八年「海船運賃議定書」 | ■■ | 七三〇 |  |
| ■■ | ■■ | (2)廻船仕法改革の要求 | ■■ | 七三四 |  |
| ■■ | 第三節 鹿島十分一騒動の展開 | ■■ | 七五三 |  |
| ■■ | ■■ | (1)天保改革と鹿島十分一 | ■■ | 七五三 |  |
| ■■ | ■■ | (2)鹿島十分一所の再興と村々―山中七三ヵ村の推移と結果― | ■■ | 七六二 |  |
| ■■ | ■■ | (3)十分一騒動の展開 | ■■ | 七七四 |  |
| ■■ | ■■ | (4)安政五年「新分一議定目録」の人々 | ■■ | 七九一 |  |
| ■■ | 第四節 椎茸栽培の発達 | ■■ | 七九八 |  |
| ■■ | ■■ | (1)椎茸栽培の定着 | ■■ | 七九八 |  |
| ■■ | ■■ | (2)旅椎茸師の活躍 | ■■ | 八〇三 |  |
| ■■ | ■■ | (3)地元椎茸師の成長 | ■■ | 八二〇 |  |
| ■■ | ■■ | (4)椎茸栽培技術の状況 | ■■ | 八二八 |  |
| |
| 編しゅう後記 若林淳之 | ■■ | ■■ |  |