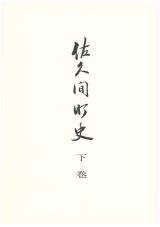| 目次 | ■■ | ページ | 画像 |
| 目次 | ■■ | ■■ |  |
| 序 佐久間町長 守屋 義雄 | ■■ | ■■ |  |
| 町史完結に寄せて 元佐久間町長 北井 三子夫 | ■■ | ■■ |  |
| 題字 山田 保夫氏 |
| |
| 序章 近代への胎動 | ■■ | 1 |  |
| ■■ | 第一節 胎動する近代の芽生え | ■■ | 3 |  |
| ■■ | ■■ | (1)ある医家の医学研究 | ■■ | 3 |  |
| ■■ | ■■ | (2)「あめり」という国 | ■■ | 10 |  |
| ■■ | ■■ | (3)北遠の国学運動 | ■■ | 13 |  |
| ■■ | 第二節 近代への陣痛 ある村方騒動の記録 | ■■ | 24 |  |
| ■■ | ■■ | (1)郷士と分付 | ■■ | 24 |  |
| ■■ | ■■ | (2)郷士の変質 | ■■ | 26 |  |
| ■■ | ■■ | (3)分付百姓の動向 | ■■ | 32 |  |
| ■■ | ■■ | (4)ある村方騒動の記録 | ■■ | 44 |  |
| |
| 第一章 明治維新と諸改革 | ■■ | 55 |  |
| ■■ | 第一節 名主から戸長へ | ■■ | 57 |  |
| ■■ | ■■ | (1)廃藩置県前後 | ■■ | 57 |  |
| ■■ | ■■ | (2)大区小区制 | ■■ | 58 |  |
| ■■ | 第二節 学制の展開 | ■■ | 69 |  |
| ■■ | ■■ | (1)学制頒布 | ■■ | 69 |  |
| ■■ | ■■ | (2)小学校の実態 | ■■ | 75 |  |
| ■■ | 第三節 徴兵制の施行 | ■■ | 81 |  |
| ■■ | ■■ | (1)徴兵令 | ■■ | 81 |  |
| ■■ | ■■ | (2)徴兵令への対応 | ■■ | 82 |  |
| ■■ | 第四節 地租改正 | ■■ | 93 |  |
| ■■ | ■■ | (1)地租改正の趣旨 | ■■ | 93 |  |
| ■■ | ■■ | (2)地租改正事業の経過と影響 | ■■ | 94 |  |
| ■■ | 第五節 文明開化と生活の近代化 | ■■ | 126 |  |
| ■■ | ■■ | (1)文明開化と衣食住 | ■■ | 126 |  |
| ■■ | ■■ | (2)小田敷日曜戸主会 | ■■ | 137 |  |
| ■■ | 第六節 地域開発の先覚者たち | ■■ | 142 |  |
| ■■ | ■■ | (1)矢高濤一 | ■■ | 142 |  |
| ■■ | ■■ | (2)四ツ門きん | ■■ | 157 |  |
| |
| 第二章 新しい村の成立と発展 | ■■ | 161 |  |
| ■■ | 第一節 近代日本の地方自治と佐久間 | ■■ | 163 |  |
| ■■ | ■■ | (1)地方三新法と区町村会 | ■■ | 163 |  |
| ■■ | ■■ | (2)市制・町村制の制定 | ■■ | 172 |  |
| ■■ | 第二節 浦川村・佐久間村・山香村・城西村の成立 | ■■ | 176 |  |
| ■■ | ■■ | (1)浦川村・佐久間村の新生と部落 | ■■ | 176 |  |
| ■■ | ■■ | (2)山香村・城西村の新生と部落 | ■■ | 180 |  |
| ■■ | 第三節 新しい村づくりの進展 | ■■ | 183 |  |
| ■■ | ■■ | (1)村政のにない手 | ■■ | 183 |  |
| ■■ | ■■ | (2)地方自治の中心課題 | ■■ | 201 |  |
| ■■ | 第四節 小学校教育の普及 | ■■ | 213 |  |
| ■■ | ■■ | (1)教育令時代の小学校 | ■■ | 213 |  |
| ■■ | ■■ | (2)小学校令と教育勅語 | ■■ | 221 |  |
| ■■ | 第五節 戦争への対応 | ■■ | 231 |  |
| ■■ | ■■ | (1)日清戦争 | ■■ | 231 |  |
| ■■ | ■■ | (2)日露戦争から第一次大戦へ | ■■ | 234 |  |
| |
| 第三章 王子製紙と久根鉱山 | ■■ | 241 |  |
| ■■ | 第一節 王子製紙 | ■■ | 243 |  |
| ■■ | ■■ | (1)気田工場の建設まで | ■■ | 243 |  |
| ■■ | ■■ | (2)わが国最初の木材パルプ工場 | ■■ | 247 |  |
| ■■ | ■■ | (3)中部工場の発足 | ■■ | 250 |  |
| ■■ | ■■ | (4)水害と火事の苦難 | ■■ | 258 |  |
| ■■ | ■■ | (5)原木から新聞用紙まで | ■■ | 267 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (イ)遠山山林 | ■■ | 267 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ロ)満島送材所 | ■■ | 270 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ハ)薪材生産 | ■■ | 271 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ニ)中部工場 | ■■ | 272 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ホ)製品の輸送 | ■■ | 278 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ヘ)王子と中部 | ■■ | 280 |  |
| ■■ | 第二節 久根鉱山 | ■■ | 284 |  |
| ■■ | ■■ | (1)明治三〇年の鉱害問題 | ■■ | 284 |  |
| ■■ | ■■ | (2)古河の進出 | ■■ | 291 |  |
| ■■ | ■■ | (3)久根本山と名合支山の地質 | ■■ | 294 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (イ)地質の概要 | ■■ | 294 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ロ)層状含銅硫化鉄鉱床の成因について | ■■ | 295 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ハ)久根本山について | ■■ | 299 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ニ)名合支山について | ■■ | 307 |  |
| ■■ | ■■ | (4)生産の消長 | ■■ | 312 |  |
| ■■ | ■■ | (5)鉱山の人々 | ■■ | 328 |  |
| |
| 第四章 茶業の発達 | ■■ | 345 |  |
| ■■ | 第一節 幕末・維新の産業 | ■■ | 347 |  |
| ■■ | ■■ | (1)明治五年上平山の産業 | ■■ | 347 |  |
| ■■ | ■■ | (2)楮・からし灰の流通 | ■■ | 353 |  |
| ■■ | ■■ | (3)経済生活の実像 | ■■ | 362 |  |
| ■■ | 第二節 茶生産の新展開 殖産興業の課題 | ■■ | 364 |  |
| ■■ | ■■ | (1)茶生産の発展 | ■■ | 365 |  |
| ■■ | ■■ | (2)茶業組合と改良委員 | ■■ | 368 |  |
| ■■ | ■■ | (3)茶生産の新展開 | ■■ | 388 |  |
| |
| 第五章 林業の発達 | ■■ | 393 |  |
| ■■ | 第一節 明治維新期の遠州木材 | ■■ | 395 |  |
| ■■ | ■■ | (1)東京市中木材輸入元国分表 | ■■ | 395 |  |
| ■■ | ■■ | (2)明治初年における林業の動向 | ■■ | 401 |  |
| ■■ | 第二節 金原明善の林業開発 | ■■ | 409 |  |
| ■■ | ■■ | (1)川上と川下 | ■■ | 409 |  |
| ■■ | ■■ | (2)瀬尻の献植と金原林 | ■■ | 412 |  |
| ■■ | 第三節 山林組合の成立と林業 | ■■ | 423 |  |
| ■■ | ■■ | (1)浦川村・山香村山林組合の成立 | ■■ | 423 |  |
| ■■ | ■■ | (2)山林組合の活動 | ■■ | 435 |  |
| ■■ | 第四節 天竜川材木商同業組合の成立と発展 木材流通の諸問題 | ■■ | 440 |  |
| ■■ | ■■ | (1)天竜川材木商同業組合の成立 | ■■ | 440 |  |
| ■■ | ■■ | (2)天竜川材木商同業組合第一部の事業 | ■■ | 456 |  |
| ■■ | ■■ | (3)記号印章 | ■■ | 463 |  |
| ■■ | ■■ | (4)天竜川材木商同業組合の事業 | ■■ | 476 |  |
| ■■ | 第五節 木材輸送の諸問題 筏船 | ■■ | 487 |  |
| ■■ | ■■ | (1)筏や船 | ■■ | 487 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (イ)筏組 | ■■ | 490 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ロ)船積 | ■■ | 503 |  |
| ■■ | 第六節 道路 産業振興と生活向上の運動 | ■■ | 518 |  |
| ■■ | ■■ | (1)道路網の整備にかける人々 | ■■ | 519 |  |
| |
| 第六章 三信鉄道の開発 | ■■ | 579 |  |
| ■■ | 第一節 国鉄建設の運動 | ■■ | 581 |  |
| ■■ | ■■ | (1)鉄道網案の発表 | ■■ | 581 |  |
| ■■ | ■■ | (2)改正鉄道敷設法の成立 | ■■ | 582 |  |
| ■■ | ■■ | (3)新線建設の遅延 | ■■ | 586 |  |
| ■■ | 第二節 三信鉄道の創立 | ■■ | 588 |  |
| ■■ | ■■ | (1)鉄道敷設後援会の活動 | ■■ | 588 |  |
| ■■ | 第三節 全線開通まで | ■■ | 601 |  |
| ■■ | ■■ | (1)株式募集と払込み | ■■ | 601 |  |
| ■■ | ■■ | (2)トンネルと鉄橋 | ■■ | 605 |  |
| ■■ | ■■ | (3)工事の経過 | ■■ | 608 |  |
| ■■ | 第四節 三信鉄道の村への影響 | ■■ | 621 |  |
| ■■ | ■■ | (1)停車場問題 | ■■ | 621 |  |
| ■■ | ■■ | (2)旅客輸送の変化 | ■■ | 625 |  |
| ■■ | ■■ | (3)貨物輸送の変遷 | ■■ | 627 |  |
| ■■ | 第五節 飯田線の移り変り | ■■ | 633 |  |
| ■■ | ■■ | (1)戦後の輸送 | ■■ | 633 |  |
| ■■ | ■■ | (2)国鉄バス | ■■ | 635 |  |
| ■■ | ■■ | (3)転落事故と安全対策 | ■■ | 636 |  |
| ■■ | ■■ | (4)佐久間ダム関係の輸送 | ■■ | 638 |  |
| ■■ | ■■ | (5)水窪廻り付替線 | ■■ | 639 |  |
| ■■ | ■■ | (6)その後の飯田線 | ■■ | 641 |  |
| |
| 第七章 太平洋戦争と生活 | ■■ | 643 |  |
| ■■ | 第一節 満州事変から太平洋戦争へ | ■■ | 645 |  |
| ■■ | ■■ | (1)昭和初年の村々 | ■■ | 645 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (イ)土地の状況と外から見た佐久間 | ■■ | 649 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ロ)主な職業とその動態 | ■■ | 650 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ハ)農林業のすがた | ■■ | 652 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ニ)生活の実相 | ■■ | 656 |  |
| ■■ | ■■ | (2)恐慌下における諸物価等の状態 | ■■ | 661 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (イ)茶 | ■■ | 661 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ロ)繭 | ■■ | 662 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ハ)木材価の変動 | ■■ | 665 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ニ)米価 | ■■ | 668 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ホ)役場吏員の給料もさがる | ■■ | 671 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ヘ)労働賃金の下落 | ■■ | 673 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ト)給料の支払延期 | ■■ | 673 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (チ)欠食児童の存在 | ■■ | 674 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (リ)浦川銀行の赤字 | ■■ | 674 |  |
| ■■ | ■■ | (3)恐慌下における対応策 | ■■ | 675 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (イ)為政者側の基本的対応策 | ■■ | 675 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ロ)税滞納の防止 | ■■ | 678 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ハ)授業料の徴収 | ■■ | 681 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ニ)小学校職員の寄附行為 | ■■ | 684 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ホ)生活改善への動き | ■■ | 685 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ヘ)経済更生運動 | ■■ | 692 |  |
| ■■ | ■■ | (4)戦時体制への歩み | ■■ | 732 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (イ)城西地区野田区有文書の状況 | ■■ | 733 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ロ)教育のあり方 | ■■ | 739 |  |
| ■■ | 第二節 太平洋戦争下の生活 | ■■ | 743 |  |
| ■■ | ■■ | (1)村内の概要 | ■■ | 743 |  |
| ■■ | ■■ | (2)戦時体制下の諸相 | ■■ | 748 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (イ)組織力の強化 隣組と在郷軍人会 | ■■ | 748 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ロ)国家財政への協力 | ■■ | 761 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ハ)資源確保のための動き | ■■ | 772 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ニ)配給について | ■■ | 788 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ホ)防空 | ■■ | 800 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ヘ)小学生時代の思い出 | ■■ | 806 |  |
| ■■ | ■■ | (3)敗戦 | ■■ | 813 |  |
| |
| 第八章 戦後改革の進展 | ■■ | 819 |  |
| ■■ | 第一節 町村の自治 | ■■ | 821 |  |
| ■■ | ■■ | (1)占領下日本の諸改革 | ■■ | 821 |  |
| ■■ | ■■ | (2)選挙制度の改革 | ■■ | 825 |  |
| ■■ | ■■ | (3)町村財政の整備 | ■■ | 831 |  |
| ■■ | ■■ | (4)警察と消防 | ■■ | 834 |  |
| ■■ | 第二節 新教育の発足 | ■■ | 839 |  |
| ■■ | ■■ | (1)新教育の理念と六・三制義務教育 | ■■ | 839 |  |
| ■■ | ■■ | (2)浦川高女から佐久間高校創設へ | ■■ | 847 |  |
| ■■ | ■■ | (3)社会教育の強化 | ■■ | 852 |  |
| ■■ | ■■ | (4)教師の周辺 | ■■ | 856 |  |
| ■■ | 第三節 戦後生活の変貌 | ■■ | 859 |  |
| ■■ | ■■ | (1)戦後インフレと耐乏生活 | ■■ | 859 |  |
| ■■ | ■■ | (2)農地改革と農協 | ■■ | 871 |  |
| ■■ | ■■ | (3)久根鉱山労働組合 | ■■ | 878 |  |
| |
| 第九章 山村生活と健康 | ■■ | 883 |  |
| ■■ | 第一節 人口の変遷と生活 | ■■ | 885 |  |
| ■■ | ■■ | (1)近世における人口の動き | ■■ | 885 |  |
| ■■ | ■■ | (2)近世の人口と生活 宗門人別御改帳より | ■■ | 889 |  |
| ■■ | ■■ | (3)現代における人口の動き 産業資本の動きと人口 | ■■ | 900 |  |
| ■■ | ■■ | (4)現在人口とその地域分布 驚くべき過疎化の進行 | ■■ | 914 |  |
| ■■ | ■■ | (5)最近の人口と年齢構成 深刻な老人化傾向 | ■■ | 919 |  |
| ■■ | ■■ | (6)最近の人口動態と健康 | ■■ | 922 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (イ)死亡の動向 | ■■ | 924 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ロ)出生の動向 | ■■ | 928 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ハ)婚姻と離婚の動向 | ■■ | 929 |  |
| ■■ | 第二節 近世の生活と疾病への取組 | ■■ | 931 |  |
| ■■ | ■■ | (1)近代の人々の疾病観 | ■■ | 931 |  |
| ■■ | ■■ | (2)民間療法 | ■■ | 943 |  |
| ■■ | ■■ | (3)病気に関する民間信仰と伝承 | ■■ | 962 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (1)俗信 | ■■ | 962 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (2)祈禱・「まじない」 | ■■ | 980 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (3)妊娠出産についての伝承 | ■■ | 987 |  |
| ■■ | 第三節 佐久間町衛生行政の歩み | ■■ | 990 |  |
| ■■ | ■■ | (1)コレラ防疫と衛生行政の芽生え | ■■ | 990 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (イ)天然痘 | ■■ | 990 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ロ)コレラ | ■■ | 996 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ハ)衛生会の設置 | ■■ | 1000 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ニ)隔離病舎 | ■■ | 1005 |  |
| ■■ | ■■ | (2)第二次大戦までに行なわれた衛生施策 | ■■ | 1007 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (イ)トラホーム | ■■ | 1007 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ロ)花柳病 | ■■ | 1010 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ハ)結核 | ■■ | 1012 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ニ)スペイン風邪 | ■■ | 1021 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ホ)乳幼児衛生 | ■■ | 1023 |  |
| ■■ | ■■ | (3)貧困者対策の制度 | ■■ | 1030 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (イ)行旅病者取扱 | ■■ | 1030 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ロ)済生会の救療 | ■■ | 1032 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ハ)米騒動と浦川村救済会 | ■■ | 1035 |  |
| ■■ | 第四節 合併後の医療保健 | ■■ | 1044 |  |
| ■■ | ■■ | (1)医療問題 国民健康保険を中心に | ■■ | 1044 |  |
| ■■ | ■■ | (2)僻地の保健医療 | ■■ | 1047 |  |
| ■■ | ■■ | (3)千葉大学医学部農山村医学研究施設の活動 | ■■ | 1051 |  |
| ■■ | ■■ | (4)母子保健活動 母子健康センターと母子保健へのとりくみ | ■■ | 1054 |  |
| ■■ | ■■ | (5)成人病対策 | ■■ | 1057 |  |
| ■■ | ■■ | (6)寄生虫・結核予防対策 | ■■ | 1062 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (イ)寄生虫対策 | ■■ | 1062 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ロ)結核予防対策 | ■■ | 1064 |  |
| ■■ | ■■ | (7)環境衛生 | ■■ | 1066 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (イ)水道の設置 | ■■ | 1066 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ロ)その他の環境衛生 | ■■ | 1070 |  |
| ■■ | 第五節 健康を守る住民運動 | ■■ | 1072 |  |
| ■■ | ■■ | (1)久根煙害事件 | ■■ | 1072 |  |
| ■■ | ■■ | (2)久根鉱山の珪肺問題 | ■■ | 1080 |  |
| ■■ | ■■ | (3)老人医療費無料化の住民運動 | ■■ | 1082 |  |
| ■■ | ■■ | (4)いずみ会(生活と健康を守る婦人の会)の運動 | ■■ | 1087 |  |
| |
| 第十章 佐久間ダムの建設 | ■■ | 1093 |  |
| ■■ | はじめに | ■■ | 1095 |  |
| ■■ | 第一節 佐久間ダム前史 | ■■ | 1097 |  |
| ■■ | ■■ | (1)前史その一 | ■■ | 1097 |  |
| ■■ | ■■ | (2)前史その二 | ■■ | 1103 |  |
| ■■ | 第二節 佐久間ダム建設決定 | ■■ | 1109 |  |
| ■■ | ■■ | (1)電発の発足とダム建設決定 | ■■ | 1109 |  |
| ■■ | ■■ | (2)ダム決定と町内の動向 | ■■ | 1114 |  |
| ■■ | ■■ | (3)総合開発計画と佐久間ダム | ■■ | 1117 |  |
| ■■ | 第三節 佐久間ダム建設はじまる | ■■ | 1124 |  |
| ■■ | ■■ | (1)建設計画と施行体制 | ■■ | 1124 |  |
| ■■ | ■■ | (2)補償問題のはじまり | ■■ | 1126 |  |
| ■■ | ■■ | (3)建設工事開始 | ■■ | 1133 |  |
| ■■ | ■■ | (4)飯田線付替計画 | ■■ | 1138 |  |
| ■■ | 第四節 補償問題の解決 | ■■ | 1146 |  |
| ■■ | ■■ | (1)水没補償 | ■■ | 1146 |  |
| ■■ | ■■ | (2)営業補償と感謝料 | ■■ | 1161 |  |
| ■■ | ■■ | (3)公共補償と水利権問題 | ■■ | 1167 |  |
| ■■ | 第五節 建設工事の進展 | ■■ | 1173 |  |
| ■■ | ■■ | (1)仮締切工事完成 | ■■ | 1173 |  |
| ■■ | ■■ | (2)発電所工事の進行 | ■■ | 1179 |  |
| ■■ | ■■ | (3)飯田線工事はじまる | ■■ | 1183 |  |
| ■■ | ■■ | (4)ダム・ブームの実相 | ■■ | 1190 |  |
| ■■ | ■■ | (5)秋葉ダム建設はじまる | ■■ | 1199 |  |
| ■■ | 第六節 建設工事最終段階へ | ■■ | 1203 |  |
| ■■ | ■■ | (1)積み上るダム | ■■ | 1203 |  |
| ■■ | ■■ | (2)発電機のすえ付け | ■■ | 1209 |  |
| ■■ | ■■ | (3)飯田線の開通 | ■■ | 1210 |  |
| ■■ | ■■ | (4)ダム湛水と発電開始 | ■■ | 1213 |  |
| ■■ | 第七節 佐久間ダムのもたらしたもの | ■■ | 1218 |  |
| ■■ | ■■ | (1)ダム完成式 | ■■ | 1218 |  |
| ■■ | ■■ | (2)ダムと開発効果 | ■■ | 1220 |  |
| ■■ | ■■ | (3)佐久間ダムのもたらしたもの | ■■ | 1232 |  |
| |
| 第十一章 佐久間町の発足と発展 | ■■ | 1237 |  |
| ■■ | 第一節 戦後町村合併の動き | ■■ | 1239 |  |
| ■■ | ■■ | (1)町村合併の背景 | ■■ | 1239 |  |
| ■■ | ■■ | (2)「町村合併促進法」の制定 | ■■ | 1244 |  |
| ■■ | 第二節 佐久間町誕生への歩み | ■■ | 1250 |  |
| ■■ | ■■ | (1)合併序曲 水窪町・城西村の磐田郡編入 | ■■ | 1250 |  |
| ■■ | ■■ | (2)佐久間町の発足への前提 | ■■ | 1252 |  |
| ■■ | ■■ | (3)合併への陣痛 四ヵ町村合併促進協議会の動き | ■■ | 1255 |  |
| ■■ | 第三節 佐久間町の発足 | ■■ | 1295 |  |
| ■■ | ■■ | (1)合併申請書の提出 | ■■ | 1295 |  |
| ■■ | ■■ | (2)佐久間町建設計画 | ■■ | 1320 |  |
| ■■ | ■■ | (3)解村(町)式そして新しい町へ | ■■ | 1349 |  |
| ■■ | 第四節 佐久間町の歩み 成立とその発展 | ■■ | 1356 |  |
| ■■ | ■■ | (1)佐久間町の担い手たち | ■■ | 1356 |  |
| ■■ | ■■ | (2)佐久間町の発展 | ■■ | 1362 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ア)天皇・皇后の行幸啓 | ■■ | 1384 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (イ)教育基盤の整備 | ■■ | 1384 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ウ)社会教育の充実 | ■■ | 1386 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (エ)福祉行政の展開 | ■■ | 1387 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (オ)生活環境の整備 | ■■ | 1388 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (カ)産業基盤整備事業 | ■■ | 1389 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (キ)防災対策の新展開 | ■■ | 1395 |  |
| ■■ | 第五節 第一回全国山村振興シンポジウムのあとさき | ■■ | 1400 |  |
| ■■ | ■■ | (1)全国山村振興シンポジウム | ■■ | 1400 |  |
| ■■ | ■■ | (2)佐久間ダム完成のあとさき | ■■ | 1402 |  |
| ■■ | ■■ | (3)新しい町づくりへの道 | ■■ | 1409 |  |
| |
| 第十二章 村人のくらし | ■■ | 1417 |  |
| ■■ | 第一節 村人のくらし | ■■ | 1419 |  |
| ■■ | ■■ | (1)食制からみたくらし | ■■ | 1419 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (イ)主食と食事の回数 | ■■ | 1419 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ロ)多彩な粉食 | ■■ | 1423 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ハ)山や川の幸 | ■■ | 1425 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ニ)調味料 | ■■ | 1428 |  |
| ■■ | ■■ | (2)服装からみたくらし | ■■ | 1429 |  |
| ■■ | ■■ | (3)山を利用する生業 | ■■ | 1432 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (イ)ヤマヅクリ | ■■ | 1432 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ロ)狩猟 | ■■ | 1440 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ハ)林業 | ■■ | 1448 |  |
| ■■ | ■■ | (4)舟運 | ■■ | 1456 |  |
| ■■ | ■■ | (5)川漁 | ■■ | 1466 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (イ)江戸時代の川漁 | ■■ | 1469 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ロ)アユ漁のこと | ■■ | 1473 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ハ)その他の漁 | ■■ | 1482 |  |
| ■■ | ■■ | (6)養蚕 | ■■ | 1482 |  |
| ■■ | ■■ | (7)炭焼 | ■■ | 1486 |  |
| ■■ | ■■ | (8)茶づくり | ■■ | 1489 |  |
| ■■ | 第二節 信仰をめぐる習俗 | ■■ | 1492 |  |
| ■■ | ■■ | (1)氏神祭礼 | ■■ | 1492 |  |
| ■■ | ■■ | (2)村人と寺の関係 | ■■ | 1499 |  |
| ■■ | ■■ | (3)火伏せの神としての秋葉信仰 | ■■ | 1504 |  |
| ■■ | ■■ | (4)卓越する御霊信仰 | ■■ | 1508 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (イ)屋敷神における若宮信仰 | ■■ | 1509 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ロ)ミサキに関する伝承 | ■■ | 1518 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ハ)七人塚その他 | ■■ | 1518 |  |
| ■■ | 第三節 年中行事 | ■■ | 1526 |  |
| ■■ | ■■ | (1)正月行事 | ■■ | 1526 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (イ)正月の準備 | ■■ | 1527 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ロ)年取り | ■■ | 1529 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ハ)正月 | ■■ | 1529 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ニ)七日正月 | ■■ | 1531 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ホ)仕事始め | ■■ | 1531 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ヘ)モチイ(小正月) | ■■ | 1534 |  |
| ■■ | ■■ | (2)春から夏の行事 | ■■ | 1537 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (イ)節分 | ■■ | 1537 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ロ)山の神祭り | ■■ | 1542 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ハ)神送り(コトハジメ) | ■■ | 1543 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ニ)三月節供 | ■■ | 1545 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ホ)彼岸・卯月八日 | ■■ | 1546 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ヘ)五月節供 | ■■ | 1547 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ト)稲作儀礼 | ■■ | 1548 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (チ)祇園 | ■■ | 1549 |  |
| ■■ | ■■ | (3)盆の行事 | ■■ | 1552 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (イ)盆 | ■■ | 1552 |  |
| ■■ | ■■ | (4)秋から冬の行事 | ■■ | 1560 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (イ)芋節供 | ■■ | 1560 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ロ)釜の神様 | ■■ | 1561 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ハ)イノコ祭り | ■■ | 1563 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ニ)霜月祭 | ■■ | 1563 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | (ホ)神送り・冬至 | ■■ | 1564 |  |
| ■■ | 第四節 人の一生 | ■■ | 1566 |  |
| ■■ | ■■ | はじめに | ■■ | 1566 |  |
| ■■ | ■■ | (1)産育 | ■■ | 1566 |  |
| ■■ | ■■ | (2)婚姻 | ■■ | 1575 |  |
| ■■ | ■■ | (3)葬制 | ■■ | 1580 |  |
| |
| 編しゅう後記 若林淳之 | ■■ | ■■ |  |