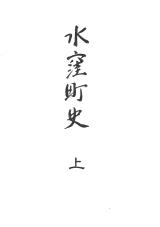 | 『水窪町史 上』 水窪町 昭和五十八年 |
| 目次 | ■■ | ページ | 画像 | |||
| 序文 水窪町長 小澤清孝 | ■■ | ■■ |  | |||
| 凡例 | ■■ | ■■ |  | |||
| Ⅰ 水窪町の自然 | ■■ | ■■ | ■■ | |||
| ■■ | 一 位置及び面積 | ■■ | 三 |  | ||
| ■■ | 二 地形 | ■■ | 十五 |  | ||
| ■■ | 三 地質 | ■■ | 二五 |  | ||
| ■■ | ■■ | (一)地史(日本列島の生いたち) | ■■ | 二五 |  | |
| ■■ | ■■ | (二)水窪町の地質概要 | ■■ | 三一 |  | |
| ■■ | ■■ | (三)水窪町の地層各論 | ■■ | 三三 |  | |
| ■■ | ■■ | (四)内帯側各論 | ■■ | 三九 |  | |
| ■■ | ■■ | (五)外帯側各論 | ■■ | 四一 |  | |
| ■■ | ■■ | (六)水窪町の化石 | ■■ | 四六 |  | |
| ■■ | ■■ | (七)中央構造線 | ■■ | 四八 |  | |
| ■■ | ■■ | (八)遠山赤石裂線 | ■■ | 五〇 |  | |
| ■■ | ■■ | (九)鉱物 | ■■ | 五一 |  | |
| ■■ | ■■ | (十)温泉 | ■■ | 五三 |  | |
| ■■ | 四 気候 | ■■ | 五五 |  | ||
| ■■ | ■■ | (一)気候概況 | ■■ | 五五 |  | |
| ■■ | ■■ | (二)気温(気温・降水量) | ■■ | 五六 |  | |
| ■■ | ■■ | (三)降水量 | ■■ | 六七 |  | |
| ■■ | ■■ | (四)水窪の観測所 | ■■ | 七〇 |  | |
| ■■ | 五 植物 | ■■ | 七三 |  | ||
| ■■ | ■■ | (一)植物に関係する町の概況 | ■■ | 七三 |  | |
| ■■ | ■■ | (二)気候 | ■■ | 七五 |  | |
| ■■ | ■■ | (三)水窪の植物と薬草調査 | ■■ | 七七 |  | |
| ■■ | ■■ | (四)天然記念物 | ■■ | 八二 |  | |
| ■■ | ■■ | (五)町の木と花 | ■■ | 八四 |  | |
| ■■ | ■■ | (六)植生の主なもの | ■■ | 八五 |  | |
| ■■ | ■■ | (七)主な植物の種類 | ■■ | 八七 |  | |
| ■■ | 六 動物 | ■■ | 九三 |  | ||
| ■■ | ■■ | (一)哺乳類 | ■■ | 九三 |  | |
| ■■ | ■■ | (二)狩猟の方法 | ■■ | 九三 |  | |
| ■■ | ■■ | (三)主な哺乳類 | ■■ | 九五 |  | |
| ■■ | ■■ | (四)両生類 | ■■ | 一〇一 |  | |
| ■■ | ■■ | (五)爬虫類 | ■■ | 一〇三 |  | |
| ■■ | ■■ | (六)鳥類 | ■■ | 一〇五 |  | |
| ■■ | ■■ | (七)昆虫類 | ■■ | 一一四 |  | |
| ■■ | ■■ | (八)魚類 | ■■ | 一一九 |  | |
| Ⅱ 通史(日本の歴史と水窪) | ■■ | ■■ | ■■ | |||
| ■■ | はじめに | ■■ | 一二七 |  | ||
| ■■ | 一 無土器時代(旧石器時代) | ■■ | 一二九 |  | ||
| ■■ | 二 縄文時代(新石器時代) | ■■ | 一三二 |  | ||
| ■■ | ■■ | (一)磨製石器と土器の発明 | ■■ | 一三二 |  | |
| ■■ | ■■ | (二)縄文時代の生活(浜松市蜆塚遺跡より) | ■■ | 一三七 |  | |
| ■■ | 三 弥生時代 | ■■ | 一四〇 |  | ||
| ■■ | ■■ | (一)文化の進展 | ■■ | 一四〇 |  | |
| ■■ | ■■ | (二)弥生時代の生活(静岡市登呂遺跡・浜松市伊場遺跡) | ■■ | 一四一 |  | |
| ■■ | 四 磐田市の遺跡 | ■■ | 一四四 |  | ||
| ■■ | 五 水窪町の遺跡 | ■■ | 一四五 |  | ||
| ■■ | 六 中国の本に見られる日本 | ■■ | 一五二 |  | ||
| ■■ | ■■ | (一)前漢書 | ■■ | 一五二 |  | |
| ■■ | ■■ | (二)後漢書 | ■■ | 一五二 |  | |
| ■■ | ■■ | (三)魏志倭人伝 | ■■ | 一五三 |  | |
| ■■ | 七 大和時代 | ■■ | 一五四 |  | ||
| ■■ | ■■ | (一)神話に伝えられる大和朝廷の成立 | ■■ | 一五四 |  | |
| ■■ | ■■ | (二)古墳と大和朝廷 | ■■ | 一五四 |  | |
| ■■ | 八 奈良時代 | ■■ | 一五七 |  | ||
| ■■ | ■■ | (一)律令国家 | ■■ | 一五七 |  | |
| ■■ | ■■ | (二)このころの水窪 | ■■ | 一五九 |  | |
| ■■ | 九 平安時代 | ■■ | 一六一 |  | ||
| ■■ | ■■ | (一)律令制度の衰退と荘園の成立 | ■■ | 一六一 |  | |
| ■■ | ■■ | (二)荘園だった水窪 | ■■ | 一六二 |  | |
| ■■ | ■■ | (三)山香荘(奥山荘)の年貢・公事・兵士役 | ■■ | 一六四 |  | |
| ■■ | ■■ | (四)荘園制の消滅 | ■■ | 一六六 |  | |
| ■■ | 十 鎌倉時代 | ■■ | 一六八 |  | ||
| ■■ | ■■ | (一)水窪町の領家と地頭方の起こり | ■■ | 一六九 |  | |
| ■■ | ■■ | (二)神原で発見された蔵骨器 | ■■ | 一七〇 |  | |
| ■■ | 十一 南北朝時代 | ■■ | 一七一 |  | ||
| ■■ | 十二 室町・戦国・安土桃山時代 | ■■ | 一七二 |  | ||
| ■■ | 十三 水窪と尹良親王(由機良親王)伝記 | ■■ | 一七四 |  | ||
| ■■ | ■■ | (一)片桐家文書 | ■■ | 一七五 |  | |
| ■■ | ■■ | (二)奥山家文書 | ■■ | 一七六 |  | |
| ■■ | ■■ | (三)奥山家文書 | ■■ | 一七七 |  | |
| ■■ | ■■ | (四)善住寺伝 | ■■ | 一七九 |  | |
| ■■ | ■■ | (五)熊谷家伝記 | ■■ | 一七九 |  | |
| ■■ | ■■ | (六)門谷・夏焼の起こり | ■■ | 一八〇 |  | |
| ■■ | ■■ | (七)遠江国風土記伝 | ■■ | 一八一 |  | |
| ■■ | ■■ | (八)各地に伝わる親王の伝記 | ■■ | 一八三 |  | |
| ■■ | 十四 なぞの宝篋印塔 | ■■ | 一八五 |  | ||
| ■■ | ■■ | (一)針間野の王子の墓 | ■■ | 一八六 |  | |
| ■■ | ■■ | (二)長者屋敷 | ■■ | 一八七 |  | |
| ■■ | 十五 久頭合高根城始末記 | ■■ | 一九〇 |  | ||
| ■■ | ■■ | (一)遠江国風土記伝 | ■■ | 一九〇 |  | |
| ■■ | ■■ | (二)奥山由緒 | ■■ | 一九五 |  | |
| ■■ | ■■ | (三)信州遠山氏との関係 | ■■ | 一九七 |  | |
| ■■ | ■■ | (四)開けずの壺と竜の玉 | ■■ | 一九八 |  | |
| ■■ | 十六 武田信玄水窪を通る | ■■ | 二〇一 |  | ||
| ■■ | ■■ | (一)青崩峠 | ■■ | 二〇一 |  | |
| ■■ | ■■ | (二)ヒョウ越峠 | ■■ | 二〇三 |  | |
| ■■ | ■■ | (三)武田の落武者 | ■■ | 二〇五 |  | |
| ■■ | ■■ | (四)上村伊藤家の系譜 | ■■ | 二〇六 |  | |
| ■■ | ■■ | (五)家康公御腰掛岩 | ■■ | 二〇七 |  | |
| ■■ | 十七 奥山という地名の起こり | ■■ | 二〇八 |  | ||
| ■■ | ■■ | (一)奥山村名の由来 | ■■ | 二〇八 |  | |
| ■■ | ■■ | (二)山住大権現棟札写 | ■■ | 二〇八 |  | |
| ■■ | ■■ | (三)遠江国風土記伝 | ■■ | 二〇九 |  | |
| ■■ | ■■ | (四)加賀前田家天野文書 | ■■ | 二一〇 |  | |
| ■■ | ■■ | (五)静岡県の歴史 | ■■ | 二一〇 |  | |
| ■■ | 十八 織田・豊臣時代 | ■■ | 二一一 |  | ||
| ■■ | 十九 豊臣氏の滅亡 | ■■ | 二一二 |  | ||
| ■■ | 二十 木地屋 | ■■ | 二一五 |  | ||
| ■■ | 二十一 江戸時代 | ■■ | 二一九 |  | ||
| ■■ | ■■ | (一)江戸時代 | ■■ | 二一九 |  | |
| ■■ | ■■ | (二)大名政策 | ■■ | 二二一 |  | |
| ■■ | ■■ | (三)諸法度・触書 | ■■ | 二二三 |  | |
| ■■ | ■■ | (四)身分制度 | ■■ | 二二四 |  | |
| ■■ | ■■ | (五)年貢 | ■■ | 二二六 |  | |
| ■■ | ■■ | (六)キリスト教の禁止 | ■■ | 二二六 |  | |
| ■■ | ■■ | (七)鎖国 | ■■ | 二二七 |  | |
| ■■ | ■■ | (八)武断主義から文治主義へ | ■■ | 二二七 |  | |
| ■■ | ■■ | (九)幕府の三大改革 | ■■ | 二二八 |  | |
| ■■ | 二十二 江戸幕府の滅亡 | ■■ | 二三一 |  | ||
| ■■ | ■■ | (一)鎖国から開国へ | ■■ | 二三一 |  | |
| ■■ | ■■ | (二)安政の大獄と桜田門外の変 | ■■ | 二三二 |  | |
| ■■ | ■■ | (三)大政奉還 | ■■ | 二三三 |  | |
| ■■ | 二十三 江戸時代の水窪 | ■■ | 二三四 |  | ||
| ■■ | ■■ | (一)中泉代官 | ■■ | 二三四 |  | |
| ■■ | ■■ | (二)村の組織と政治 | ■■ | 二四五 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 1 村の組織 | ■■ | 二四六 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 2 名主の任命 | ■■ | 二四九 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 3 名主の仕事と給料 | ■■ | 二四九 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 4 組頭 | ■■ | 二五一 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 5 百姓代 | ■■ | 二五一 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 6 組庄屋 | ■■ | 二五一 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 7 五人組 | ■■ | 二五二 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 8 村差出帳 | ■■ | 二五六 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 9 検地 | ■■ | 二七五 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 10 名寄帳 | ■■ | 二九七 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 11 年貢 | ■■ | 二九九 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 12 国役金 | ■■ | 三〇四 |  |
| ■■ | ■■ | (三)苦労した人々 | ■■ | 三〇七 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 1 慶安御触書 | ■■ | 三〇七 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 2 農民の暮らし | ■■ | 三〇九 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 3 よく生きてきた人々 | ■■ | 三二四 |  |
| ■■ | ■■ | (四)宗門人別帳その他 | ■■ | 三二七 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 1 宗門人別帳 | ■■ | 三二七 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 2 過去帳 | ■■ | 三三六 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 3 村入用帳 | ■■ | 三三七 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 4 巡見使 | ■■ | 三四一 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 5 天保の改革と御触書 | ■■ | 三四六 |  |
| ■■ | ■■ | (五)榑木役 | ■■ | 三五四 |  | |
| ■■ | 二十四 明治時代 | ■■ | 三六八 |  | ||
| ■■ | ■■ | (一)大政奉還と王政復古 | ■■ | 三六九 |  | |
| ■■ | ■■ | (二)五箇条のご誓文と新政府の発足 | ■■ | 三七〇 |  | |
| ■■ | ■■ | (三)版籍奉還と廃藩置県 | ■■ | 三七二 |  | |
| ■■ | ■■ | (四)静岡県の成立 | ■■ | 三七二 |  | |
| ■■ | ■■ | (五)四民平等 | ■■ | 三七三 |  | |
| ■■ | ■■ | (六)家禄制度の廃止 | ■■ | 三七四 |  | |
| ■■ | ■■ | (七)地租改正 | ■■ | 三七五 |  | |
| ■■ | ■■ | (八)地券 | ■■ | 三七六 |  | |
| ■■ | ■■ | (九)貨幣制度 | ■■ | 三七六 |  | |
| ■■ | ■■ | (十)壬申戸籍 | ■■ | 三七七 |  | |
| ■■ | ■■ | (十一)散髪廃刀令 | ■■ | 三七七 |  | |
| ■■ | ■■ | (十二)学制頒布 | ■■ | 三七八 |  | |
| ■■ | ■■ | (十三)警察 | ■■ | 三七八 |  | |
| ■■ | ■■ | (十四)徴兵制度 | ■■ | 三七九 |  | |
| ■■ | ■■ | (十五)欧米視察 | ■■ | 三七九 |  | |
| ■■ | ■■ | (十六)文明開化 | ■■ | 三七九 |  | |
| ■■ | ■■ | (十七)近代思想の芽ばえと自由民権運動 | ■■ | 三八一 |  | |
| ■■ | ■■ | (十八)条約改正 | ■■ | 三八三 |  | |
| ■■ | ■■ | (十九)日本の大陸進出 | ■■ | 三八三 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 1 日清戦争 | ■■ | 三八四 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 2 北清事変 | ■■ | 三八四 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 3 日露戦争 | ■■ | 三八五 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 4 韓国併合 | ■■ | 三八六 |  |
| ■■ | ■■ | (二十)明治の文化 | ■■ | 三八六 |  | |
| ■■ | ■■ | (二十一)地方行政機構の変遷 | ■■ | 三八六 |  | |
| ■■ | 二十五 大正時代 | ■■ | 三八八 |  | ||
| ■■ | ■■ | (一)第一次世界大戦と日独戦争 | ■■ | 三八八 |  | |
| ■■ | ■■ | (二)好景気と米騒動 | ■■ | 三八九 |  | |
| ■■ | ■■ | (三)ワシントン会議 | ■■ | 三九〇 |  | |
| ■■ | ■■ | (四)経済恐慌と関東大震災 | ■■ | 三九一 |  | |
| ■■ | ■■ | (五)皇太子外遊 | ■■ | 三九一 |  | |
| ■■ | ■■ | (六)労働争議 | ■■ | 三九二 |  | |
| ■■ | ■■ | (七)虎の門事件 | ■■ | 三九二 |  | |
| ■■ | ■■ | (八)治安維持法・普通選挙法公布 | ■■ | 三九三 |  | |
| ■■ | ■■ | (九)大正時代の流行 | ■■ | 三九三 |  | |
| ■■ | 二十六 昭和時代 | ■■ | 三九八 |  | ||
| ■■ | ■■ | (一)世界経済大恐慌と深刻だった水窪 | ■■ | 三九八 |  | |
| ■■ | ■■ | (二)満州事変 | ■■ | 四〇一 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 1 満州国の独立 | ■■ | 四〇二 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 2 国際連盟脱退 | ■■ | 四〇三 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 3 強まる軍国主義 | ■■ | 四〇三 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 4 相次ぐ暴力事件 | ■■ | 四〇四 |  |
| ■■ | ■■ | (三)日中戦争 | ■■ | 四〇五 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 1 盧溝橋事件 | ■■ | 四〇六 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 2 予想外の苦戦 | ■■ | 四〇六 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 3 国民精神総動員運動 | ■■ | 四〇七 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 4 国家総動員法制定 | ■■ | 四〇七 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 5 張鼓峰及びノモンハン事件 | ■■ | 四〇八 |  |
| ■■ | ■■ | (四)第二次世界大戦 | ■■ | 四〇八 |  | |
| ■■ | ■■ | (五)新体制運動と大政翼賛会 | ■■ | 四〇九 |  | |
| ■■ | ■■ | (六)太平洋戦争突入 | ■■ | 四〇九 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 1 南方進駐 | ■■ | 四一〇 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 2 落日の苦闘 | ■■ | 四一二 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 3 本土決戦かポツダム宣言受諾か | ■■ | 四一八 |  |
| ■■ | ■■ | (七)終戦 | ■■ | 四一九 |  | |
| ■■ | ■■ | (八)廃虚の底から | ■■ | 四二〇 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 1 生活の窮乏 | ■■ | 四二一 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 2 天皇の人間宣言 | ■■ | 四二三 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 3 新憲法公布と地方自治法 | ■■ | 四二三 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 4 陸海軍解体と極東軍事裁判 | ■■ | 四二四 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 5 財閥解体 | ■■ | 四二五 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 6 農地改革と開拓事業 | ■■ | 四二五 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 7 農業会から農協へ | ■■ | 四二六 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 8 民生事業の充実 | ■■ | 四二六 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 9 新円切替えと金融 | ■■ | 四二七 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 10 労働運動 | ■■ | 四二八 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 11 警察・消防制度 | ■■ | 四二九 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 12 教育改革 | ■■ | 四三一 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 13 平和条約締結 | ■■ | 四三二 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 14 日米安全保障条約締結 | ■■ | 四三二 |  |
| ■■ | ■■ | (十)よみがえった日本 | ■■ | 四三三 |  | |
| ■■ | ■■ | (十一)世界の情勢と日本 | ■■ | 四三七 |  | |
| ■■ | 二十七 兵事 | ■■ | 四三八 |  | ||
| ■■ | ■■ | はじめに | ■■ | 四三八 |  | |
| ■■ | ■■ | (一)明治初年の軍制 | ■■ | 四三九 |  | |
| ■■ | ■■ | (二)水窪に残る軍事関係文書 | ■■ | 四四〇 |  | |
| ■■ | ■■ | (三)壮丁及び徴集人員 | ■■ | 四四六 |  | |
| ■■ | ■■ | (四)戦争動員と戦没者 | ■■ | 四四七 |  | |
| ■■ | ■■ | (五)出征軍人家族援護 | ■■ | 四六七 |  | |
| ■■ | ■■ | (六)昭和時代 | ■■ | 四七六 |  | |
| ■■ | ■■ | (七)銃後の水窪 | ■■ | 四七九 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 1 出征軍人を送る | ■■ | 四八二 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 2 防空演習 | ■■ | 四八五 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 3 灯火管制 | ■■ | 四八六 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 4 竹槍訓練 | ■■ | 四八七 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 5 食糧戦争 | ■■ | 四八八 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 6 生活必需品の欠乏 | ■■ | 四九〇 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 7 無言の帰還 | ■■ | 四九二 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 8 遺書 | ■■ | 四九四 |  |
| Ⅲ 行政 | ■■ | ■■ | ■■ | |||
| ■■ | 一 行政機構とその動き | ■■ | 五〇五 |  | ||
| ■■ | ■■ | (一)江戸時代の地方支配組織 | ■■ | 五〇五 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 1 歴代代官と名主 | ■■ | 五〇五 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 2 江戸時代の村 | ■■ | 五一四 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 3 村役人 | ■■ | 五二〇 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 4 水窪での村役人 | ■■ | 五二二 |  |
| ■■ | ■■ | (二)明治初期の行政機構 | ■■ | 五二八 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 1 大小区制と戸長制度 | ■■ | 五二八 |  |
| ■■ | ■■ | (三)水窪町の誕生 | ■■ | 五三七 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 1 村制施行 | ■■ | 五三七 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 2 村の分離 | ■■ | 五四〇 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 3 町制施行 | ■■ | 五四一 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 4 磐田郡編入 | ■■ | 五四四 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 5 町村合併問題 | ■■ | 五四五 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 6 役場 | ■■ | 五五〇 |  |
| ■■ | 二 選挙と議会 | ■■ | 五六五 |  | ||
| ■■ | ■■ | (一)選挙 | ■■ | 五六五 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 1 衆議院議員選挙 | ■■ | 五六五 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 2 貴族院多額納税者議員互選 | ■■ | 五六九 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 3 参議院議員選挙 | ■■ | 五七〇 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 4 県知事選挙 | ■■ | 五七一 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 5 県議会議員の選挙 | ■■ | 五七二 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 6 市町村長選挙 | ■■ | 五七四 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 7 町村議会議員選挙 | ■■ | 五七五 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 8 選挙管理委員会 | ■■ | 五七八 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 9 地方自治法施行後の選挙 | ■■ | 五八〇 |  |
| ■■ | ■■ | (二)議会 | ■■ | 五八一 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 1 村制施行前の議会 | ■■ | 五八一 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 2 町村制による議会 | ■■ | 五八三 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 3 地方自治法による議会 | ■■ | 五八五 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 4 村会・町会議員 | ■■ | 五八五 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 5 議長及び副議長(地方自治法による議会) | ■■ | 五九五 |  |
| ■■ | 三 区長 | ■■ | 五九六 |  | ||
| ■■ | ■■ | (一)区長制度 | ■■ | 五九六 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 1 明治初期 | ■■ | 五九六 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 2 市町村の制度化と区の制度化 | ■■ | 五九七 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 3 水窪町内の行政区域の制定 | ■■ | 五九七 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 4 初代区長の選出 | ■■ | 五九八 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 5 区域等の一部改正 | ■■ | 五九九 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 6 部落会制度の発足と区長制度の廃止 | ■■ | 六〇〇 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 7 部落会制度の廃止 | ■■ | 六〇一 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 8 自主的な区長制度生まれる | ■■ | 六〇一 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 9 区の分離 | ■■ | 六〇一 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 10 歴代区長 | ■■ | 六〇二 |  |
| ■■ | 四 官公署 | ■■ | 六一四 |  | ||
| ■■ | ■■ | (一)静岡地方法務局水窪出張所 | ■■ | 六一四 |  | |
| ■■ | ■■ | (二)水窪営林署 | ■■ | 六一七 |  | |
| ■■ | ■■ | (三)水窪警察署 | ■■ | 六一八 |  | |
| ■■ | ■■ | (四)静岡県天龍林業事務所水窪支所 | ■■ | 六二二 |  | |
| ■■ | ■■ | (五)静岡県天龍土木事務所水窪支所 | ■■ | 六二四 |  | |
| ■■ | ■■ | (六)水窪郵便局 | ■■ | 六二五 |  | |
| ■■ | ■■ | (七)水窪電報電話局 | ■■ | 六二七 |  | |
| ■■ | ■■ | (八)遠江二俣自動車営業所水窪派出所 | ■■ | 六二八 |  | |
| ■■ | ■■ | (九)飯田線水窪駅 | ■■ | 六三〇 |  | |
| ■■ | ■■ | (十)飯田線向市場駅 | ■■ | 六三二 |  | |
| ■■ | ■■ | (十一)飯田線小和田駅 | ■■ | 六三二 |  | |
| ■■ | ■■ | (十二)飯田線大嵐駅 | ■■ | 六三五 |  | |
| ■■ | 五 財政 | ■■ | 六三七 |  | ||
| ■■ | ■■ | (一)江戸時代の財政 | ■■ | 六三七 |  | |
| ■■ | ■■ | (二)明治初期の財政 | ■■ | 六三九 |  | |
| ■■ | ■■ | (三)奥山村の財政 | ■■ | 六四七 |  | |
| ■■ | ■■ | (四)町の財政 | ■■ | 六五九 |  | |
| ■■ | 六 人口 | ■■ | 七〇九 |  | ||
| ■■ | ■■ | (一)先住民 | ■■ | 七〇九 |  | |
| ■■ | ■■ | (二)中世期人口の考察 | ■■ | 七一〇 |  | |
| ■■ | ■■ | (三)江戸時代の人口 | ■■ | 七一二 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 1 御水帳にみる家数 | ■■ | 七一二 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 2 五人組帳にみる家数 | ■■ | 七一四 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 3 村差出帳にみる家数と人口 | ■■ | 七一五 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 4 宗門人別帳による人口 | ■■ | 七一六 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 5 江戸時代の人口異動 | ■■ | 七一九 |  |
| ■■ | ■■ | (四)明治から大正時代の人口 | ■■ | 七二三 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 1 明治五年戸籍 | ■■ | 七二三 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 2 明治十九年戸籍 | ■■ | 七二三 |  |
| ■■ | ■■ | (五)国勢調査による人口 | ■■ | 七二四 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 1 第一回国勢調査 | ■■ | 七二四 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 2 第二回国勢調査 | ■■ | 七二八 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 3 第三回国勢調査 | ■■ | 七三〇 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 4 第四回国勢調査 | ■■ | 七三二 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 5 第五回国勢調査 | ■■ | 七三二 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 6 昭和二十年人口調査 | ■■ | 七三三 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 7 昭和二十二年臨時国勢調査 | ■■ | 七三三 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 8 第七回国勢調査 | ■■ | 七三六 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 9 第八回国勢調査 | ■■ | 七三九 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 10 第九回国勢調査 | ■■ | 七四二 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 11 第十回国勢調査 | ■■ | 七四二 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 12 第十一回国勢調査 | ■■ | 七四七 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 13 第十二回国勢調査 | ■■ | 七五一 |  |
| ■■ | ■■ | (六)付表 | ■■ | 七五六 |  | |
| ■■ | 七 厚生と福祉 | ■■ | 七七一 |  | ||
| ■■ | ■■ | (一)衛生 | ■■ | 七七一 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 1 江戸時代の医療 | ■■ | 七七一 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 2 伝染病と隔離病舎 | ■■ | 七七三 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 3 結核 | ■■ | 七八〇 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 4 水窪町立結核診療所 | ■■ | 七八六 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 5 医師 | ■■ | 七八七 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 6 薬剤師 | ■■ | 七九〇 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 7 助産婦 | ■■ | 七九〇 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 8 鍼・灸・マッサージ師 | ■■ | 七九一 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 9 保健婦 | ■■ | 七九二 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 10 患者輸送車 | ■■ | 七九二 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 11 町営屠畜場 | ■■ | 七九三 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 12 上水道 | ■■ | 七九四 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 13 し尿処理 | ■■ | 七九八 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 14 塵芥処理 | ■■ | 八〇〇 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 15 公害問題 | ■■ | 八〇三 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 16 保健衛生 | ■■ | 八〇四 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 17 共同墓地と火葬場 | ■■ | 八〇八 |  |
| ■■ | ■■ | (二)福祉 | ■■ | 八一一 |  | |
| ■■ | ■■ | ■■ | 1 社会福祉と社会福祉事業 | ■■ | 八一一 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 2 民生委員制度 | ■■ | 八一三 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 3 生活保護 | ■■ | 八一六 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 4 身体障害者福祉 | ■■ | 八一七 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 5 老人福祉 | ■■ | 八一九 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 6 児童福祉 | ■■ | 八二四 |  |
| ■■ | ■■ | ■■ | 7 国民健康保険 | ■■ | 八三〇 |  |
| ■■ | 八 消防 | ■■ | 八三八 |  | ||
| ■■ | ■■ | (一)旧幕時代 | ■■ | 八三八 |  | |
| ■■ | ■■ | (二)明治時代 | ■■ | 八四一 |  | |
| ■■ | ■■ | (三)水窪町の消防 | ■■ | 八四二 |  | |
| ■■ | ■■ | (四)消防組頭、警防団長、消防団長 | ■■ | 八五二 |  | |