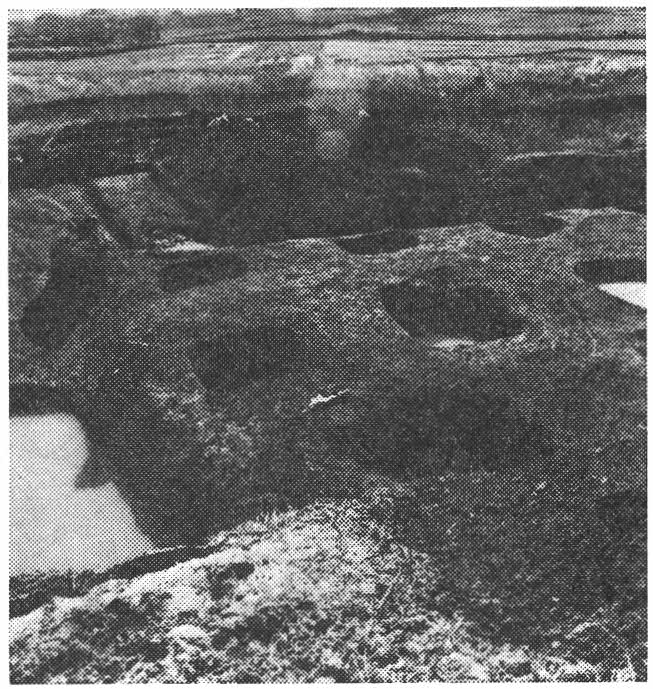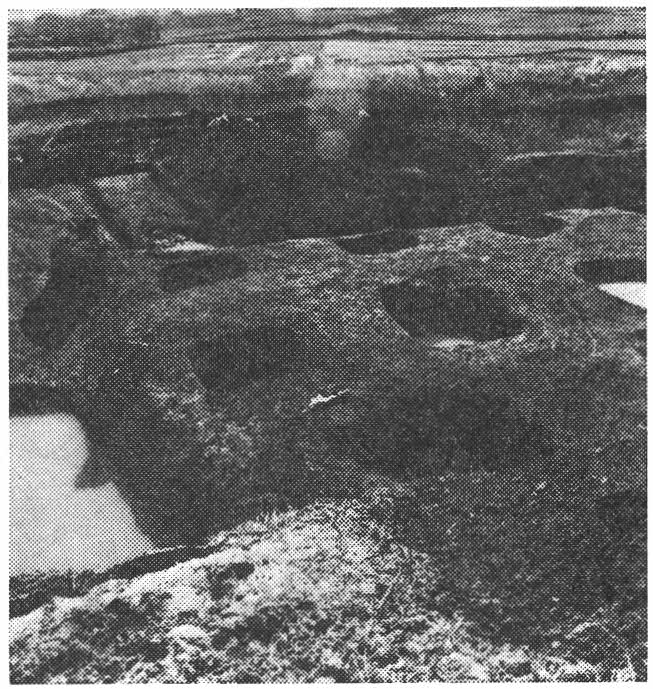大化の改新(六四五)の後、政府は、中央集権的な律令国家をつくりあげるため、多くの行政改革を行った。国造制による豪族支配制度を廃止して地方の支配制度を確立したのも、その一つのあらわれである。改新前の茨城県域(常陸国域)は高(たか)・久自(くじ)・仲(なか)・新治(にいばり)・筑波(つくば)・茨城(いばらぎ)の六か国が国造によって分割統治されていたが、改新の制度によって六か国は統合され、新たに常陸国が誕生した。国内に、多珂(たが)・久慈(くじ)・那珂(なか)・新治(にいばり)・真壁(まかべ)・筑波(つくば)・河内(かわち)・信太(しだ)・茨城(いばらぎ)・行方(なめかた)・香島(かしま)の一一郡が設置され、国府(国衙(こくが))は現在の石岡市に置かれ、それぞれの郡には郡家(ぐうけ)(郡衙)が設けられた。地方支配体制の確立をめざす国・郡(評)・里の成立期は必ずしも明確といいがたいが、庚午年籍(こうごねんじゃく)の作成(六七〇年のころ)前後においては、この制度はほぼ全国的に促進され、地方行政区画の成立と併せて、村落支配の推進が徹底されたとみられている。このうち、評は旧来の国造制の国を継承するもので、これを分割するために里を設けたようであるが、大宝元年(七〇一)に完成をみた大宝令によれば、五〇戸を一里として編成しており、この制度は霊亀元年(七一五)には、里を郷に改名するとともに、郷の下部組織として里を設定する郷里制に改編されている。しかし、郷里制の村落制度も、天平一二年(七四〇)のころに里は廃止され再び郷制にもどされている。この郷里制の施行は部分的ではなく全国的規模で行われたようである。関東諸国においても、下総国葛飾郡大嶋郷甲和里・仲村里・嶋俣里、上総国天羽郡讃岐郷磐井里、武蔵国男衾郡獦倉郷(笠)里、上野国群馬郡下賛郷高田里、相模国(余綾)郡□□郷大磯里など、戸籍・金石文・調庸関係墨書銘からその一端をうかがうことができる。
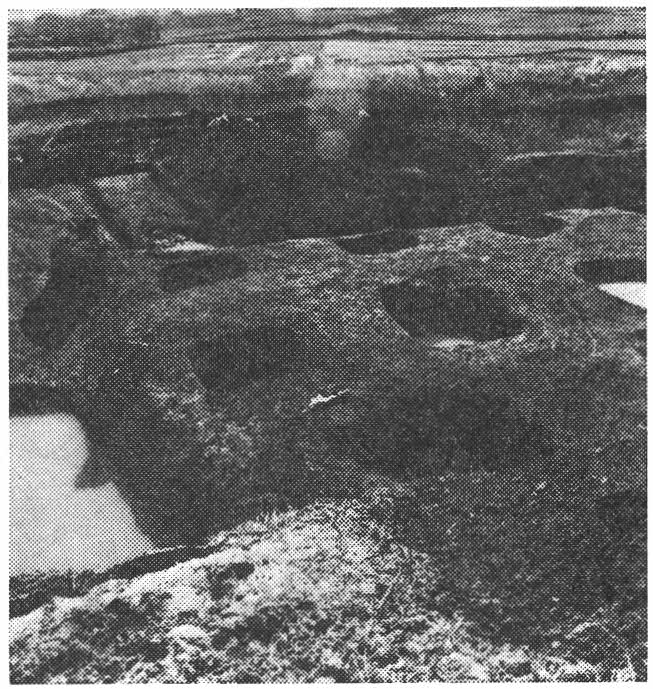
官衙遺跡の柱穴跡
(筑波町平沢遺跡)