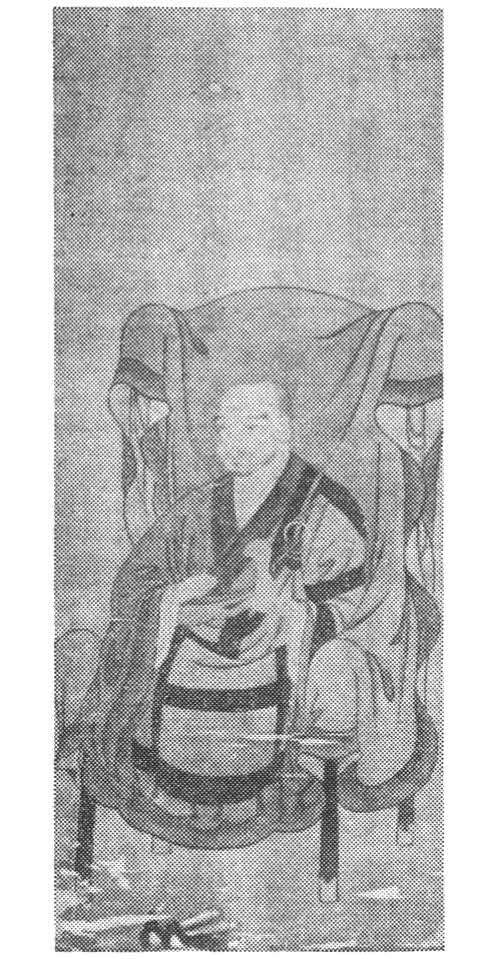
聖冏上人画像(法性寺蔵)
聖冏酉蓮社了誉書状
常陸国久慈西瓜連草地常福寺に領御寄進状の事は、延文三(一三五八)戊戌十二月七日、浄喜(大)守の時
に(佐竹)右馬権頭源義篤御判である。然を去嘉慶(一三八八)二戊辰二月廿一日 宿中(瓜連)残る所無く
焼失の時刻、流火によって彼堂(常福寺)炎上の時 御寄進状并坊敷 田畠坪付等 悉くもって紛失畢っ
た。其已後、今も知行は相違はないが、御沙汰所判申請け 御証に備えたい。此旨を御披露に預る者で
ある。
敬白
(応永十二年)三月六日 西蓮社了誉(聖冏)在判
進上 稲木(常仙)殿御奉行所
右は、常福寺が瓜連宿火災の類焼にあって、聖冏が書類まで焼失してしまったから証文を頂きたいとの申状で、それに対し稲木常仙(義信)は次の返報をしている。
延文三戊戌十二月七日 御寄進状并坊敷、寺領之坪付粉(紛)失云々 其旨承候〓(おわんぬ)者 守二
先例一可レ被レ致二精誠御祈祷一也
応永十二年(一四〇五)三月六日 沙弥常仙
逐命啓上
常福寺は佐竹義篤の開基で寄進によるものであったが三〇年目に焼け、一族稲木義信が寺の証文、敷地、寺領田畑を再確認している。
この後、また三〇年目に上杉禅秀の乱に戦火にあっている。応永二四年正月一〇日、禅秀は自殺し、稲木は禅秀に味方したために鎌倉府から攻められて四月二四日落城している。
聖聡書状写(5)
一日大野下河辺荘へ御越候けるよし、今度承候 えんてん[炎天]時分勿体なく存候 其上又御状にあ
つかり候 尤当年はいまた御めにかゝらず候 又常福寺のなりゆき候ありさま くわしく物かたり申
たく候へとも 武州へいそく子細候間 大野よりまかり上候今度不レ入二見参一候之條 心もとなく存候
又御状のおもて常福寺に悦喜申され候 御茶事は無子細御よろこび候 上方はいまた阿弥陀山に御座
候、瓜連の事は中々しかのふしと[鹿の伏戸]となり候 人民更に不二還住一候 まして僧坊聖道 禅家
皆他国流浪の事に候 言語道断に候き 就中老師(聖冏)の有様目もくれ心もさえはてゝこそ 見すて
申候てまかりのほり候へし 御愁敷 我等悲泣何(いか)にせん/\秋の頃は申度候 相構/\御法門
へ終夜申て候 しかれとも 餘に/\散々に申され候二ケ條注進候 其餘は中々不レ及レ申候 いと
とたに浄土宗すたれ行候事 歎入存候
重註文恐々謹文
西誉(大蓮社聖聡)
横曽袮(根)学頭進候
聖冏が常福寺住職中、応永二三年、上杉禅秀の乱が起こって戦火にあい瓜連から流浪の身となって武蔵へ急ぐ苦労の有様を弟子聖聡が知り、書状には日付けはないが乱中のことで、応永二三年夏のもので聖聡が横曽根法性寺の学頭宛に師聖冏の難儀、寺僧らの退職を述べ悲しみ、浄土宗はすたれたと報じている。このように常福寺は衰えたが、水海道では盛んになって、その中心が鎌倉光明寺と共に有名となっている。
次の状は禅秀の乱の時、聖冏が瓜連から北方へ逃れて久慈郡不軽山(あるいは阿弥陀山)にいる時、先師(聖聡)が武州江戸から常陸佐竹に来て聖冏の安否を気づかっての帰途、大野(下大野村(総和)の正宗寺)から横曽根へ遣わされたものである。
了暁[聖蓮社/慶誉]副状幷譲状写
私[慶誉/了暁]文安年中(一四四四~一四四八)宝徳二年(一四五〇)
この親筆の書札を見て感じ 歓は身に余り感歎は肝に銘する程て 文字はその通り写すので 座席も机
も動かさないで切紙に認め後輩に送ることにする 問答文は大切である 就中初め問答は 帰着(おち
つき)の深妙幽玄細釈の深妙〓共に仏願難思他力引拠のわけをのべ 衆生の報土得出の旨をあらわして
その欣求を勧むるか 之は俗世界のつまるところ教門であるどうして所詮(つまるところ)浄土の僧体に
配当する事をいうか 玄[幽玄]義を以って仏法僧に分かれ属(つ)いて之を縁に先師(聖聡)に最も感心す
る。
次の問答は諸行各々一つの行を守って、また是れ本願を非するのである。念仏は万徳の帰する所である。
行もまた是れ本願である。そのように念仏をすれば、即ち、この上の無い菩提に趣の奥義であるから、
是又智恵の理にちかわない、しかし智恵は即ち難が劣る本願でない行である、念仏はこれ本願に勝る行
である。易に難、劣に勝。願と非願 是各々別である。同してあるといって之を修るとか 苦しくない
というとか彼の制多山の西の山に上って二つの問答は共に大要である 少し述べたらないが 以上である
今 曜誉が酉(聖聡)と冏(聖冏)に仏法を求むるの志、丁寧であるので慥に授けられたこれらの大綱を
守って弘通さるべきである。
文明十二年(一四八〇)庚子二月十八日 了暁(花押影)