先手の水海道勢が破れたので下妻勢も(新)荒井木の下より引き返している。後北條方も帰陣した。田村弾正の戦死の場所、小貝川辺には弾正塚が築いてある。
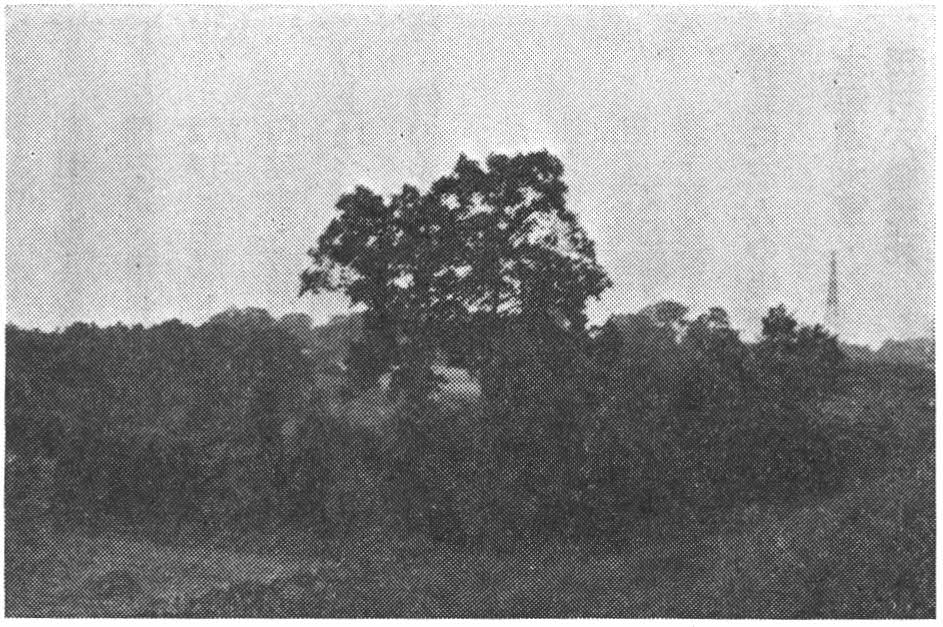
弾正塚
下妻方は敗戦の原因は軍船が不備であったとして池田宗三郎を船手の大将にし、染谷民部手下の猿島水軍、これは飯沼の猿島縁の漁農民で五〇〇余と号した。これと地元の水軍を合わせ報国寺から吹上にかけて夜も篝を焚いて調練した。
義長は横瀬主膳・小川(外記次男)・海老原と同舟して水海道実城の近在の八幡宮鳥居に乗り着け、さらに諏訪明神前を経て吹上に忍びこもうとしたところ、猿島水軍の大将染谷民部が外孫の主膳を見つけた。大音をあげた染谷に小川雅楽助信綱が斬りかかったのを高野(水海道)の風見主税が引きはずした。しかし家伝によれば斬られている。弓田の正光院墓碑の日附は天正五年六月一六日とある。五木田因幡は横瀬主膳と渡り合った。海老原が大竹弥三郎を倒すと落合九郎・石浜五郎・寺沢宮内三人で海老原に打ちかかったが、かえって寺沢を除いて倒された。
富村・鶴見・野沢・星合・中村・高島らが三勇士を包囲したが、三勇士はひるまなかった。重経は敵ながら天晴れとして囲みを解いたので八幡宮に立ち退いていた義長の許に着いた。義長は八幡の加護と感謝して福岡に帰城した。
時に天正五年六月のことである。
医師中村徳庵は多賀谷重経に福岡を落とす方法があると申しあげ中妻、箕輪を迂廻して義長の陣に行った。横瀬の案内で面談に及ぶと義長から、水軍の将池田が内通していると、その書状を示された。徳庵はそれを懐中して急ぎ水海道に帰り重経に渡した。池田は吹上から呼びよせられ、書状を見せられるに、自分の筆跡同然である。敵の反間であると弁じたが及ばず打ち首にされた。息庄次郎は驚き憤ったが一族と共に急ぎ筒戸に遁れている。