建武五年九月に入ると、北畠親房が東条浦に漂着し、小田治久、関宗祐、下妻政泰等の南朝側の武将に迎えられて神宮寺城(現桜川村)に入った。親房はこの城のほかに阿波崎城(東村)を南朝側の拠点にしようとしたが、佐竹義篤、鹿島幹寛、烟田時幹、宮崎幹顕ら尊氏方に攻略され、小田治久の居城の小田城(筑波城)に入った。親房が常陸に滞在した約五年の間に、小田城で南朝側の立場から『神皇正統記』を著わしたといわれる。しかし、常総での南朝側の拠点は、次第に尊氏方によって潰されていった。暦応二年(延元四、一三三九)から三年にかけての駒城(現下妻市)の攻防、同四年九月には、信太荘佐倉城(現江戸崎町)、東条城(現新利根村)、亀谷城(現江戸崎町)、高井城(現竜ケ崎市)が落ち、十一月には小田城も落ち、親房はやむなく小田城から関城(現関城町)に移らなければならなかった。親房は白河結城宗広の子親朝に救援を要請する書状約七〇通を送ったが、彼は動くことができず、康永二年(興国四、一三四三)十一月、常総での南朝側の拠点の関・大宝両城は落ち、関宗祐、下妻政泰らは討死した。ついで伊佐城も落ち、ここに常総での南朝勢力は大きな打撃を受け、その勢力は陸奥の一部拠点霊山などに押し込められた。こうして常総には、足利方に味方した佐竹氏の勢力が伸長してくるのである。

Ⅲ-2図 小田城跡
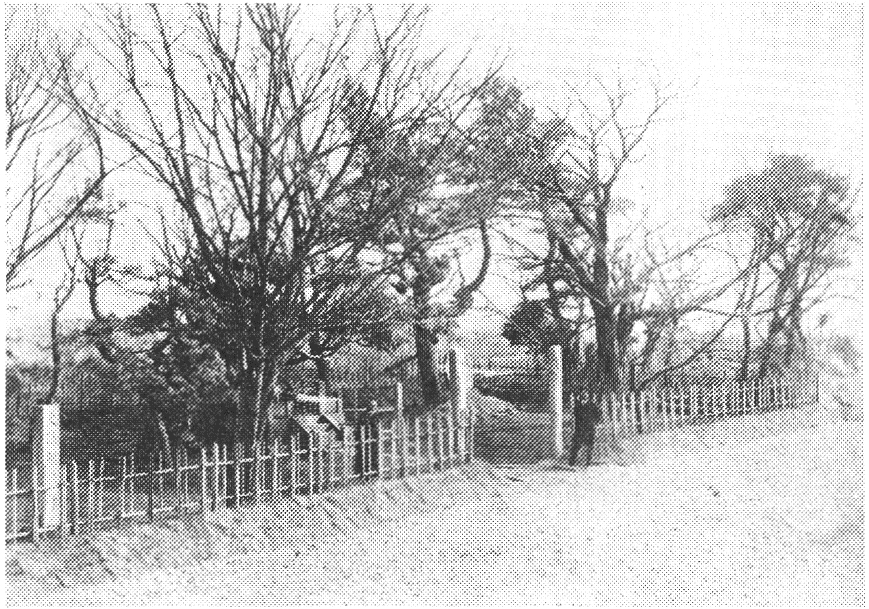
Ⅲ-3図 関城跡(関城町史編さん室提供)

Ⅲ-4図 大宝城跡(下妻市教育委員会提供)
最後に、常陸南部・西部で南朝勢力の拠点となった荘園は、信太・南野・下妻・関などがあげられる。そして、関荘を除いた荘園の本家は八条院であった時期があり、鎌倉期には何らかの形で北条氏の影響下にあったところが多く、後醍醐天皇の建武の新政下、荘園の地頭職をもっていた在地武士は、大覚寺統つまり南朝方に立ったものと推察できる。北下総の下河辺荘も八条院領であったことから、同様のことがいえるのではないかと思われる。また、この他の理由として前述したように、北条氏得宗領として無理に所領を没収された武士の中には、周辺の敵対する武士の動向を熟視しながら、南朝・北朝のいずれかに分れていった場合もあったろう。こうした点からみると、南朝側に味方する武士は、限定されて多くはなかったといえる。
こうした中で、当時の豊田氏の動向を追うことはきわめて難しく、かつての平氏滅亡の時と同様、静観していたのではないかと考えられる。