林子は、明治九年(一八七六)四月横浜小学校に入学した。母が病気のため、鵠沼の母の実家に預けられたが、母は十月に二八歳で死去した。翌年父は再婚した。林子はこの母に大いに愛されたが、この義母もまた十二年に死去し、父は再々婚した。ところが、翌年十二月には火災に遇い、家資産もろとも失い石下の父の実家に帰ることになった。
明治十七年(一八八四)の春再び横浜に行き、裁縫、読書等に身をいれていたが、翌年八月には一家をあげて石下に移った。しかし、勉学は怠ることなく、二十二年(一八八九)には、東京府から小学校裁縫授業生の免許状を下附された。しかし上京して勉学する道も絶たれたので、近隣の少女等に裁縫などを教えていた。唯一の楽しみは歌を作ることであった。
二十八年(一八九五)一月に、猿島郡幸島村から児矢野周蔵を迎えた。周蔵は判事の筆記試験に合格し、口頭試験受験のため勉学中であったが、結婚後病に冒される身となった。
林子は同年十一月十二日男子を分娩したがその夜に死去。周蔵は生家に帰り療養していたが、十八日に病あらたまり死去した。
周蔵辞世の歌
何事もなさではてなん我身こそ世に多具ひなき恨みなりけれ
林子は産後の肥立ち悪く、翌二十九年一月上京して第一病院に入院し、十一月に小康を得て退院。翌三十年には医師のすすめで熱海に転地療養したが五か月ほどで帰郷。翌三十一年(一八九八)には慢性の腎臓炎悪化のため国府津に転地したが、二月十五日急変しひとり転地先で死去した。母の没年と同じ二八歳であった。
辞世の歌二首
父君の深き恵を報いえでさきだつ身こそ悲しかりけれ
かねてより行くべき道と知りつればなど此際に思ひ迷はむ
二月十八日寿広山西福寺に葬った。

Ⅶ-12図 ありし日の関井林子
父庄吉は薄幸の娘林子の死を悼み、その霊を慰めんと、林子の歌稿、日記等を携えて、三十一年六月、歌人佐々木信綱を訪ね、涙ながらに訴えて、遺稿を整理して「関井林子追悼号」を出すことを依頼した。信綱またその至情に動かされて出版されたのが『落葉集』である。
佐々木信綱は、明治における短歌革新運動の一方の旗手であり、万葉研究を中心とする新進歌学者であり歌人であった。林子より一つ若い新進学徒の信綱は、明治二十九年(一八九五)竹柏園歌塾の機関誌として「いささ川」という雑誌を出し、七号で休刊したが、林子死去の月に、改題して「心の華」(後「心の花」)を創刊したのである。
「落葉集」は、三十一年十月編集兼発行者佐々木信綱の名で発行された。
冒頭に「関井林子をいたみてよめる歌」として信綱が九首の歌を寄せている。
三日月の有あけの月とならぬまにいにし吾子よゆきし夫はや
いづる湯のあたみの里の旅まくら心やいかにわきかへりけむ
燈火のくらき夜床にひとりありて息あるうちと筆やとりけむ 等
それに今も日本歌壇史に名を留めている伯爵東久世通禧(みちあき)・川田順・石槫千亦(くれちまた)といった錚々たる信綱門下生たちが、目白押しに追悼歌を寄せている壮観は、まことにみごとという外はない。
『落葉集』『和歌部』には関井林子自詠の歌一五〇首ほどあるが、幾首かを抜萃すると
鶯のともよぶ声をなつかしみ梅さくそのにけふもとひきぬ (熱海にて)
ゆめさむる夜半の枕にきけば猶さびしさまさる軒のはる雨 (病院にて)
かすみたち雪むらきえし野べみれば我心さへ春めきにけり
今もなほ思へば悲しいかばかり心のこしてうせましにけむ (亡母十三回忌に)
世に出む春をまちつるかひもなく草葉の露と消えし君はも (亡き夫を思ひて)
撫子の花のはかなくかれしより露の我身はあるかひもなし (子の亡せる頃)
起出むかひこそなけれ時のまに夫をも子をも先立てし身は (病の床にありて)
うるはしく口にはいえど中々にたのみがたきはひと心かな
たが為に何をまつとて永らえむはかなきものは我身なりけり
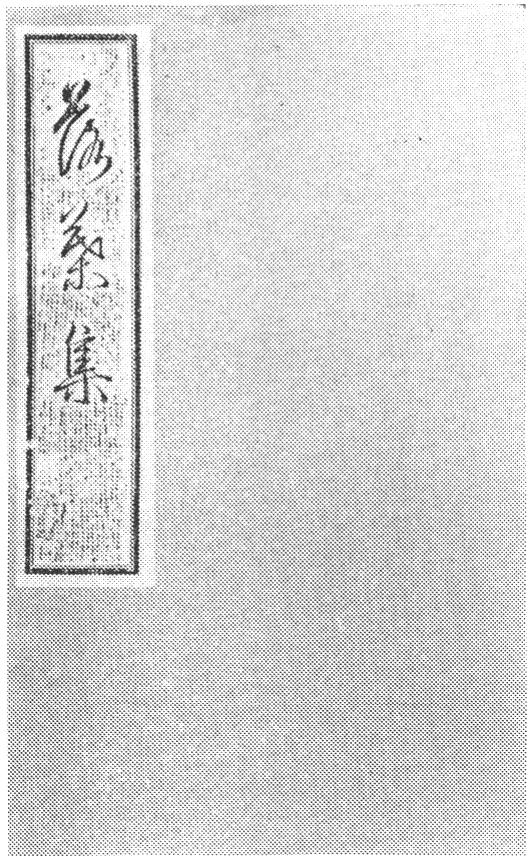
Ⅶ-13図『落葉集』復刻版
(関井修氏蔵)
『落葉集』の終りの方に、林子の妹関井ぬひ子(関井仁氏母堂)と父庄吉の歌がある。
こぞまではともにめでつる庭ざくらひとり見るこそ悲しかりけれ 関井 ぬひ子
遠くともおなじこの世のうちならば文のゆきかひあらましものを 〃
とはるべき子の奥つきをとふばかり悲しきことの世にあらめやも 関井庄吉
はるさめのふる夜な夜なはいとどしく思ひせまりてねられざりけり 関井庄吉
なお、この集には石下町の有志を中心に、宗道、三妻、大花羽等各地の多くの人達が追悼歌を寄せているが、一九歳の長塚節もその一人である。
追悼歌寄稿の顔ぶれをみると、今さらに当地方の歌壇の層の深さと広さを思いしらされ、文学的風土のゆたかさに驚かされる。
ちりしみのうらみや深きみし人のなげきやおほきあたらこの花 長塚節
春ごとにかはらぬものはおくつきに植し手向の花にぞありける 荒川隆之助
うつくしとめでつる花も夢のまにみをも結ばでちりすぎにけり 小林林助
時ならぬあらしに花はさそはれてちりにし庭にはるさめぞふる 幕田繁次郎
春もややくれゆく庭の葉ざくらにいとどむかしの忍ばるるかな 荒川辛
さけばちる花とおもへど涙がはうき世のせきをこさで行くとは 中山橘之助
左記の人達も歌を寄せている。
中島観琇・高橋正賢・高橋謙次郎・荒川玄周・中川政之助・山田福三郎・荒川徳次郎・荻野酉之助・
高橋益三郎・幕田孫作
ある学者の研究によれば、長塚節の初期の指導者は関井林子でなかったかといわれる才女であった。