
島松沢を国道36号から望む美しい谷戸の風景
谷戸、川辺の生き物たち
―――魚―――
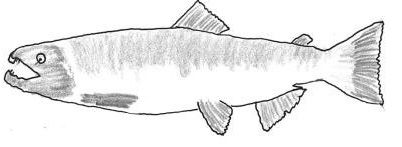
サクラマス
サケ科
道庁が名付け親
大きいものだと70cmにもなる。回遊魚で春に遡上し秋に産卵する。河川残留型をヤマメとも言う。
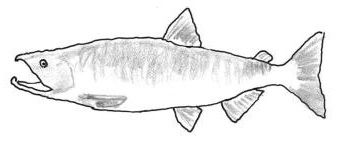
サケ
サケ科
全長50cmほど。1~6年海洋生活を経て10月から12月に生まれた川に戻り産卵する。

エゾサンショウウオ
サンショウウオ科固有種
全長15cmほど。森林に近い止水域に生息している。雪解けの後に池や用水路等で産卵する。
―――鳥―――
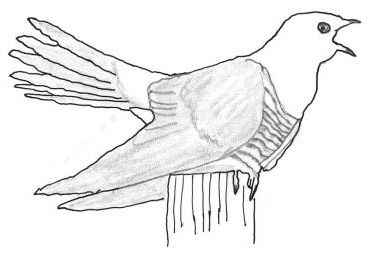
カッコウ
カッコウ科
全長30cmほど。本州では山地の鳥だが、北海道では里地や平地にも生息する夏鳥。
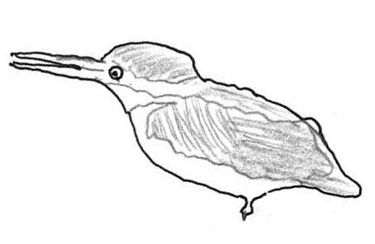
カワセミ
カワセミ科
全長15cmほど。北海道では夏鳥で冬は暖かい場所へ渡る。鮮やかな水色の体色と長いくちばしが特徴。
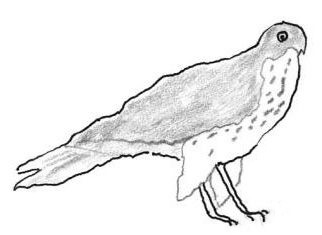
オオタカ
タカ科
全長50cmほど。食物連鎖の頂点に位置する猛禽類。近年は人里近くでもみられる。
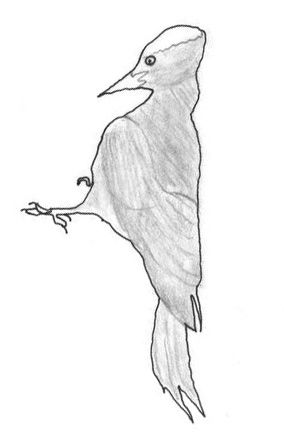
クマゲラ
キツツキ科 天然記念物
全長50cm超えるものもいる。全身は黒い羽毛で頭部のみ赤い羽毛がある。
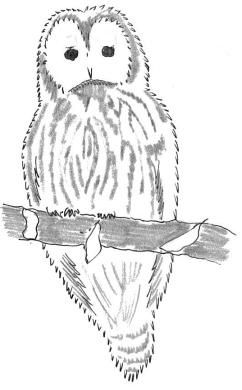
エゾフクロウ
フクロウ科
全長50cmほど。大木の樹洞などに営巣。夜行性で夕方から活動をはじめ、ネズミや小鳥を捕って食べる。
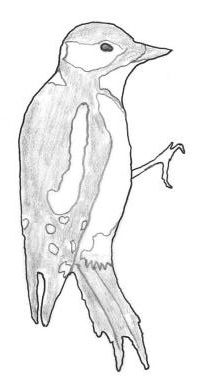
アカゲラ
キツツキ科
全長20cmほど、もともと亜高山帯の鳥だが寒冷地の北海道では低地に生息する。針広混交林で主に見られる。
―――動物―――
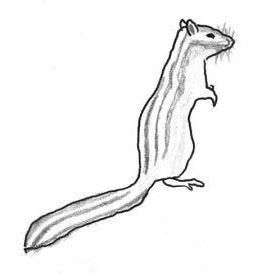
エゾシマリス
リス科
体長は15cmほど、尾は10cmほど。人里近い林野でもみられる。冬は樹洞で冬眠をする。
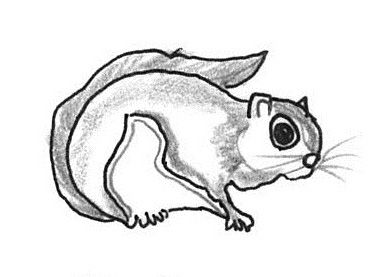
エゾモモンガ
リス科
体長は16cm程。学名の由来は「翼のあるネズミ」夜行性、雑食性。
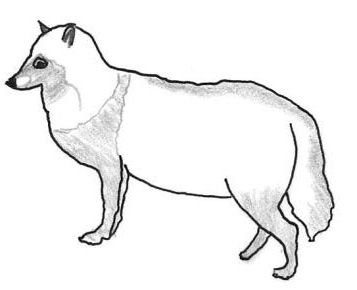
エゾタヌキ
イヌ科
体長は60cm程。里に近い林や、川・沼沢がある地域に生息する。夜行性、雑食性。
―――昆虫―――
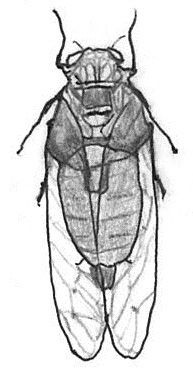
エゾハルゼミ
セミ科
全長2-3cmの小型のセミで、北広島では人家近くでも鳴き声が聞こえる。5月~6月ころに鳴く。
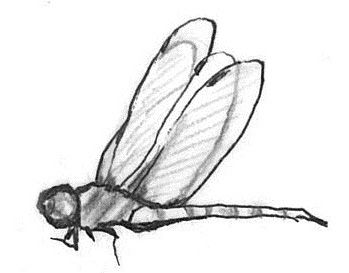
ルリボシヤンマ
ヤンマ科
全長8cmほど、寒冷な気候を好み、池や湿地に多く生息している。雄では斑紋の一部が水色になる
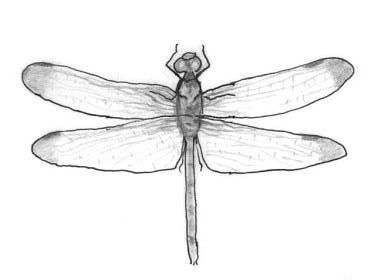
ノシメトンボ
トンボ科
全長は5cmほどの翅の先が茶色いアカトンボ。民家の庭や田畑でもよく見られる。