まず、廻り田新田の斉藤家に残された多くの返草をみると、それぞれ投句者の広がりに広狭はあるが、小平市域の俳人のみで構成されたものが確認できる。文化六年(一八〇九)一二月下旬の「珉江亭朗月評句集」をみると、廻り田新田、恋ケ窪村、内藤新田、本多新田、榎戸新田の九名と、不明二名の計一一名の俳号が確認できる。高評点者は、廻り田新田の玉桜が三九点で「天」、恋ケ窪村の舟江が三九点で「地」、恋ケ窪村の深海が三五点で「人」と続く。主催者と思われる「珉江亭朗月」なる人物については不明であるが、この地域の人物とも考えられる。

図3-15 「(珉江亭朗月評句集)」文化6年極月(斉藤家文書)
幕末期以降、近隣の恋ケ窪村(現国分寺市)では、この地の出身で、江戸の俳諧宗匠である宝雪庵蘭山(ほうせつあんらんざん)に弟子入りした宝雪庵可尊(かそん)(坂本八郎兵衛)を宗匠とする俳諧連が存在した。可尊は、幕末期から明治初年にかけての北多摩地域において、太白堂孤月(たいはくどうこげつ)と勢力を二分するほどの影響力を持った人物である。寛政一一年(一七九九)に生まれ、文政年間(一八一八~三〇)にはすでに蘭山の俳諧連に属していた。帰郷するのは明治元年(一八六八)であるが、それ以前より多摩地域で活発な活動を行っている。
さきにみた文化六年「珉江亭朗月評句集」で高得点を獲得している深海は、この可尊の父である。この句集は可尊が俳諧宗匠として大成する以前のことと考えられ、このような小平市域の俳諧連の存在が、可尊を輩出する基盤となっていたことがわかる。
年月日未詳であるが、「蓼窓評句集(りゅうそうひょうくしゅう)」には、「珉江亭朗月評句集」に投句した者と多く重なるほか、小川新田の琴松、鈴木新田の黒松・楚月らが名を連ねている。また、同じく年月日未詳の「南華評句集」では、廻り田新田の玉桜、鈴木新田の黒松・楚月のほか、小川新田からの多くの投句者があり、芦原・琴松・崎松・花渓や大沼田新田の徳次郎が名を連ねている。
月並発句を行うには、投句の募集から評点付け、返草の印刷・配布と、多大な時間と労力、費用を要する。この「珉江亭朗月評句集」などがどのような形で行われたのかは定かではないが、ほかとほぼ同様の作業を行っていたと考えられる。つまり、小平市域内において、このような月並発句を継続的に行うことを可能とする文化的環境が整っていたといえる。
斉藤家文書に残された史料から明らかになったものであるため、玉桜を中心とした俳諧連を抽出することができたが、玉桜の存在はこの地域で大きな意味を持っていたことは間違いない。
つぎに、小金井橋の袂で料理屋・旅宿を経営していた柏屋勘兵衛を担い手とした文化活動があげられる。柏屋勘兵衛については、本章第四節で詳しくみるが、江戸や周辺地域の文人らと小平地域との結節点となっていた人物である。柏屋の二階の座敷には、桜花を詠んだ詩歌を請う帳面が備えられ、文人墨客がこぞって記帳した。柏屋勘兵衛自身も「主人風雅のもの」といわれるような文人であり、柏屋が小平地域の文化活動の拠点となっていたことがわかる。
柏屋勘兵衛がかかわった月並発句の広告が、廻り田新田の斉藤家文書のなかに残されている。未二月とあるのみで年代は確定できないが、近世後期のものと考えられる。催主の筆頭には「武城西小金井郷」の清貧亭秀国とあり、以下、連光寺村(現多摩市)の山梁舎沢雉、小田文(分)の幽篁窓白友、府中(現府中市)の芳雪斎芝丘、小金井橋の柏屋勘兵衛、府中明神前の松本屋甚五左衛門、八王子宿(現八王子市)の小谷屋彦太郎と続く。
その告知文を次にあげておく(句点は筆者註)。
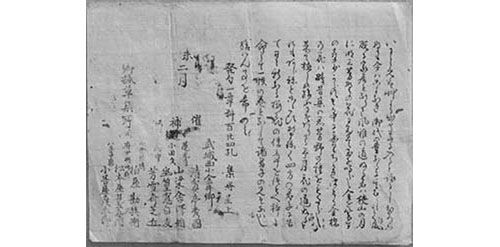
図3-16 「(桜花佳章の発句集販布案内)」
末2月(斉藤家文書)
いにしえは、艸より出て草に入ると詠にしひろき野も、今ハこよなき御代の豊なるに其むし其くま、既に家居となりて風雅の道ふる君ハ、狭山の月に明、三芳野の花に暮て、玉を鳴らし金を響すの声少からす、その中に我里ちかきほとり金橋の花ハ、疇昔某の君、芳野の種をもたらし来て植しめ給ふにそありける、予月花の道ふるとにもあらねと、こたひあまねく四方の君子に告て、日々新なる桜花の佳章をつとへ、梓に命して一帙の巻となして、諸君子の見そなハし給ハん事を希のみ
冒頭の「艸より出て草に入る」とは、『万葉集』に詠まれた「武蔵野は月の入るべき山もなし 草より出て 草にこそ入れ」のことである。この地域は古代より詩歌に詠まれるナドコロ(中世までの詩歌で修辞的用法として使用された地名)であった。かつては広大な野原であった武蔵野は、今は開墾されて多くの家屋が建っており、そこに居住する風雅を嗜む人びとに向けたものである。
この告知文で注目されるのは、金橋桜花を新たな名所として位置づけようという意図が読み取れることである。『万葉集』で詠まれてから長らく「武蔵野」という言葉がナドコロとして認知されていたが、近世になると、この地域では主に「狭山の月」と「三芳野の花」が名所・景物として詠まれるようになっていた。それに対し、「我里ちかきほとり金橋の花」への注目を促している。広く投句を求め、それを句集として編さんして配布することで、金橋桜花を地域の名所として確立しようと試みているのである。
この文化活動の中心となっていたのは、「武城西小金井郷」の清貧亭秀国と柏屋勘兵衛であったと考えられる。そして、協力者として、府中や八王子の文人らが加わっていたと考えるのが妥当である。つまり、小平市域の住民が主体となった金橋桜花の名所化であり、それを拠点に地域文化を確立しようとしていたといえるのである。
さらに、この時期には、江戸の文人らの活動により、「金橋桜花」は江戸近郊の名所として江戸住民に認知されていた。この月並発句は、行楽客としての江戸の文人だけに向けたものではなく、地域住民に向けた金橋桜花の名所としての位置づけを確立させるための活動として評価できる。江戸文人らと協力した江戸の居住者へ向けた金橋桜花の名所化の活動とは別に、地域住民に対する名所化と地域文化の拠点としての位置づけを目指したものであった。
最後に、玉桜こと廻り田新田名主の斉藤忠兵衛の詠句についてみることとする。「鬼染主人」にあてた書付には、つぎのような句が記されている。
「秋の雨 稀なる客の 縁へかな」
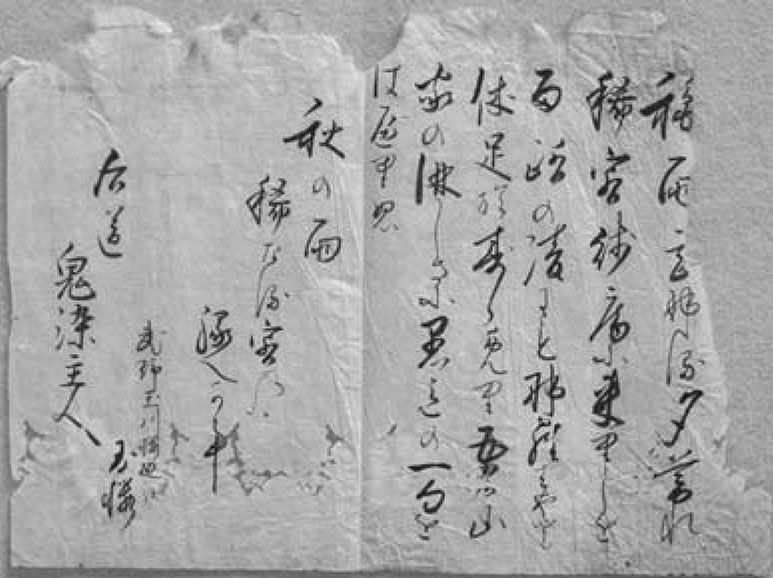
図3-17 「(秋雨の句)」(斉藤家文書)
この詠句の解説も記されており、秋雨の激しく降る夕暮れに、稀な客が賤庵にきたので、雨路のしのぎにもなればと休息を進めたが、我が山家の寂しさに愚意の一句を詠んだものという。
玉桜は自らの居住地について、「武野玉川桜辺住」と記しており、金橋桜花が強く意識されていたことがわかる。一方で、〝秋の季節の稀なる客〟を詠んでいることから、金橋桜花が存在するこの地域が、あくまでも桜の季節のみのものとして注目されることに対し、四季を通じて存在していることを居住者として訴えかける意図も込められているとはいえないだろうか。
このように、小平市域では、単に俳人が存在していたというだけでなく、自ら主体的に文化的拠点となる金橋桜花の名所化をはかるとともに、多摩地域においても地域の文人らを利用しつつ、名所としての確立を目指して文化活動を行っており、一つの文化圏-小平文化圏-が存在していたといえる。