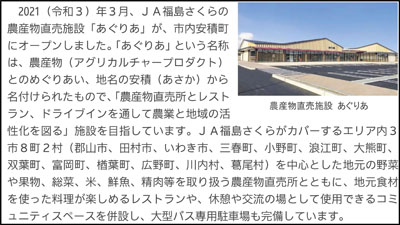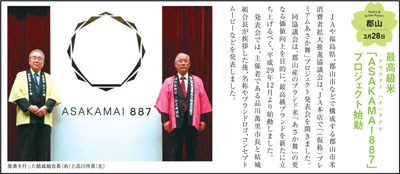前述のように2012(平成24)年からの郡山市の農業の重要な課題は、農地除染と米の全量全袋検査など、農地・農産物の各段階での原発事故影響の克服にあったが、そこから新たな農業や農産物の流通を創造して地域再生や経済活性化に展開していく動きが様々なレベルで模索された。
従来から本県JAグループの中では合併構想が議論されてきていたが、震災により停止していた。郡山市を含む中通りにおいて震災直後の影響が落ち着いたところで、2013(平成25)年3月に全県にJA合併推進協議会が設立され、郡山市を含むエリアでは、2014(平成26)年に、郡山市・たむら・いわき・いわき中部・ふたばの5農協の合併の基本構想がまとまり、翌2015(平成27)年5月に合併農協の名称を公募案の中から「JA福島さくら」と決定した。その後、同年度末(2016(平成28)年3月)に新農協が発足した。
本合併農協は、震災後の浜通りの地域復興を中通りから阿武隈地域の力で支えることを意図し、本県の猪苗代湖から太平洋まで東西に横断してつなぐ新たな広域農協のコンセプトを「湖(うみ)から洋(うみ)へ」と掲げた。
合併農協は、JA全農とより緊密な連携をして首都圏向けの農産物の出荷体制を整備するとともに、地区ごとの特産品の振興や、地産地消・直売所・農産物加工・食農教育を通じた地域活性化に尽力していくことが求められる。
また、旧JAたむらで振興していたサツマイモを、郡山市や双葉地区でも普及していくことなど、広域合併のメリットを生かし、生産振興の効果につなげていくことも課題である。
合併後、JA福島さくら郡山地区は、農産物直売所と市内産の米の新たなブランド化に注力した。
従来からJAの郡山市の農産物直売所としては、前出の市内の直売所のうち、富田町の「富田ふれあい朝市」、「旬の庭」大槻店・久留米店があったが、加えて新規事業として、安積町に「あぐりあ」を2021(令和3)年3月に開店し、広域農協の範囲である郡山市・田村市・いわき市・田村郡の2町、双葉郡の6町2村の合計3市8町2村で生産された農産物やキノコ、精肉、それらの加工品などを取り扱い、交流スペースも充実させた。なお「あぐりあ」開店に合わせて、近くに立地していた同農協の「旬の庭」久留米店は2021(令和3)年1月に閉店している。
また、JA全農福島の直売所「愛情館」は、2013(平成25)年5月に新装開店し、3年後の2016(平成28)年5月に来店者数100万人を達成するなど、市内の小区域ごとの農産物直売所と一段異なる存在感を発揮しており、福島県全体の農産物を豊富に取り扱い、広域から消費者が集う拠点としての地位を確立している。
JA福島さくら郡山地区は、市とともに「こおりやま食のブランド推進協議会」を2018(平成30)年5月に立ち上げ、市内産の農産物、とりわけ主食用のブランド米「あさか舞」(品種はコシヒカリ・ひとめぼれ)の普及に取り組み、そして2018(平成30)年度から、郡山市の米消費拡大推進協議会とも連携して、あさか舞の新ブランド「ASAKAMAI887」(あさかまいはちはちなな)を生み出した。
これは従来よりふるいの目を広く2.0mmとし、大粒で粒ぞろいで良食味が保証されたプレミアム米としたもので、それを含めて七つの基準、1.食味値88点以上であること、2.タンパク質含有量6.1%以下であること、3.ふるい目2.0mm、4.整粒歩合80%以上、5.特別栽培米であること、6.GAP(農業生産工程管理)に取り組むこと、7.エコファーマーに認定されていることを全て満たすことが課せられる。
なお、本『郡山市史 続編5』の対象期間から外れるが、2018(平成30)年から2022(令和4)年までの5年間は当初の基準を継続し、2023(令和5)年からは6.GAP認証取得者(取得農場)に限る、7.カーボンニュートラル水田(中干し期間を長くとってメタンガス発生量を削減する取り組みによる)に限る、と移行した。
新ブランド米は、長く水田を維持して稲を育てて米を作ってきた伝統的な水稲農家の88の手数を顕彰し、さらに現代の高い目標である7基準を付加し、併せて「887」と名付けたものである。資源・環境を守って水田で米作りをする営みを広く消費者・市民の理解と支援によって永続させようとする郡山市の水田農業のフラッグシップとしての役割を担うもので、広域JAとしてこのように単一の自治体の米のブランド化に力を入れる例は稀であり、今後の広がりが注目されるところである。一方では、気候変動の下で米作りには従来以上の苦労が出てきている中で、この高い基準を満たすことには多くの課題もあり、消費者や米穀事業者は、この意欲ある7基準を目標として掲げた郡山市の水田農業の目的をよく学んでいく姿勢が求められている。
「ASAKAMAI887」は、前述のJA直売所で販売される他、開成マルシェのようなイベントでも毎年展示・即売される。また、田村町の老舗・宝来屋がこれを原料とし甘酒を製造している。