『武徳編年集成』によると、慶長十一年(一六〇六)十二月二日、「神君(家康)の密旨に依て台徳公(秀忠)古河・下妻・佐竹筋巡視し給ふべき為に、放鷹と称せられ、今日江城(江戸城)御出輿」という記事がみえる。当時鷹狩にことよせて関東各地を巡視していた徳川氏の政策の一端が知れよう。また『徳川実紀』には、慶長十八年九月二十八日に「大御所越谷に狩したまふ、二十九日大御所西城に還御なる」という記事があり、このときは家康みずからが越ヶ谷を訪れている。
続いて同年十一月二十日の記事には「大御所には岩槻より越谷にわたらせられる。本多上野介正純小山より参りむかへ奉る、廿一日大御所御鷹狩有て鶴三雁十六得給ふ、廿四日近郊の農民大御所御狩の路に出て、訴状をさゝげ代官の私曲を訴ふ、御旅館にかへらせ給ひ、秉燭の後双方を召して訴訟を聞き召さるゝ所、農民非拠たるにより首謀六人禁獄せられる、大御所越ヶ谷に於て日々御放鷹あり、鶴十九得給ひ御けしき大かたならず、明日葛西にならせ給ふべしと仰出さる、廿七日越谷より葛西にならせ、御道にて鶴六得給ふ、御旅館より御使ひもて松平政宗へ鮓・枝柿・山椒をたまふ」とあり、家康は越ヶ谷において七日間にわたる鷹狩を行なっている。ここで注目されるのは、在地の農民が訴状をささげ代官の私曲を直接家康に訴えており、家康はまたこれを受けてじきじき越ヶ谷御殿で裁判を行なっていることである。
幕府の行政組織が整い、近世的吏僚制度による地方支配が完備すると、将軍ならびに領主への直訴は厳しい法度(はっと)として禁ぜられた。すなわち幕領の場合は、村役人―代官―奉行―評定所―将軍という訴訟ルートが確立され、農民が将軍に直訴することは重罪として処罰されたのである。しかし幕初の慶長・元和期の段階では、幕府吏僚による行政機構もまだ不充分であり、在地土豪層がそのまま地方代官として農民を支配していることが多かった。家康は、こうした在地権力を排除し、幕府の忠実な吏僚機構をつくりあげるため、在地の農民が代官等郷村の支配者に反抗することも許した。
これは慶長七年(一六〇二)十二月六日に家康が発した三ヵ条と五ヵ条の旗本・代官への二通の定書、続いて翌八年三月二十七日に農民に対して発した七ヵ条の定書(中村孝也『徳川家康文書の研究』)によって端的に知ることができる。これらを要約すると、まず郷村を支配する代官・旗本に対しては
(1) 農民が地頭の不法な支配を理由に逃散した時は、地頭がどのように言いわけをしても農民を帰村させることができない。
(2) 年貢は近辺の村々の年貢率を標準にし、年貢未進の際は奉行所でその年貢量を算定する。
(3) 農民を殺害してはならない。農民に罪があったときは、奉行所で対決のうえ裁判を行なう。
という内容であり、一方農民に対しては、
(1) 地頭や代官に不法があった場合、年貢を納めたのちなら農民はどこへ移住(逃散)してもよい。
(2) 農民が地頭の非分を家康に直訴する場合は、村から退去する覚悟を定めてから直訴せよ。
(3) 地頭の非分についての直訴は、地頭に人質を取られ、代官・奉行に再三訴状を出しても受理されない場合に限りこれを認める。
(4) 代官に非分ある場合は、代官・奉行に届けでずに直訴してよい。
というものである。
つまり地頭や代官が不法な支配を行なったときは、農民が農地を捨て離村(〝逃散〟ともいい支配者に対する抵抗の一方法である)することや直訴すること認め、また地頭や代官が、自己の所存で農民をみだりに殺してはならないとし、農民に罪があるときは奉行所が裁判を行なってこれを罰することを明示している。ここでは領民の生死を自己の所存で掌握していた中世領主の検断権(司法権)を否定したものである。
「越ヶ谷瓜の蔓」のなかに、「頭山是は会田出羽手前仕置候者埋申候之由」という記事がある。頭山とは会田氏が自分の所存で仕置に処した者を埋めた塚であるという。この記事は中世における会田氏が越ヶ谷において在地領主的な存在であったことを示唆したものとして興味深い。いずれにせよ家康は、中世来の根強い在地権力をすべて徳川の支配体制に組入れるための、過渡的な一手段として、このような郷村定書を発したものと思われる。
さて、前述の慶長十八年十一月二十四日の越ヶ谷近郊農民の家康への直訴は、その夜越ヶ谷御殿において、訴えられた代官と訴えた農民が対決させられて裁かれた。その結果、農民の訴えが根拠のないものと判定され、農民側の首謀者六名が罰せられた。このような例は慶長十七年十一月の鴻巣鷹狩の際にもみられる。一方代官側が罰せられた例では、慶長十八年十一月、忍の鷹狩の際、代官深津八九郎が職を免ぜられているなどがある。
翌慶長十九年は大坂冬の陣である。この年十月、家康は豊臣秀頼を大坂城に攻め、同年十二月一日一たん講和を結んだ。この講和も翌元和元年四月には破れ、再度大坂城の攻防戦が展開されたが、同年五月、大坂城は落城して豊臣氏は滅亡した。同年八月、家康と将軍秀忠は大坂の役の戦後処理を終え、家康は駿府城に凱旋した。
それから間もない同年九月二十九日駿府を立ち江戸に向った。家康は各地を旅行して廻るときには、あらかじめ自筆の道中宿付を発しているが、このときの宿付は、日光東照宮蔵の「宿付書」によると、九月二十九日清水、十月一日善徳寺、三日三嶋、四日小田原、六日中原、十日藤沢、十一日神奈川とそれぞれ泊りを重ね十二日に江戸着、二十四日蕨、二十八日河越、十一月三日忍、十三日岩付、十四日越谷、二十三日葛西、二十五日江戸、二十八日小杉、十二月二日中原、それから往路と同じ地で泊りを重ね同十五日駿府到着の予定であった。しかし実際はかならずしもこの日程通りではない。このときも同年十月二十一日江戸を出た家康は、足立郡戸田を手はじめに川越・忍・岩槻・越ヶ谷・葛西と廻ったが、日程表にない千葉・東金・船橋と下総の諸地域を廻り、一ヵ月以上にわたり狩をしながら各地を巡遊していた。越ヶ谷への巡遊は十一月十日から十五日にいたる五日間であった。
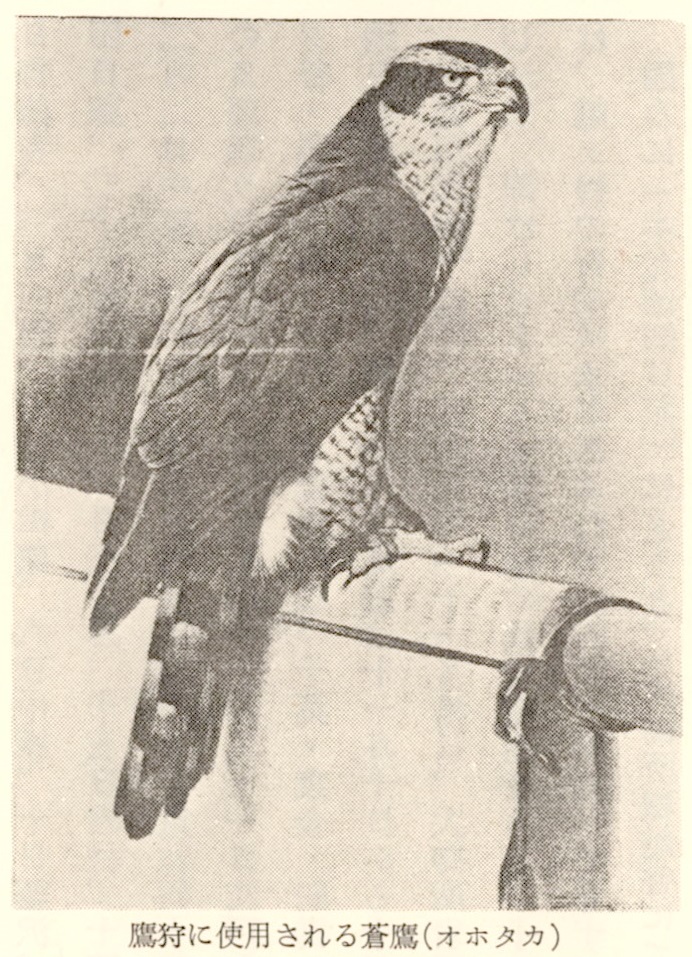

『徳川実紀』には、元和元年「十一月拾日、大御所岩槻より越谷に至り給ひしが、御狩場水泛溢して放鷹を得ざりしかば、御けしきよからず其の地の代官勘発せらる、十五日大御所越ヶ谷より葛西に至らせ給ふ」とある。このときは、越ケ谷の狩場に水があふれていたので鷹狩ができず、機嫌を損じた家康からこの地の代官が叱責をうけている。
因みに「本光国師日記」によると、「大御所様越谷にて少御機嫌悪敷御座候ツルよし、将軍様も御気遣に思召候ツル、もはや御機嫌もなおり候て御大慶之御事に候、従将軍様鳥見ニ被遣候助太夫と哉申人御改易之由候、名字ハ不存候、御鷹場に事外水をせき入、新ひらきなど仕候故と相聞候、其上先年御鷹野之時、はかまかたぎぬで右之助大夫御目見被仕鳥見には似合候ハぬいでたちと御しかりあり被成候、其人又当年御鳥見に出候、其御とがめと爰元にこの御沙汰にて候、委細之様子ハ各より可被仰入候」とあり、御咎にあったのは、苗字はわからないが、助太夫という鳥見の者であると記している。
このとき家康に随行した一行は、宮内庁刊『放鷹』によると、「乗輿の嬬子三人、馬上の婢十八人、且蜂屋九郎左衛門が軽卒五〇人扈従す」とある。すなわちかごに乗った側室三人、馬に乗った女房衆十八人、それに蜂屋九郎左衛門の士卒五〇人が家康に従っていたとあり、はなやかな巡遊であったことか知れる。それにしても家康の越ヶ谷放鷹は、おそらくこれが最後であったろう、翌元和二年(一六一六)四月、家康は七五歳の生涯を駿府城内でとじた。