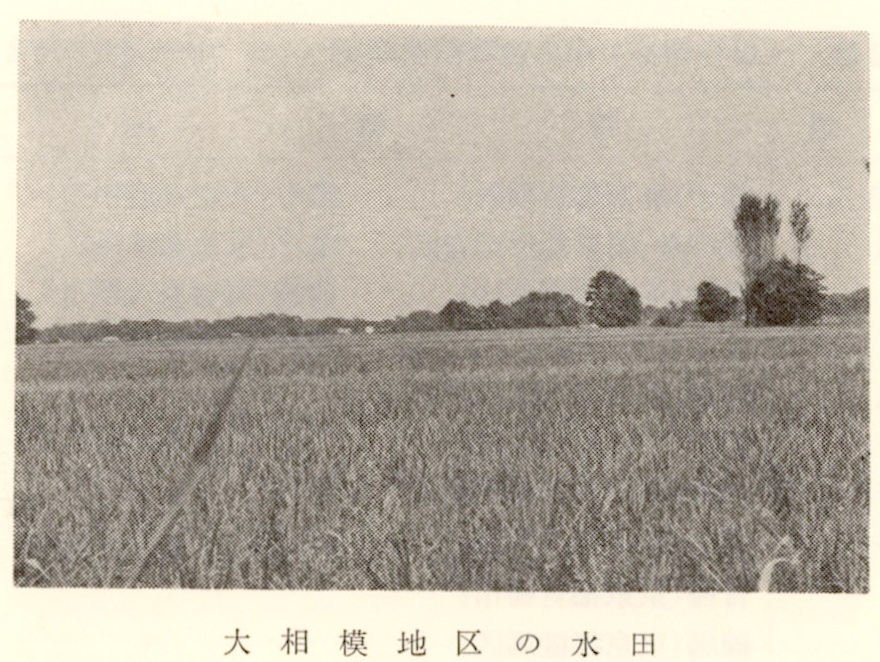越谷出身の江戸時代の俳人として知られる越谷吾山(本編第九章第一節参照)は、「諸国方言物類称呼(しよこくほうげんぶつるいしようこ)」、「俳諧翌檜(はいかいあすなろう)」、「朱紫(あけむらさき)」といった書物を次つぎに出版している。安永八年(一七七九)刊の「俳諧翌檜」には俳人として季語・季題を求める必要上からか、全国各地の名産を記した部分がある。これによって武蔵国の農産物をみると第2表の通りである。
| 品種 | 特産地 | |
|---|---|---|
| 瓜(四谷瓜) | 鳴子(東京都新宿区) | 府中(東京都府中市) |
| 西瓜 | 瀬田谷(東京都世田谷区) | 亀戸(東京都江東区) |
| 砂村(東京都江東区) | 西袋(埼玉県八潮市) | |
| まくわり(未詳) | 大桑(埼玉県加須市) | |
| 越瓜 | 田畑村(東京都北区) | |
| 茄子 | 千住(東京都足立区) | 寺嶋(東京都墨田区) |
| 茗荷 | わせ田(東京都新宿区) | |
| 覆盆子(ふうぼんし) | 関口(東京都文京区) | 駒木野(東京都青梅市) |
| 青梅(東京都青梅市) | ||
| 大根 | 練馬(東京都練馬区) | |
| 蕎麦 | 深代寺村(東京都調布市) | |
| 芋茎 | 赤山(埼玉県川口市) | |
| 夏大根 | 清水村(未詳) | |
| 午蒡 | (空白ママ) | |
| 冬葱 | 同所(ママ) | |
| 糯米 | 越谷(埼玉県越谷市) | |
かれが、江戸近郊農村の特産物をあげたなかに、西袋(現八潮市)の西瓜、赤山(現川口市)の芋茎といった近隣の村々の産物のほか、越谷の〝糯米(もちごめ)〟をあげてある。この糯米とは後述の通り当時江戸市場で高い評価をうけていた太郎兵衛糯を指すものと思われるが、郷土の産物をあげておいてくれたのはありがたく嬉しいことである。吾山の指摘のように、東武蔵の沖積低地に位置する越谷は米作りがその最も主要な産業であったので、まず水田稲作農業からみていくこととする。
江戸時代における越谷地方の水田は一毛作であった。村明細帳によってみると「両毛作御座なく候」(享保十年、西方村)とか、「両毛作場御座なく候」(天保九年、七左衛門村)と記されている。越谷地方の水田は後背湿地に位置する低湿な土地が多く、冬期にも水はけが悪いので、裏作は行なわれず、水稲の一毛作地帯であった。もっとも水稲の外には蓮・慈姑(くわい)などの根菜作物を栽培し商品化していた。作付方式は水稲と輪作したり、混作する方法であったと思われる。