次頁に掲げた第39表は、安永二年(一七七三)から同四年にいたる砂原村六左衛門家の収支勘定である。六左衛門家の田畑の所持高ならびに家族構成はつまびらかでないが、若干の小作地を持ちまた奉公人や日傭人を使用して手作地を経営する高持層であったことは確かである。六左衛門は安永二年に親から家督を譲られたが、かれは、当主となった安永二年から四年までの収支勘定をしたためた「書記」に、農家経営の破綻をつづり、翌安永五年に隠居した。
| 収入 | 金6両2分 | 銭272文 | 繰越金と米15俵の代金 |
| 金37両1分3朱 | 〃92文 | 田地売却代 | |
| 金19両1朱 | 〃32文 | 米65俵分代金 | |
| 計金63両1朱 | 〃52文 | ||
| 支出 | 金30両3朱 | 〃216文 | 借財返済金 |
| 金22両1分 | 奉公人給金未払分と前金 | ||
| 金17両3分 | 〃309文 | 両親小遣及び生計費 | |
| 金2両2分 | 畑方年貢と普請金 | ||
| 計金72両3分 | 〃181文 | ||
| 差引 | 金9両2分3朱 | 〃129文 | 不足額 |
(注)1両=銭5貫500文相場
1両=米約1石3斗相場
| 収入 | 金19両3分 | 銭7文 | 米72俵分代金 |
| 金35両2分 | 〃300文 | 田地売却代 | |
| 計金55両1分 | 〃307文 | ||
| 支出 | 金22両2分 | 〃24文 | 質地金返済 |
| 金17両2分3朱 | 〃181文 | 両親等小遣及び生計費 | |
| 金11両3分2朱 | 奉公人給金 | ||
| 金3両1分 | 賃金 | ||
| 金8両1朱 | 〃146文 | 肥料代 | |
| 金3両2分2朱 | 〃275文 | 講金払 | |
| 金9両2分3朱 | 〃139文 | 前年繰越不足金 | |
| 計金76両3分1朱 | 〃167文 | ||
| 差引 | 金21両2分 | 〃204文 | 不足額 |
(注)1両=米約1石4斗余
| 収入 | 金21両 | 銭294文 | 米58俵分代金 |
| 金8両2分 | 講金借用 | ||
| 計金30両2分 | 〃249文 | ||
| 支出 | 金9両2朱 | 〃334文 | 小遣及び生計費 |
| 金3両2分 | 肥料代 | ||
| 金21両2分 | 〃204文 | 前年度繰越不足金 | |
| 計金34両3朱 | 〃201文 | ||
| 差引 | 金3両2分2朱 | 〃244文 | 不足額 |
(注)1両=米約1石余
1両=銭5貫400文
この「書記」によると、六左衛門は安永二年の三月に、銭三貫六〇〇文と米一五俵(代金五両三分と銭八〇〇文)を親から引継いだ。この年、おそらく累積した借財の清算にあてるためと推定されるが、金三七両余で所持地のうちの一部田地を売却した。したがって当年の六左衛門家の総収入は、銭三貫余の繰越金と繰越米一五俵の代金五両三分余、それに当年の収穫米六五俵の売却代金一九両三分余と金三七両余の田地売却代をあわせ、合計金六三両一朱余であった。これに対し支出は、借財の返済金三〇両三朱余、奉公人給金の未払分と前渡金が金二二両一分、両親の小遣いならびに六左衛門家の生計費が一七両三分余、畑方年貢金と普請金が金二両二分であり、差引き金九両二分余の不足勘定であった。
翌安永三年度の収入は、再び田地を売却した代金三五両二分余と米七二俵の売却代金一九両三分余で合計金五五両一分余であった。これに対し、当年の支出は、質地金の返済金二二両二分余、両親の小遣いならびに生計費が金一七両二分三朱余、奉公人給金一一両三分余、そのほか日傭人の賃金や肥料代金、講金の支払いや前年度の繰越不足充当金などで、金二一両二分余の不足額を生じた。
翌安永四年度は、収入が米五八俵の売却代金二一両余と講金の借入金八両二分であり、合計金三〇両二分余に対し、支出は両親の小遣いと生計費の金九両余、肥料代金三両二分、それに前年度の不足金二一両二分余を充当しただけで、すでに金三両二分二朱余の不足になった。しかも当年は両親の小遣いを半額に減らし、六左衛門家の生計費も極度に切りつめたが結果は同じく赤字であった。このため六左衛門は農家経営に自信を失い、将来に不安を感じて翌安永五年に隠退を決意した。
六左衛門の書き記した「書記」には、このほかの収入に、畑方小作金などがあるが、この小作金は年々の役金に充当したので、収支勘定には記さなかったとある。また大山講や秩父講の講金を借用し、これにさらに利金を加えて他人に又貸をしている。この講金の運用は、たとえば不動講金のうち銭一一貫二六四文を利金一割で預かったが、このうち一〇貫文を年利一割半で又貸している。ほかに若干の貸借があるがこれは別紙に記すとあり詳細は不明である。
さらに、「このような収支勘定であるので、私の経営ではとても身上向きが立ちゆきません。そこで両親ならびに名主・五人組・諸親類に面目が立たないので隠居を願ったが、両親はことのほか立腹です。私はよくよくの罰あたり者、どうか私を犬と思召めしてご了簡なされ、名主はじめ五人組・諸親類から両親にお詫びを願います。私の跡式は養子八蔵に渡したく、ひとえにお世話頼み入ります。なお、八蔵が成長のうえ、身上賄いができるまで、伯父上が八蔵の後見となって面倒をみていただき、両親に苦労をかけぬよう願いあげます。つぎに私の妻は、少々金銭がかかりますが、小曾川村の実家にお返し下さい。また私の娘は八蔵の心にかなうように仕向け、ゆくゆくは一緒になるようにして下さい。」と記し、終りに両親・名主・五人組・諸親類宛の起請文と歌をしたためている。この起請文は「拙者儀身上に望み御座なく候事」との一ヵ条を示し、なお「右の人々様なにとぞ拙者家を出ても、当家に出入り相成り候様に、ひとえに願い上げ候」とあり、続いて「我が身をば どう成とても わすれ草」、「わすれなみ 身はくもいに成ぬとも 空行く月のめぐりあふまで」の歌を記して結んでいる。当主隠退にあたっての、六左衛門の悲愴な心情がうかがえるものである。
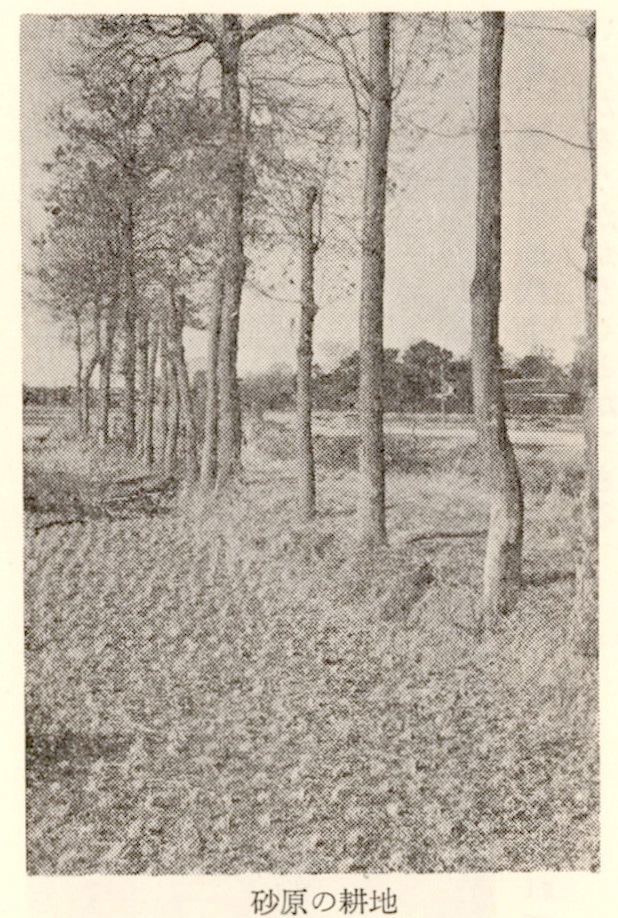
では、はたして農家経営における六左衛門の無能が家計の破綻を招いたものであろうか。この簡略な収支勘定書ではすべてを明確につかむことはできないが、当時の農家経営の一つの問題が秘められていると思われる。六左衛門は安永二年と同三年に、一部の所有田地を売却し、質地などの累積借財を返済したとみられるが、借財がなくとも収支の均衡が大きくくずれていたことが知れる。たとえば安永三年度の収支をみると、六左衛門家の唯一の実収入である米七二俵分の代金が、金一九両三分であるのに対し、金一一両三分余が生産労働のための奉公人の給金や日傭人の賃金にあてられている。つまり奉公人の賃金が高額であり、手作地の拡大経営はすでに困難な状況であったことが知れる。また、六左衛門家の生計費は、両親の小遣いを含め、米の売却代金に近い金一八両近くもが消費されている。いかに農家の家計が貨幣経済の進行によって混乱していたかをうかがうことができる。
すでにこの時期の農家経営は、貨幣経済に適応した方法への切換えが必要であったとみられよう。すなわち奉公人や日傭人を必要とする手作地を小作地に変えるか、米のほかの商品作物の栽培に力を入れるか、あるいは農間余業に活路を見出すか、いずれにせよ六左衛門家にみられるごとく、米作一筋の純農業経営では行づまりをみせていたことが知れよう。しかも当時こうした行づまり経営が一般的であったため、貨幣経済に対応できた一部の農家は、高利金融などで土地を集積する傾向にあり、このため村内における階層の分化が急速に進行しつつあったのである。