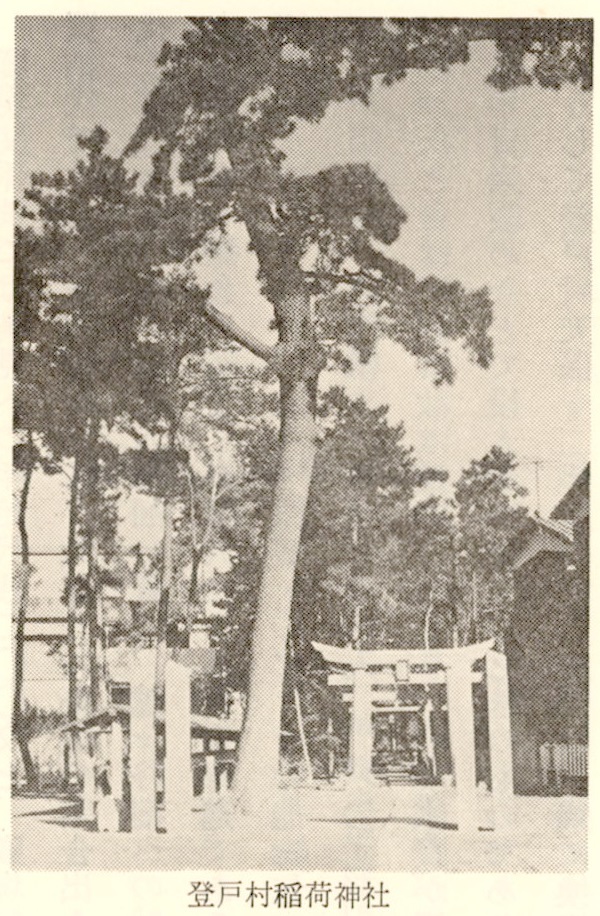登戸村関根家文書文政元年(一八一八)の「村入用帳」によって、村高二八九石余の登戸村の村入用をみると、もっとも大きな出費は伝馬諸掛り金八両である。内訳は伝馬雇出賃銭のほか助郷惣代給料・会所入用費などである。
つぎに比重の大きいのは、用水等河川関係の諸普請費金二両と銭二貫八一一文である。この内訳は川俣圦番給ならびに川俣用水触次給など諸給料割合分銭一貫九八四文、葛西用水水防諸入用割合銭二貫八七四文、このほか綾瀬川藻刈入用・瓦曾根溜井廻り入用、往還掃除入用などである。また登戸村は幕府領であるが、この地域は紀伊家鷹場のなかに含まれていたので、鷹場の出費もある。このなかにおそらく鷹に与える餌鳥のそのまた餌とみられるみみずも紀伊家に納めることになっている。したがって登戸村の当年の鷹場出費は、鳥見役の宿泊賄い割合分銭五七六文のほか、八月に一三五七筋のみみずを蒲生村の市郎左衛門から銭一貫一三〇文で購入し、冬にも銭六九一文分のみみずを買ってこれを納めていた。
このほか当村も浪人や旅僧の合力、あるいは諸寺社の勧化を村入用で取扱かったが、旅僧への喜捨が二件で銭三二文、諸勧化の喜捨がすべてで銭四〇八文に対し、浪人への合力は銭四六〇文である。浪人は三人四人と集団で訪ずれていたのは砂原村と同様であるが、登戸村では一件あたり銭一二文、あるいは銭二四文を与えていた。なお当年の登戸村の名主出府旅費は銭一貫八二文、飛脚や駄賃代が銭九四四文、幕府諸役人の宿泊賄いが金二分と銭五二四文、筆墨紙ろうそく代が銭一貫六四文、代官へのお年玉が金一分などである。
さらにこの村入用の比率をわかりやすくするため、同じ登戸村の天保十二年(一八四一)度の村入用を種別ごとに示したものが第41表である。ただしこれには増助郷免除願雑用費を除いて助郷関係費用が記されてないので、おそらく助郷費用は別勘定に扱われたとみられる。この助郷諸掛りを除いた登戸村当年の村入用で占める割合の大きいのは、用水等土木関係費である。このうち主なものを挙げると、用水浚いの人足賃、綾瀬川の藻刈賃、川俣井筋普請分担金、用水圦番給、瓦曾根溜井廻り普請入用費などがある。つぎに割合の大きいのは年寄や定使いの給料小遣いである。このうち金二両は年寄四人分の給料、金二分が年寄四人分の小遣、金一両一分二朱が定使の給金である。登戸村では名主給は役高引であったので、名主の給金はない。
| 種別 | 合計額 | |
|---|---|---|
| 用水等土木関係費 | 金4両2分 | 銭1803文 |
| 年寄・定使給料小遣 | 〃3両3分2朱 | |
| 鷹場関係費 | 〃2分 | 銭6959文 |
| 往還掃除費 | 〃1分3朱 | 〃947文 |
| 諸材料費 | 〃1分1朱 | 〃1382文 |
| 囚人送り入用割合 | 〃1分1朱 | 〃321文 |
| 諸勧化喜捨代 | 〃3朱 | 〃1208文 |
| 浪人等合力代 | 〃2朱 | 〃2032文 |
| 村役人江戸出府旅費 | 〃2朱 | 〃2780文 |
| 増助郷免除願雑用費 | 〃2朱 | 〃203文 |
| 幕府役人休息賄費 | 〃3730文 | |
| 寄合・筆墨紙代 | 〃2898文 | |
| 飛脚賃 | 〃286文 | |
| 合計銭75貫740文 | ||
| 1軒当り平均 銭2貫705文 | ||
鷹場関係費では鳥見への年始代銭二〇〇文と、鷹場触次給や組合諸雑費金一朱と銭三八七六文を除くと、みみずの買納代である。往還掃除費は日光道と八条道の割合出金分であり、諸材料費は橋の掛替えなどに使用された丸太や竹代などである。囚人送り入用割合費は、越ヶ谷宿への助合出金分であり、諸勧化喜捨代は、子安観音・妙儀大神宮・赤城大神宮・鎌倉八幡宮・出雲大社などへの寄進である。合力代では、特別な措置であったとみられる金二朱の老人飯料泊り賄いを除き、浪人・旅僧・ごぜ・その他物乞への喜捨であり、なかでも浪人合力が主なものである。村役人の江戸出府は、宗門帳や触書請書の納入、年貢小手形引替えなどで、支配役所へ年間五、六度は出張するが、訴訟などがあったときは出張日数は長期にわたり、その旅費が嵩むときもある。このほか幕府役人休息賄い費は、例年代官所から年貢米改めなどで役人が出張するときのものであり、また普請所見分で廻村する普請役人などもいる。
こうして登戸村天保十二年度の村入用費は、銭に換算すると七五貫七四〇文であり、一軒あたり平均銭二貫七〇五文であった。この費用の徴収は、村割・惣割の別が設けられていたが、高割合で出金したので、農民のなかでも持高の少ない者は銭二〇文あるいは銭三〇文の出金ですんだ者もいる反面、銭三〇貫文の割当をうける農民もいた。