山崎家に所蔵されている近世資料の中に、平田篤胤の書簡が保存されている。保存状態はあまりよくなく、完全な形のまま保存されたものは少く、断片として残されたものがほとんどである。その上、巻尾のあるものは月・日については知れるとしても、年の記載された手紙は一通もない。そこで山崎家に残された、平田篤胤の書簡の考察と発信年・月・日の推考を試みた。
資料1
(上欠)奉存候、然者平田大人署神代系図近〻すり出しに相成候に付、其御地御門人方江内談に則平田世話人伊助と申仁差遣し申候間、右方々より御承知も有之候哉、右系図之儀仕立に相成金六両ほと不足に而差支に相成候ニ付、御地御門人方え御無心差上申候、大かた貴君様へは別段御出情相願可申哉にも候、何卒無余日返金為致申候間御聞済之様子御談合可被下候、委細伊助・市右衛門・善兵衛より御承知之上奉願候、先は右之段申上度如此に御座候、
二白 当十九日は是非 (下欠)
この書簡は平田世話人が入門まもない越ヶ谷門人の山崎長右衛門・小泉市右衛門・町(松)山善兵衛に平田篤胤の著した「神代系図」の摺立代金の不足分六両の負担を依頼した手紙である。平田門人が篤胤の著書を入手する過程を示す貴重な書簡であるが、巻頭・巻末ともなく、中の部分のみという不備のものであるが、文面から推して、平田門人衆より山崎長右衛門に宛た手紙であることは間違いない。門人帳によれば長右衛門の入門は文化十三年、市右衛門・善兵衛の入門は文化十四年である。また「神代系図」の彫刻上りは夏目甕麿宛篤胤の書簡によれば文化十四年九月二十一日である。以上の点と書簡文中の「神代系図近々すり出し」等を照し合わせて見るに、この書簡は文化十四年九月十九日の差し出しであろうと考えられる。
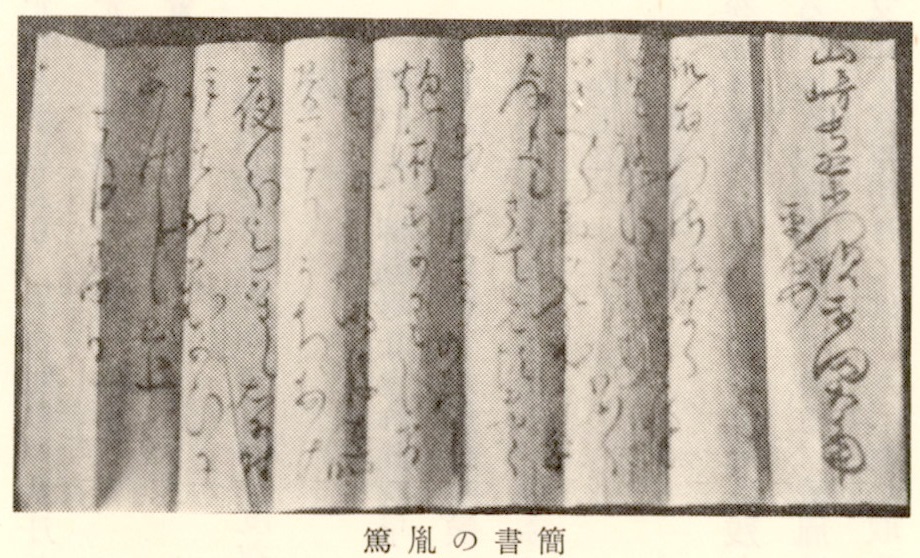
資料2
「(表書)長右衛門様 伊吹能屋より 用事」
追々冷気に相成候所いよ/\被成御揃御平定之由珍重奉存候、乍去此間ハ少々御風けの由いかゞ候や御床しく存候、我等ことも忰儀とかく同へんにて困り入申候、さてとや此方能様委細伊介より御きゝ可被下候、○本屋どもより(下欠)
この書簡も巻末は紛失していおり、文化十四年九月の発信であろうと思われるがあくまで推察である。理由は、書面中「追々冷気」とあることから九月と考え、年については「忰儀とかく内遍介」とあることから、篤胤の次男又五郎の死亡した文政元年九月二十四日(日記)以前のものであることは申すまでもないが、本屋云々の記事もあることから、また後述資料(4)の書簡等と合わせ考えるに、文政元年とするより、その前年の九月と解する方がよいと判断した。勿論文化十四年九月初日のものでないとすれば文政元年九月初旬の手紙である。
資料3
(上欠)御俗名を入れて記し度存候へ共、余りさし出しなること故、名乗斗りと御申故あの如く致し候事に御座候、
何れよく御勘考なされ此次早々のたよりに御申こし可被下候かし、
廿六日までに御さた無御座候へば相直し申候間左様御承知可被下候、
○しろざけありがたく、ゆふべおばあ様としてたべ誠によく出来申候、ありがたく存候、何も/\早々めて度、
かしこ
正月廿一日
巻頭は紛失しているが、末尾は残されているため正月廿一日であることは問題ないが、文化十五年であろうと推定するのは次の理由からである。篤胤は長右衛門から「玉真柱」摺立代として一五両を文化十四年十二月に借り、続いて文化十五年正月には二九〇両の取りきめで、古史成文と古史徴の彫刻代を借り出し、契約の日一月十日には門人平島伊助が二十両内金を持ち帰った(日記)。尚彫刻の始まったのは十五日である。篤胤は費用の提供者には出版の折序文の記載者として名前を記載し、その返礼としている。当然大金の出費者として、山崎長右衛門名で古史徴の序文が書かれ出版された。
しかし長右衛門としては、師の篤胤の書いた序文を自分で書いたようにすること、また著名な篤胤の書に一商人の長右衛門が名ばかりとはいえ、掲載されることに困惑したのは当然であった。
資料4
(上欠)参らせ、さて玉だすきを清書のとき篤利がかく云るは誠に然る事也とて古書を引て註し、御名を国中にかゝやかさんといふ下がまへにて致し候事に御座候、能々寸志を御勘考可給候、殊には春御出之節入御覧、かつわけを申候所御得意の事故、既に是を付て公儀へもさし出し有之、其上板もみな出来候上にてか様の御俗言何とも当惑に存候、学問にはをやづらに御座候へ共、内実は子の心得にて居候へば、親とたのむ貴老の外聞にかゝることは致し不[ ]目なし共は[ ]誠に(下欠)
本書簡は巻頭、巻末ともなく、中間のみであるが、書中の「御名を国中にかゝやかさん」とは前項で述べた通りのことであり、したがってこの手紙も、文化十五年一月のものであろうと推測する。
資料5
「(表書)山崎長右衛門様 ひらた」
此間は御早々奉存候、今以腕いたみにて扨々こまり入申候、漸々まづ是斗出来致し候付御目にかけ候、委細は伊助に申含メ候、よろしく御談合可被下候、何も早々、以上
二月九日
内容の判断しにくい手紙であるが、伊助を通して談合が進められていること、また「是斗出来」とは彫刻のことと考えられ、文化十五年二月九日の手紙であろう。なお、篤胤の「腕いたみ」は持病で、このことから年を推定するのは困難である。
資料6
(上欠)今以て残暑御座候所弥々御平安被成御出珍重奉存候、扨は今月三日に権平上候節二十両御渡し被下慥に落手仕候、乍去其節の如く申進じ候は盆前にはかならず御出これ有べく、其節御さし置可被下と存候故二十両と申上候事に御座候、然る所権平へとても盆前には御出無之よし御申こし(下欠)
八月三日権平が二十両借りて来たとの文面から、この書簡は文政元年八月の三日以降、十五日前と判断する。
資料7
「(表書)山崎ぬし ひらた 用事」
猶々信友より伊介に申含候事ども能々御きゝ可被下候、さて秘書一さつ上候、
日を追て冷気相募候へども御二人様無御替珍重々々、此方忰こと今以同扁にて扨々困り入申候、夫故校合はかどらず遺恨に存候へ共致しかたなく誠に御待遠に候半とぢれ度事に御座候、信友も番帰りにはいつも参候てすけ呉候へ共、第一の我等右の仕合せ故遅り候、其上少々やごとなき御方より一ノ巻に云々のことを認メ候方可然と御申有之、迚も之事と存じ信友など相談にて其事を書キ加に懸り候所、病人故はかどりかね候、其事信友よりも可申候、はた又我等こと十五日頃には参るべく存居候所忰儀又々うちかへし此節は絶食同様にて候程之事故伊介上候、なほ信友よりも可申候間よろしく御きゝとり可被下候、何も取込み早々如斯御座候、以上
九月二十日認ム ひらた
山崎ぬし
猶々御内様おかねさまにもよろしく奉願候 かしこ
この書簡は欠けた部分がなく、しかも書面に「忰儀又々うちかえし、此節は絶食同様にて候」とあり、先の資料(2)で記述のとおり、日記に見られる「九月廿四日今朝六時過又五郎殿死去」「廿六日今晩七ッ時出棺」と照合して、文政元年九月二十ば日の手紙であることは明確である。
資料8
(上欠)とれへも我等が志が通るまいかとあんしをり、御合点かいたら早々御返事可被下候、もし御都合相成候はば一夜どまりにて御出府被下候様に致し度候、さしたる用事も無れども板も出来そろひ又々何かの御咄しもしみ/゛\致し度候へば也、さて三十日ごろまでのたよりに七両ばかり御むし被下候(下欠)
資料9
(上欠)本は引はりたらずかへっていかゞ存ずべく候間、今五十部ばかりも御まし不被下候ては難渋之由達て申候付、不止事又々五十部之すり申付候、思召之所何とも恐入申候、委しき子細は伊介より御きゝ可被下候、但之左様ニ本屋ども望み候事ハ大吉事にて御座候、全く役所むきも無滞相すみ候故と存し誠に誠にありがたくひとへに御かげ故に御座候、此事に付てもくわしき訳は伊介御咄可中候、何も取込み早々申上候、かしく(下欠)
資料(8)と(9)の書簡は年月日とも確証といえる記載がないが、文政元年の手紙と推察する。理由は書中の「上刻・増刷り・借用金」と日記の「八月廿八日、古史成文、同徴共本屋仲間割判無滞相済候よし前川より申来」「十月十二日、伊助越谷より帰宅二九六両と取窮メ十三両受取皆済と申事」「十一月三日、成文・徴共九冊仕立上り」等々と見比べるとき、文政元年の書簡としてよい様に考えられるのである。
資料10
二白 寒気折角御加養被成候様奉存候、且又当日廿三日発会鈴屋大人霊祭古史開板之祝儀兼開筵仕候間是非御出席可被下候、末ながら其御地皆々様へよろしく御伝語可被下候、こなた渾家宜御祝儀申上候事に御座候、不尽
新春之御慶賀万里同風目出度申納候、先以被成御揃弥御安泰御迎春被成目出度奉存候、随而当方皆々無異加年仕候間御休慮可被下候、年始之御祝辞申上度如此御座候、恐惶謹言
正月十日 平田大角
山崎長右衛門様 篤胤(花押)
この書簡は文政二年正月十日のものであることは間違いないだろう。手紙に見られる「当月廿三日発会ノ鈴屋大人霊祭、古史開板之祝儀兼開筵仕候間是非御出席可被下候」と、文政二年一月廿三日の日記「大人御祭、入来人数等別帳に有之、以後三八ノ日御講読有之此節開題記彫刻申也」が全く一致するからである。
資料11
(上欠)少々つゞ御心よくとは存候へ共、両人誠に御あんじ申上候、何れ盆過キ早々両人之内まかり出相伺ひ可申候、誠に此節は家内大朝おき、ひるねなどいたし候ものなく午まの大はたらき故、とても盆すきならでは参上仕かね候、御ゆるし可被下候、何も用事而已早々、以上
七月十二日 大角
長右衛門様
本書簡は文政二年七月十二日と考えた。篤胤の三人目の夫人、おりせが越ヶ谷豆腐屋より輿入れしたのは文政元年十一月十八日、婚礼は十二月十二日である。したがって文面から推察して初の盆を迎えた年、いわゆる文政二年と推察したのである。
資料12
今日は寒く御座候へ共弥御平安奉寿候、此間中は大勢参り長逗留殊にめどいたみにて御苦労相かけ恐入候、帰りを案じ候所何ともなく段々よろしく、今日は大キにこゝろよく候間御あんじ下されまじく候、廿九日の御出を相待居申候、おりせも山々よろしく申事に御座候、いろ/\ありがたがり私よりくれ/\よく/\と申候、何も近日拝顔万々可申候、以上
十月廿六日 大角
婦翁君
資料13
「(表書)婦翁君 平田大角」
(上欠)いまだ上むきの御覧不相済候ゆえ当分つれて参りがたく候、其内是より御さた可申候、
○あつたねの御祓しん上いたし候、御しん/゛\可被成候、
○屋代様のしん上石ずり上申候、何も早々、以上
十一月十四日
資料(12)(13)の書簡は資料(11)でも触れたように、篤胤の新夫人おりせは長右衛門が親代りであることから宛名を婦翁君としている。婦翁君の宛名を使ったのはおりせ夫人の入輿後一年程で以後は使わなかったと思える。したがって資料(12)は文政二年十月廿六日、資料(13)を文政二年十一月十四日と判断する。
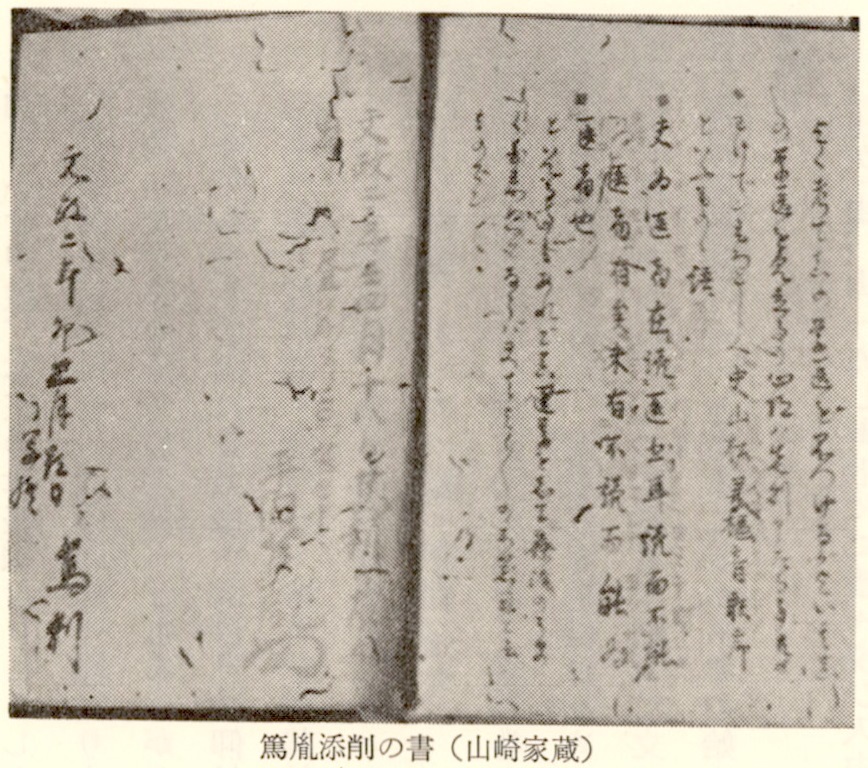
資料14
(上欠)あまり/\御苦労ばかり御きかせ申候故またうれしき事を御きかせ申候、本庄の津軽様よりこうしやくに出てくれろと申込み有之候、これ甚タ吉事のわけ御座候、
○公儀御目付のはきゝ内藤周防守様より古学の趣意をかき出し候様にとの事故認メ出し候、是大吉事に御座候、其後いまだ御沙汰は無之候へどもありがたき事に御座候、
○今年か来年の内に公方様へ御目見被仰付可申と彼是より取持申上候由も承り伝へ候、是も出来可申と存候、
○水戸様・越中様・はなハ・林大学様其外きゝ道の所々にても当時平田ほどの学者ハないとて開題記の評判誠によろしく御座候、弟子内でほめることはひいきにもあれど、右之所々にての評判は誠に天下のよき評判に候故うれしく存候、すべてヶ様に評判(下欠)
この書簡は内容的には豊富であるが、巻頭巻末共に欠け年月日とも推測は大変困難である。津軽侯より講釈の申し込みが記るされているが、篤胤が津軽侯に初めて講義をしたのは文政三年三月二十三日のことである。したがってこれ以前の手紙であるが、この前年まで遡って文政二年暮れのものであろうと思うのは、書面に「今年か来年の内に公方様へ御目見被仰付可」とあることから年の始めとは考えられないためである。
資料15
(上欠)由、山一ぬし御咄にて皆々悦ひ入申候、さて御かげにて五日に此方へ引移り何れも無事に喜ひ入申候、ありがたく/\、扨又前川の方よりの仕切之こと彼方にても例の本屋公事の事に付、大取込み昼夜寸暇なくいまだ取集め不申候由、何れ近日之内勘定有之筈に御座候、夫に付四五日以前より久八を日がへりに遣し可申と存居候へども、此節権平もはつも下り候故無人にて日々御たよりもあらばと(下欠)
資料16
(上欠)幸御伝声御願申候、何れ前川より勘定有之次第早々人上可申候間左様御承知可被下候、
○娘ことも嘸々御案じと存候、乍去此方ハ最早たんと物も入らずに済口に成りかゝり候上御安心可被下候、
○家はそとむきいたみ候へども一体は結構なるふしん故、骨は少しもいたみ不申誠によき家に御座候、扨々早く皆様に御目に懸度と日々咄し居候事に御座候、何も御目に懸り候節とあら/\如斯御座候、以上
三月十六日 大角
山崎君
資料17
(上欠)御病気段々よろしくとぞんじ候、二人とも参り度と申居候へども何かと取込み御無音申上候、前川方も例之出入今以片不申、夫故金納遅り申候、則彼方より之紙面入御覧候、来月十日前には無間違と申事に御座候左様思召可被下候、
○此廿三日に津軽様へ出候所、玉の真はしらよく/\御覧なされ委しき御問にて、昼九時より夜四時まで御咄し申上誠に御意に(下欠)
資料18
「(表書)長右衛門様 大角
要用 」
(上欠)我等年頃を申候所、其くらゐの年にてヶ様に学問の出来候といふハ只今には有まじ、何れ公儀にても比学問は御取り用へなさるべく、是也に御すて置キなされがたきとの事、かへす/\御ほめなされ追而御さた有べくとの事に御座候、一統誠にありがたがり大悦仕候、是も偏に御かげ故に御座候、なほ吉さう次第可申上候、色々様子よき事ども段々御座候也、
○上杉六郎の所より来り候、しやけハ誠にめづらしき大もの也とて遣し候事に御座候、此人よりの手紙又考の事に付き色々おもしろき御咄し御座候へども御目に懸り候節御咄可申候、此筆ろうそくを一丁〓え御遣し可被下候、どふぞ御かもじ様ちつと御暇を被下候はゞ御出なされ家を御覧可被成候、みんながほめ申候、何も用事而已早々、以上
三月廿八日 大角
山崎君 人々御中
資料(15)(16)(17)(18)の書簡何れも文政三年三月のものであることに違いあるまいと思う。資料(15)(16)に湯島の家へ引越したことが記されている。この件を他の資料でみると、「三月三日、湯島天神男坂下へ移り玉ふ(壑記一代)「三日、今日天神下へ引移る」(日記)との間に二日の差はあるとしても文政三年三月初旬に湯島へ引越したことは誤りなかろう。資料(17)に此廿三日に津軽侯に玉の真はしらの咄をした、とあるが、これは前の(14)で触れたとおり、日記の文政三年三月廿三日の「本所津軽様へ初て御出」と合致することから、資料(17)の書簡は三月下旬のものとして無理はあるまい。資料(18)については、上杉六郎のところから鮭が届いたこと、家を見てくれとの記事等から判断して、文政三年のものとした。家については上記のとおりであり、上杉六郎については門人帳に三月十六日入門とあり、越後国蒲原郡小関村の人であることが知れる。よって本手紙を文政三年三月廿八日と判断した。
資料19
「(表書)あぶらや
長右衛門ぬし ひらた」
不時候不相応之冷気御座候所弥〻御平安奉寿候、実や此間例之如くありがたく何か彼此の間違にて御夫婦様へ御心労相かけ恐入候、大蔵かたは委細に善兵衛ぬしへ相頼候間まつ御安心可被下候、
○さてのろしのことはいまだ日限相知不申、しれ次第御案内可申候、其内得貴意万〻可申、早々此間之御挨拶ながら如斯御座候、以上
六月廿五日
資料20
「(表書)山崎長右衛門様平田大角
平安 」
御あつさつよく御座候得共、御そろひなされいよ/\御さへり敷御入被成めて度存上候、さて先頃御やく申あけ置候のろし炮術あかりし間御出可被下候、明後廿六日昼よりうちあけ夜分迄御座候、右に付伊助御むかひにあけ申候、已上
七月廿四日
資料(19)(20)ともに、のろし砲術のことが記されている。鉄砲の人といえば国友藤兵衛能当(よしとう)のことであり、藤兵衛は鉄砲の産として知られる近江国坂田郡国友村の出身で、文政三年六月十日平田門人となった人である(門人帳)。よって、文政三年六月廿九日と同年七月廿四日の書簡であろうと思うのである。
資料21
「(表書)山崎ぬし ひらた」
此間は御早々奉存候、然は彼小僧また来り候、委細のわけは松安子より御きゝ可被下候、何も取込み早々、以上
十一月五日
今ばん松安子を御とめ被成候ていさいを御きゝ可被下候、かしく
書簡中に「彼小僧また来り候」とあるのは寅吉の入門寸前のことであろうと考える。日記に「十月十日、長崎屋へ天狗小僧を見に御出」とあり、門人帳には「十月十一日高山寅吉、後石井嘉津間篤任十四歳、屋代紹介入門」とあること等を照し合わせて、文政三年十月五日のものと考える。
資料22
「(表書)山崎長右衛門様 要用 平田大角」
(上欠)致させ候、参りきたのにはこまり入申候、山一とうふやへもよろしく御頼申候、おばァ様こと山一がくるの/\と日々御まち被成候間其由も御申可被下候、
○夏もの二十品もたせ上候、御六ヶ敷ながら御しまひおき被下、冬ものみな御こし可被下候、もしみなもてず候はゞ折瀬のはあとへまわしてもよろしくと申事に御座候、
○かたぎぬはかまはせうぞくのいためがみへ一しよにして御こし可被下と申事に御座候、いたむから
○はみがき上候是はよろしき品故、先日のよりは高き由に御座候、
○ひきわりを少〻御とらせ可被下候、くれぐれも善二郎は明白此男と一しよに御こし可被下候、以上
九月五日
紀州より手紙来り、とら吉こと誠に評判よろしき由申来り候、
書簡末尾に「紀州より手紙まいり、とら吉こと誠に評判よろしき由申来り候」とあることと、日記の「七月十六日、寅吉事紀州へ出立、石井伝右衛門同道」、「十月二十二日、寅吉紀州より帰る」の記事と突き合わせれば、この手紙が文政四年九月五日のものであることに疑の余地はない。
資料23
(上欠)様子は先日宅へ御出被成候由に候へば御聞可被下候、其後段々に京中之学者も帰伏いたし、殊に雲上には御評判よろしく、禁庭には公家衆方富小路様に御逢被成候とは我等事を御ほめ御尋被成由に御座候、富小路様とは真はしら序文を被遊被下候御公家様に御座候、是人は度々参上いたしいつも殊の外の御馳走にて難有きこと可申様なき事共に御座候、其外御公家様方にもあまた御目に懸り御懇命を蒙り、夫々御執持にて禁裡様・仙洞様両方へ書物のこらず献上になり、御ほうびの勅命の御書付も頂戴いたし古史成文の序文は富小路へ被仰付言語同断之ありがたき御序文なし下され候、是ら全く貴翁之御厚情故と日〻存出さぬ日もなく候、また吉田様の方も様子至極よろしく推つけ天下の神主の学師に可被仰付候間、其節は又〻可申上候、右等の事に付其外にも種々様々の危き日にもあひ難義も致し候事、今は書尽しかたく何れ帰宅後早〻罷出万々御咄し可申候、大かた帰りは十月に相成可申候間何分宿元之所よろしく御見立被下候様偏に御頼申候、山一へも此内よろしく御伝声可被下候、今日客来の所しひて数通の書状相認メ、余り退屈も致し候故是にてまづ投筆致し候、猶後便に可申入候、早々、以上
九月十三日 大角
長右衛門様 人々へ
この書簡は篤胤が京都より長右衛門に宛たものである。篤胤の上京は文政六年の日記に「七月廿二日御上京に付御出立」、「十一月十一日八ッ時御帰着」とある。申すまでもなく文政六年九月十三日のものである。
資料24
(上欠)入れて御ふき可被成候、
○十六日に山一又々御出之よし其節金子十両御もたせ御こし可被下候、右用事のみ早々、其内大宮がへりに又々参り万々可申述候、めで度、かしく
十月六日 あつたね
山崎ぬし
御もとへ
文中の「大宮がへりに又々参り万々可申述候」と、日記の文政七年「九月、岩井中務此頃来居る」と対比し、大宮の一の宮岩井中務との交流をもった頃、即ち文政七年十月六日の書簡と推察する。
資料25
「(表書)をりせどの 大角より」
(上欠)可被成候、
○どふぞ御かもじ様をかごにのせ申て御つれ可被成候、おばァ様とも相談いたし候、どふぞ御つれ可被成候、
○お千枝こと咋日よりこしけづき候由申来り、昨日御ばァ様御出なされ候、今日など出産かもしれ不申候、早々めで度、かしく
四月十一日 大角
折瀬どの
文中に「お千枝こと昨日よりこしけづき候」、「今日など出産かもしれ不申候」とあり、日記の文政九年「四月十二日、今暁丑ノ中刻過女子出産」と合致することから、本手紙が文政九年四月十一日のものと考えて、誤りないと思う。
資料26
(上欠)をり候ことに御座、なほおひ/\申べく候へどもあら/\今朝までの所を申上候、長右衛門様へ山〻よろしくおばァ様へも深く御あんじなきやうによろしく御頼み申上候、何も/\善兵衛どのたよりにつけ早々目出度、
かしく
六月二十二日
文の内容からみて、文政九月二十二日の書簡と思うが確証はない。
料資27
(上欠)其節取かへ可申候、御をさめ御大切に御もち可被成候、
〽ふた親をかきはときはにおはせとて、祝ひぞおくるよしの根のふえ
さて湯治の御あたりもこれなきよしうれしく、此内よろしく御伝へ可被下候、内のやつかいを尽くはらひ大安気に両人申合せ、出精たし候間御あんじ被下まじく候、此内山一おば様へ山々よろしく御願上候、以上
七月二日 あつたね
資料28
(上欠)昔よりの譬に九十九疋の鼻かけ猿が、鼻のまんぞくな一疋の猿を、かたはじやと云て笑ひ候とぞ、笑ふなら笑はしておいて可然候、古人の語にも上士は道を聞て大によろこぶ、下士は道をきいて大に笑ふ、笑はざればいまだ道とするにたらずとも申候、すべて道のことは人のとりとらぬにも、気に入る気に入らぬにもかゝはらず、思ふまに/\いひもし記しもすべき物ぞとは、先師の玉がつまにもかへす/\いひおかれ候間、決してそこらの御心遣ひなさるまじく候、ひつけう御文面を察し候所当時はなほいまだ跡式御ゆづりもなく、いまだ御隠居もなされず金銀の商売にて居られ候故、そこらからの御くんしやくと存候へども、是はこしがへの(下欠)
資料(27)(28)の書簡については、年次を推察する手掛りがなく、現段階では不詳である。
資料29
又申上候烏此の人至而心安キ人に御座候間其思召にて御あしらひ可被下候、以上返〻、丹事差たる事には無御座候間必々御案思被下まじく、御見廻等之儀は決而御用捨可被下候、為念申上置候、以上
追日寒気相募候得共御揃弥御壮健に可被成御入目出度御儀奉存候、次に当方一同息才に罷在候間乍憚御安慮可被下候、扨は先達而御咄し申候烏の啼やうを聞分る人福智忠兵衛と申仁、国元へ帰りがけ其御地通行いたし候由に付、書状相添参上いたさせ申候、御慰に御聞可被成候、ゆる/\御とめ置被成候ても宜敷御座候、将又子息も同道に御座候が此児殊の外絵の上手に御座候間、御好み御書せ御覧可被成候、
一其後は大に御無さた申上真平御免可被下候、何卒私壱人なり共上り度は存居候得共、短日ゆへ学事殊之外世話敷只々上り度心に存居候斗りに御座候、
一例年之通り稲穂御願申度奉存候、御地より御幸便御座候はゝ御事伝可被下、此方よりも其内には御願に差上可申、何レとも幸便次第奉希上候、
一丹事十月頃には緩々泊りに上り可申兼々存居候処、兎角積気少々起相勝し不申何分出兼申候而御無沙汰に相成申候、乍去何も御気遣被下候程の事には無御座候間此段は御気遣下間敷候、先は烏の人さし上候に付用事旁々一筆申上候、差急き乱略之書面御宥覧可被下候、以上
十一月廿五日 平田内蔵助
御両人様 御許に
尚々両親初一同宜申上旨申聞候、扨又御序も御座候はゝ豆腐屋へ宜奉希候、追々寒気強相成可申候間切角御厭可被下候、以上
この書簡は篤胤の養子平田鉄胤の書簡である。書面中「烏の啼やうを聞分人福地忠兵衛と申仁」ある。日記の「文政五年十月廿三日、烏の人福地忠兵衛来」、及び門人帳の文政五年「十月廿三日福地忠兵衛典則、下野国、屋代翁紹介」などと合致する。書面の意は新門人福地忠兵衛が下野の国元へ帰る途中越谷へ立寄らせるというものであることは容易に知れる。以上の事情から、文政五年十一月廿六日の手紙と判断する。
| 年 | 年・月・日 | 山崎長右衛門篤利(越谷門人) | 篤利年令 | 月・日 | 平田篤胤大角(平田家・気吹舎・越谷関係) | 篤胤年令 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一七六六 | 明和3年 | 粕壁宿山口万蔵の二男として生まれる。幼名美利・銀次郎 | |||||
| 一七七六 | 安永5年 | 10 | 8・24 | 秋田、大和田清兵衛の四男として生まれる | |||
| 一八〇〇 | 寛政12年 | 35 | 8・ | 平田藤兵衛の養子となる | 25 | ||
| 一八一五 | 文化12年 | 50 | 「諸国方言物類称呼などいうもの御覧被成候か…」(信友宛書簡、研P八二四) | ||||
| 一八一六 | 文化13年 | 不明 | 篤利・気吹舎門人となる。小島元吉紹介(門人帳) | 51 | 4・ | 篤胤、大角と号す | 41 |
| (9月24日、又五郎死)(壑一代) | |||||||
| 一八一七 | 文化14年 | 不明 | 「神代系図近々すり出し…六両不足用立てられたし…」(資1 手紙) | 52 | 9・21 | 「神代系図彫上り」(夏目甕磨宛書簡 研P八五〇) | 42 |
| 不明 | 小泉市右衛門・町(松)山善兵衛気吹舎入門、元吉紹介(門人帳) | 11・52 | 越ヶ谷へ行、伊助御供(日記) | ||||
| 12・20 | 玉真柱摺立代金、一五両貸す(資30借用文書) | 12・3 | 越ヶ谷より御帰り、上首尾のよし(日記) | ||||
| (霊能真柱、文化9年著) | |||||||
| 不明(秋9月頃) | 追々冷気ニ相成…忰内遍介…伊助より…本屋ども(資2 手紙) | ||||||
| 文化15年 | 1・10(文政元4・22日) | 古史成文・古史徴、彫刻代二九六両貸す(資31 借用文書) | 53 | 1・10 | 越ヶ谷より金二〇両受取り、此後度々御受取也(日記) | 43 | |
| 1・21 | 長右衛門の名出すかたよろし……(資3 手紙) | 1・15 | 古史彫刻初る(日記) | ||||
| 不明 | 御名を国中にかゝやかさん……(資4 手紙) | ||||||
| 3・4 | まづ是斗出来…委細は伊助に(資5 手紙) | ||||||
| 不明(8月頃) | 残暑…今月三日に権平に二〇両(資6 手紙) | 8・28 | 古史成文、同徴共本屋仲間割判無滞相済候よし前川より申来(日記) | ||||
| 9・20 | 忰絶食同様…仏道大意かなづけ信友にすけてもらう(資7 手紙) | 9・24 | 今朝六時過又五郎殿死去(日記) | ||||
| 10・12 | 伊助越谷より帰宅二九六両を取窮メ一三両受取皆済と申事(日記) | ||||||
| 不明 | 板も出来そろい…三〇日ごろまでの便に七両ばかり(資8 手紙) | 11・3 | 成文、徴共九冊仕立上り(日記) | ||||
| 不明 | 五〇部ばかりの増刷り…伊助お咄可申…(資9 手紙) | 11・18 | 織瀬平田家へ入輿(壑一代日記) | ||||
| 12・18 | 今晩御婚姻(日記) | ||||||
| 一八一九 | 文政2年 | 1・10 | 新春の慶賀…廿三日の発会…鈴屋大人霊祭…古史開校之祝儀…祝儀開・案内(資10 手紙) | 54 | 1・23 | 大人御祭、入来人数等別帳に有之、以後三八の日御講読有之此節開題記彫刻申也(日記) | 44 |
| 不明7・12 | 家内大はたらき…盆すぎならでは参上仕かね(資11 手紙) | ||||||
| 不明10・26 | 大勢参り長逗留…おりせも山々よろしく(資12 手紙) | ||||||
| 11・14 | あつたねの御祓志ん上…屋代様の志ん上石ずり上…(資13 手紙) | ||||||
| 不明 | 本庄津軽様よりこう志やく申込ミ内藤周防より古学の趣意とかき出し候… 今年か来年の内に公方様へ…評判よし(資18 手紙) |
||||||
| 一八二〇 | 文政3年 | 正月 | 古史二帙、一八冊皇太神宮神庫ニ奉納(資32 奉納書籍事) | 55 | 55 | ||
| 不明 | 五日に此方へ移り…前川仕切之こと…本屋公事の事ニ付大取込み昼夜寸暇なし(資14 手紙) | 3・3 | 湯島天神男坂下へ移り玉ふ(壑一代) | ||||
| 3・16 | 前川より勘定有之…家はそとむきいたみ候へども…(資15 手紙) | 3・5 | 今日天神下へ引移ろ(日記) | ||||
| 不明 | 前川方も例の出入今以片付不申…此廿三日ニ津軽様へ出候所玉の真柱…昼九時より夜四時まで御咄…(資16 手紙) | 3・16 | 上杉六郎入門(越後国蒲原郡小関村)(門人帳) | ||||
| 3・28 | ケ様に学問の出来候といふハ只今ニハ有まじ、…公儀にても御取り用へなさるべく…上杉六郎の所より来る志やけ家を御覧なされ候(資17 手紙) | 3・23 | 本所津軽様へ初て御出(日記) | ||||
| 6・29 | のろしのことはいまだ日限相知不申…(資19 手紙) | 6・10 | 国友藤兵衛能当(近江国郡国坊田友村)平田入門(門人帳) | ||||
| 7・24 | のろし炮術…明後26日昼よりうちあけ(資20 手紙) | 9・17 | 右史成文、徴蔵板の儀に付、出雲寺文二郎・前川六左衛門より申出たることあり、不束の次第に付、屋代翁より厳敷申談せられ、右書長事両人并に行事奥印の誤証文二通受取らる。右ハ先月廿日頃より追々掛合有ての事也(日記) | ||||
| 10・5 | 彼小僧また来り候…今ばん松安子をおとめ被成候(資21 手紙) | 10・16 | 国友藤兵衛、風炮もち来(日記) | ||||
| 10・10 | 長崎屋へ天狗小僧を見に御出(日記) | ||||||
| 10・11 | 高山寅吉 後石井嘉津間篤十四14才屋代紹介入門(門人帳) | ||||||
| 一八二一 | 文政4年 | 56 | 7・16 | 寅吉事紀州へ出立、石井伝右衛門同道なり(日記) | |||
| 10・22 | 寅吉紀州より帰る、中島丈助同道(日記) | ||||||
| 9・5 | 夏もの…かたぎぬ…はかま、はみがき、ひきわり少々山一へ なつめ…紀州より手紙 とら吉こと誠に評判よろし(資22 手紙) |
10・23 | 山谷せともの屋市兵衛死去(織瀬夫人の伯父)(日記) | ||||
| 一八二二 | 文政5年 | 11・26 | 烏の啼やうを聞分る人福地忠兵衛と申仁…書状相添 参上いたさせ…例年の通り稲穂御願(資29 手紙) |
57 | 10・23 | 烏の人福地忠兵衛来(日記) | 47 |
| 〃 | 福地忠兵衛典則 下野国屋代翁紹介入門(門人帳) | ||||||
| 一八二三 | 文政6年 | 9・13 | 京中之学者も帰伏いたし殊に雲上ニハ御評判よろしく 禁裡様仙洞様両方へ書物のこらず献上…(23手紙) |
58 | 3・26 | 新庄道雄、鈴屋大人敷島の御肖像持参(日記) | 48 |
| 7・22 | 御上京に付御出立(日記) | ||||||
| 11・9 | 八ツ時御帰着 宇右衛門、又兵衛御供(日記・12月2日出是香宛書簡) | ||||||
| (鉄胤養子の話し 壑一代) | |||||||
| 一八二四 | 文政7年 | 10・6 | 十六日に山一又々御出之よし其節金子一〇両御もたせ…大宮がへりに又々参り万々可申述候…(資24 手紙) | 59 | 49 | ||
| 1・15 | 鉄胤入家(日記) | ||||||
| 9・ | 岩井中務此頃来居る(日記) | ||||||
| 一八二五 | 文政8年 | 60 | 3・12 | 天気、越ヶ谷彦右衛門殿死去(日記) | 50 | ||
| 8・22 | 曇、父君母君越ヶ谷へ御出、竹来、大童子まきも御供なり(日記) | ||||||
| 8・25 | 晴、越ヶ谷より八ツ半頃御帰り(日記) | ||||||
| 10・23 | 越ヶ谷叔父様御出(日記) | ||||||
| 11・20 | 越ヶ谷長右衛門様御出(日記) | ||||||
| 一八二六 | 文政9年 | 61 | 1・10 | 晴風、武蔵越ヶ谷西川久二郎殿…今朝御成(日記) …越ヶ谷へ書状出す(日記) |
51 | ||
| 3・23 | 天気、…越ヶ谷より御出…(日記) | ||||||
| 3・25 | 曇、越ヶ谷をぢ様御帰り、内蔵勝五郎、勇太郎を連れ越ヶ谷へ行く(日記) | ||||||
| 3・26 | 雨、父君越ヶ谷へ御出(日記) | ||||||
| 4・11 | お千枝こと昨日よりこしけづき候…今日など生産かも志れ不申候(資25 手紙) | 3・28 | 天気、…父君御初我等越ヶ谷より帰ル(日記) | ||||
| 4・12 | 今暁丑ノ中刻過女子出産、十八日七夜祝、ふきと名く。二一日宮参り(日記) | ||||||
| 8・16 | 曇、今日越ヶ谷へ御出(日記) | ||||||
| 8・17 | 雨、勇太郎越ヶ谷より帰る(日記) | ||||||
| 8・12 | 天気、…今夜越谷より御帰り(日記) | ||||||
| 12・18 | 天気、越ヶ谷より稲来 重吉御使也(日日) | ||||||
| 一八二七 | 文政10年 | 62 | 2・16 | 曇雨小、越ヶ谷へ行(日記) | 52 | ||
| 2・19 | 晴、越ヶ谷より帰る(日記) | ||||||
| 閏6・21 | 天気、今暁越ヶ谷出立、大童子供なり(日記) | ||||||
| 6・23 | 晴、越ヶ谷より帰る(日記) | ||||||
| 7・4 | 天気、今朝越谷ヶへ行(日記) | ||||||
| 8・21 | 晴、越ヶ谷へ行(日記) | ||||||
| 8・22 | 晴、越ヶ谷より帰ル。御伝記の板、御様式の板持帰(日記) | ||||||
| 12・21 | 晴、越ヶ谷へ行(日記) | ||||||
| 12・23 | 晴、越ヶ谷より帰ル(日記) | ||||||
| 一八二八 | 文政11年 | 63 | 2・1 | 雨、越ヶ谷豆腐屋より御出(日記) | 53 | ||
| 2・26 | 天気、父君越ヶ谷へ御出(日記) | ||||||
| 2・28 | 天気、風、…父君越ヶ谷より御帰り(日記) | ||||||
| 3・26 | 曇、…昨日越ヶ谷より入来、今日帰り(日記) | ||||||
| 4・18 | 天気…越ヶ谷豆腐屋より御出(日記) | ||||||
| 4・28 | 曇、越ヶ谷へ書状…出す(日記) | ||||||
| 4・29 | 天気、善二郎の事に付駒吉を越ヶ谷へ遺す…(日記) | ||||||
| 5・1 | 曇、…越ヶ谷より善二郎の事ニ付庄左衛門来(日記) | ||||||
| 5・3 | …越ヶ谷より板木来(日記) | ||||||
| 5・20 | 天気…越ヶ谷油屋より御出 | ||||||
| 5・21 | 同、長右衛門殿帰り、夜に入内蔵助越後より帰る(日記) | ||||||
| 6・1 | 曇、越ヶ谷より庄左衛門来ル(日記) | ||||||
| 6・20 | 天気、越ヶ谷より重吉来…(日記) | ||||||
| 8・23 | 天気、越ヶ谷より御出…(日記) | ||||||
| 12・18 | 晴、越ヶ谷より重吉来(日記) | ||||||
| 12・22 | 晴、越ヶ谷へ行く(日記) | ||||||
| 12・23 | 晴、…五ツ前越ヶ谷より帰る…(日記) | ||||||
| 一八二九 | 文政12年 | 64 | 7・28 | 天気、…越ヶ谷老嫗御入来(日記) | 54 | ||
| 8・23 | 曇、母君越ヶ谷老嫗と御同道出立(日記) | ||||||
| 8・6 | 晴、越ヶ谷より正(庄)左衛門使に来る(日記) | ||||||
| 8・16 | 晴、暁六ツ前父君越ヶ谷へ御出立、三次郎御供、今夜婚儀あるに伝て也(日記) | ||||||
| 8・8 | 天気、越ヶ谷より御帰り…(日記) | ||||||
| 9・21 | 晴、越ヶ谷へ行く。市衛供也(日記) | ||||||
| 9・22 | 晴、夜越ヶ谷より帰る(日記) | ||||||
| 天保9年 | 6・19 | 山崎長右衛門没す | 73 | 63 | |||
| 天保12年 | 1・1 | 篤胤江戸払い。著述差留(壑一代) | 66 | ||||
| 1・12 | 秋田国元へ向い出立、草加に泊る(越ヶ谷を避ける→仁良川へ) | ||||||
| 天保13年 | 4・19 | こしがや姉様へだんごこしらへ上る(日記) | 67 | ||||
| 天保14年 | 閏9・11 | 秋田市外 旭川村大字手形字大沢に没す。墓立つ | 68 | ||||
| 9・14 | 広沢山に葬る | ||||||