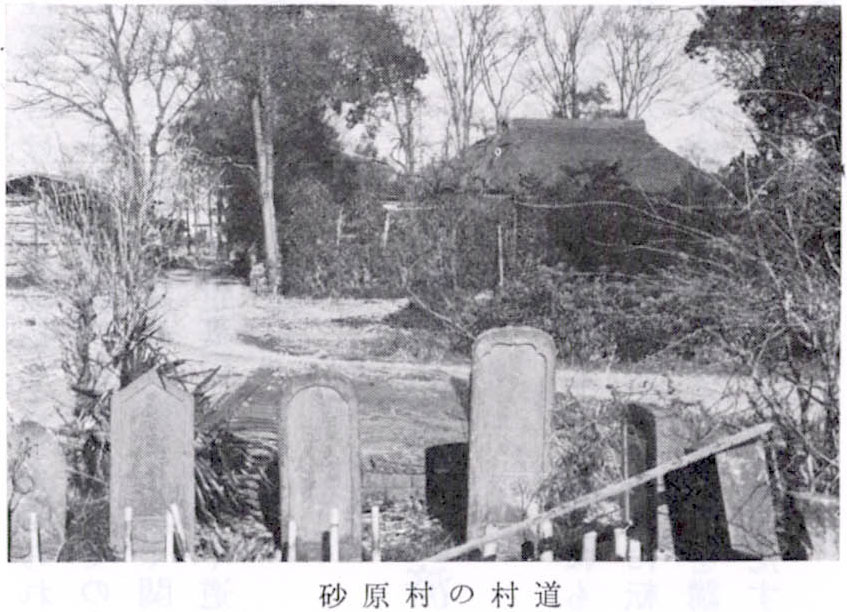自給自足経済を基本とした農村にも貨幣経済が浸透してくると、農家の経営も貨幣経済に対応した切り替えを迫られ、商品作物の栽培に転換させたり農間余業に活路を見出したり、あるいは小作地をふやして手作地を縮少するなどの措置を講じることも必要であった。ところがその方法がつかめず旧来の経営方法を踏襲したため、破綻をきたす農民も少なくなかった。ことに米作専業農家にその傾向が強かったようである。
安永二年(一七七三)、三月砂原村の百姓六左衛門は親から家督を引継ぎ当家の経営に専念することになった。このとき引継いだ生計費は銭三貫文余と米一五俵この代金五両三分余りであった。六左衛門はこの年、おそらく累積した借財の清算にあてるためとみられ、金三七両余りで所持地の一部を売却した。このほか収穫米五俵を金一九両余りで売却したので、当年の総収入は金六三両余りであった。
これに対し当年の支出は、借財の返済金が三〇両余り、奉公人給料の未払金や前渡金が二二両余り、小遣を含めた生計費が一七両余りで差し引き金九両余りの赤字となった。翌三年度も極度に家計を切りつめてみたが、日傭人の賃金や肥料代金が嵩み、金二一両余りの大幅な赤字を示した。翌四年度も米の売却代など金三〇両の収入に対し前年の繰越赤字などで諸経費を清算しないうち、すでに金三両余りの赤字を示した。
このため六左衛門は当主となって僅かに三年目で「このような収支勘定であるので私によるこの農家経営ではとても身上向が立ちゆきません」とて、隠居を申し出た。そして当家の跡式は親戚の子に譲り、将来自分の娘と結婚できるように取りはからっていただきたいと願っている。さらに六左衛門は妻を小曾川村の実家に帰すが「拙者家を出ても当家に出入り相成候様に、ひとえに願い上げ候」とて「わすれなみ、身はくもいに成りぬとも空行く月のめぐりあふまで」の歌を残して家を去っていった。
それでは果して六左衛門が無能であったのでこの結果を招いたのであろうかこれをみてみよう。
たとえば安永三年の収支をみると、米七二俵分の代金が金一九両三分余りであるのに対し、金一一両余りが奉公人や日傭人の賃金にあてられており、広大な手作地の経営は労働力給金のうえから困難な状況にあったことが知れる。また、六左衛門家の生計費も生産米の売却代に近い金一七両余りを示しており、それまで自給自足経済を原則とした農家の家計が貨幣経済の進行でいかに混乱していたかをうかがうことができる。
安永三年といえば、今から二〇〇余年前のことであるが、すでにこの頃の農家経済は大きな転換期にきており、生活様式の変化とともに階層の分化がはげしくなっていく境目であった。