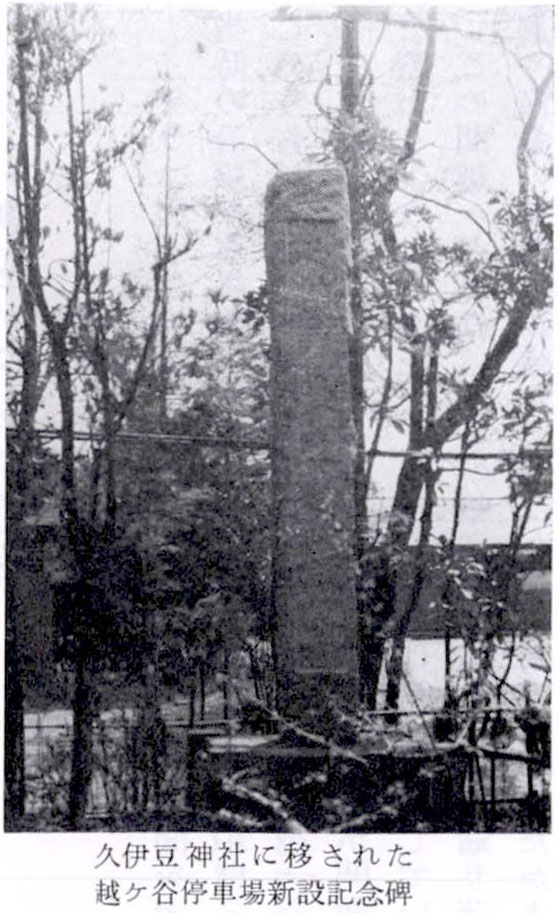イギリス製蒸気機関車が東武鉄道北千住・久喜間を走ったのは、明治三十二年八月のことであった。当時の沿線停車場は、北千住・西新井・越ヶ谷・粕壁(現春日部)・杉戸・久喜の六停車場であったが、このうち越ヶ谷停車場は現在の北越谷駅であり、越ヶ谷町には停車場が設けられなかった。その後同年十二年には、新田・蒲生・武里・和戸の四停車場が開業し、それぞれの駅近辺は飲食店や運送店の進出で賑わうようになったと、当時の新聞はこれを報じている。
この間越ヶ谷町は、貨物の輸送など主に綾瀬川通り蒲生の河岸場から舟運を利用していたが、町の発展や産業の振興は鉄道によるほかないとの要望がたかまり、大正八年五月、越ヶ谷町長を会長とした町民有志による「停車場新設期成同盟会」が結成され、積極的な誘致運動が展開された。こうして東武鉄道との交渉が進められたが、その結果相互協議による停車場開設要項が鉄道側から示された。
この要項の主なものは、
一、停車場の位置や設計は東武鉄道の定める所による。
二、越ヶ谷町は東武鉄道にこの経費として金一万六〇〇〇円を寄付する。
三、越ヶ谷町は東武鉄道と貨物輸送の契約を締結し、その保証の責任を負うものとする。
などとなっていた。そこで越ヶ谷町はとりあえず東武鉄道への寄付金調達として、日歩二銭の利息で中井銀行越ヶ谷支店から五〇〇〇円、永川貯蓄銀行越ヶ谷支店から五〇〇〇円、日進銀行越ヶ谷支店から六〇〇〇円の融資をうけ、同年五月二十六日鉄道側に納入した。この銀行借入金の返済は、主に同盟会員の寄付によって各銀行に振込まれたが、同年六月には一万二〇〇〇円が返済されている。このときの大口寄付者を示すと、一三一○円の会田善次郎を筆頭に、一〇九三円の山崎長右衛門、八一七円の小泉市右衛門、七一三円の白鳥喜四郎、五〇〇円の遠藤平吉、四九四円の仁科仁兵衛、四九三円の井橋太郎兵衛、三八〇円の会田吉五郎、同じく有滝政之助、三五六円の松本紋蔵、三四四円の会田太助、三一三円の有滝龍雄、三〇三円の鈴木源兵衛その他となっている。
このほか四号国道に通じる駅前道路の用地買収なども順調に進み、新停車場の建設や駅前通りの造成が急ピッチで進められた。かくて翌大正九年四月すべての工事は竣功し、同月十七日の開業日を期し停車場構内で盛大な祝賀会が挙行された。会場には緑のアーチが建てられて、まばゆいばかりの電灯装飾がほどこされ、商品陳列場などが設けられたが、この会場内で相撲大会や神楽なども挙行された。さらに町内では小学校生徒による旗行列や、青年団主催の仮装行列、それに提灯行列なども催されて終日町を挙げての賑わいをみせた。
かくて越ヶ谷町の新設駅は越ヶ谷停車場と称されたが、これにともない大沢町にあった越ヶ谷停車場は、武州大沢停車場と改称された。当時の越ヶ谷駅の年間乗降客(大正十年度)は二八万三千余人、この運賃は四万七千余円。貨物は発送着到合わせて二万余頓、この運賃は九五五〇円であり、武州大沢をはるかに上まわっていた。なお越ヶ谷町では越ヶ谷駅の新設を記念し金六七八円余で停車場新設記念碑を駅構内に建設したが、現在この記念碑は越ヶ谷久伊豆神社境内に移されている。