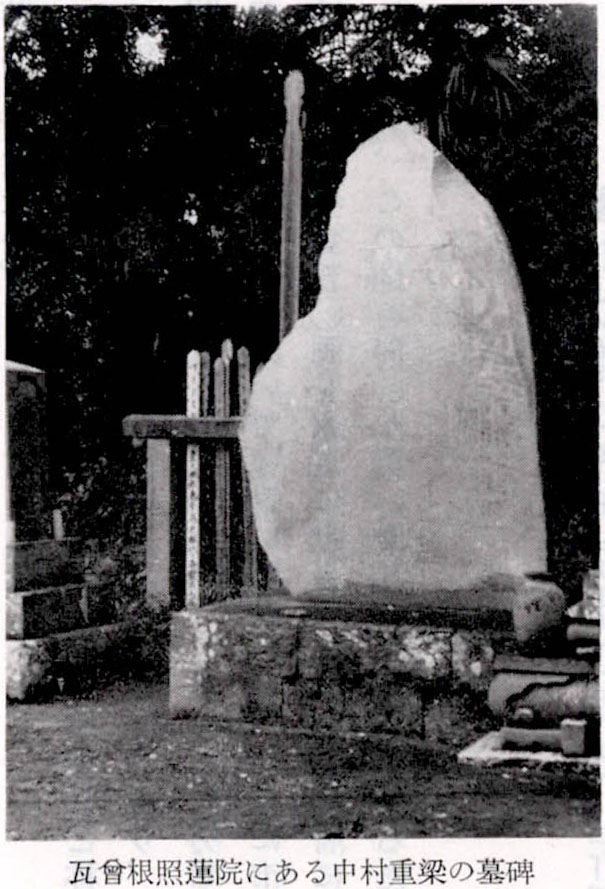朝晩めっきり冷えこみ、秋も酣(たけなわ)に入ったという感じの今日この頃である。この澄み渡った秋気に色を添える花といえば、まず菊の花があげられるが、丹誠こめた菊花の展示会などが催され、観覧者の眼を楽しませている。江戸時代においても同じく、富裕な人びとのなかには風流を好み、とくに菊づくりを楽しむ人も多かった。
その一人に瓦曾根村の中村彦左衛門重梁(しげはり)をあげることができる。重梁の生家は代々瓦曾根村の世襲名主を勤めた家柄であったが、重梁の代の明和八年(一七七一)、時の勘定奉行石谷備後守清昌より、将軍家に納める御膳細糯(ごぜんほそもち)御用取扱人に任ぜられ、天明四年(一七八四)閏正月苗字帯刀を許される家格が与えられた。この間安永五年(一七七六)十一月の越ヶ谷宿の大火や、天明三年信州浅間山噴火と冷害による大凶作などには、大量の米殻を放出して窮民の救済に務めるなど、人びとの信望はことに厚かった。
またその子重権は、御膳細糯御用精勤のかどにより、寛政十二年(一八〇〇)幕府より五人扶持(ふじ)を与えられた。父重梁は寛政八年六二歳で中村の家督を重権に譲り隠居の身となった。隠居した重梁は、葛西領寺島村(現墨田区東向島)に移り住み、その名も自休と称して菊の裁培に余生を送り、文化四年(一八〇七)十一月、享年八〇歳で没し瓦曾根村照蓮院に葬られた。法号を宜秋雲児自休居士と称す。
さてこの寺島村の別宅における重梁の菊づくりは当時評判であったとみえ、向島百花園(現墨田区東向島)の初代の園主佐原平兵衛が文政十一年(一八二八)の著「墨水遊覧誌」のなかで、菊の隠居と題し、次のような記事を載せている(文中現代かな文字で読み下した個所もある)。
この菊の隠居は文化ごろ、川原ぞね(瓦曾根)の何がし(中村重染)、この寺島村へ隠居して菊をつくり、たのしみていわく、陶淵明独菊を愛す、周茂叔のいわく、菊は花の隠逸(世の中を避ける)なるものといいしも、今の世は花壇に錦をかざりしごとく、年々珍花を植添へしも、今は名木奇岩を以て庭をつくり、また〝菊のや〟と号して会席料理屋を渡世とす、風流なる献立にて日々客来りてはんじょうす。石灯籠の名所なり。
これによると、重梁は菊を裁培するかたわら、風流な献立で当時繁昌した〝菊のや〟という会席料理屋を経営していたようである。そしてこの客人のなかには、自休居士墓碑銘に「退居葛西寺島村(中略)常陸府中候聞君高節、屢訪其家」とあるので、徳川御三家の水戸藩主もしばしば重梁の別宅〝菊のや〟を訪れていたようである。また天明期から寛政期にかけて活躍した浮世絵師鳥文斉細田栄之(えいし)が、重梁の郷里瓦曾根村の溜井を画いた(現市文化財)のも、あるいは〝菊のや〟が取り持った機縁であったかもしれない。現在この重梁別宅はなくなっており、その所在跡も訪ねる術はない。
なお重梁の妻は、恩間村名主渡辺左助の娘美久と称した。美久は重梁隠居後重梁とともに寺島の別宅に住んでいたが、重梁の没後髪をおろして尼となり、文政元年(一八一八)十二月享年八五歳で没した。この間美久は三男三女をもうけていたが、このうち次男幸次郎は江戸浅草福富町の豪商池田屋稲垣市兵衛の養子となり、家督を継いで家業に精勤した。ことに市兵衛は文化三年幕府に金五〇〇両を献金したのをはじめ、毎年金五〇両を永久に献金することを幕府に願いでていた。これは池田屋の屋敷地は借地であったため、この地を何とか買い取り町人身分になるための悲願による運動であったとも伝える。
(本間清利稿)