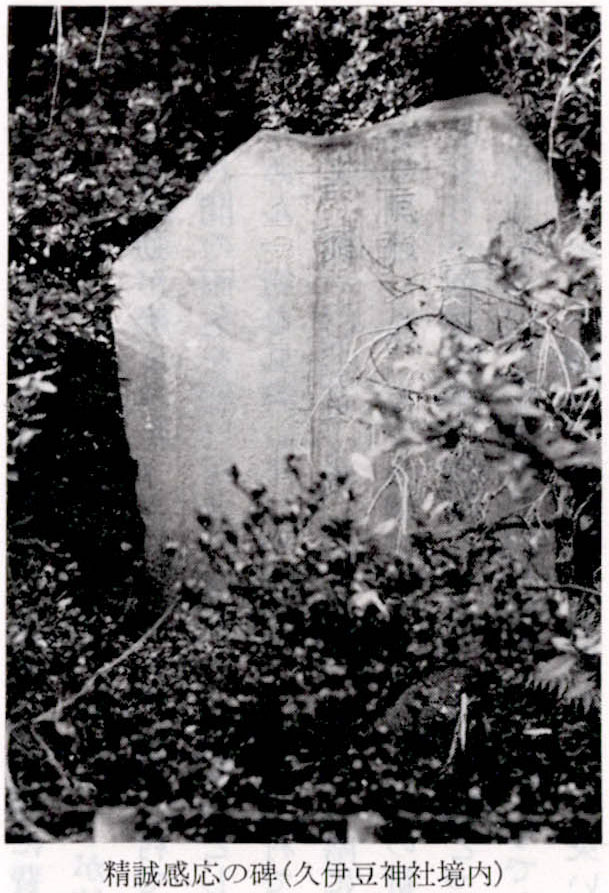六月も中旬頃から、一名〝五月雨(さみだれ)〟ともいわれる梅雨の季節に入り雨の日が多くなる。記録によると、大風雨をともなった台風の襲来により河川が氾濫して洪水になることが多かったが、梅雨の時の豪雨で水害をうけることも珍しくなかった。宝永元年(一七〇四)・宝暦七年(一七五七)・嘉永二年(一八四九)の関東洪水は、いずれも梅雨どきの大雨によるものである。
逆にこの梅雨どきに雨がないときは、田植えに差し支えたり、あるいは稲の植え付けができても田の水が干上がり旱魃(かんばつ)になる恐れがあった。このときは水車を使って川水を汲み入れたりしたが、いよいよのときは〝雨乞い〟と称し在地の寺社に祈願したり、上州板倉の雷電社などから〝御水〟を戴いてきて、その水を田面に撒(ま)いて降雨を祈った。
寛政六年(一七九四)六月、この年は稲の植え付けは終わったものの、連日日照りが続き、瓦曾根溜井の水が干上がり陸地と化すほどの状態で、稲田には地割れが生じ、稲は枯死(こし)寸前であった。このため西方村やその周辺村々は一同申し合わせ、大相模不動尊へ六月二十六日から七日間にわたる雨乞い祈禱を依頼した。こうして大相模不動で古式にそった雨乞い祈禱がはじまるや、人びとは村ごとに挑灯(とうとう)をかかげ鐘や太鼓で念仏を唱えながらそれぞれ行列をつくって不動尊境内につめかけた。
この七日間にわたる雨乞い祈禱中、これを伝え聞いた八条領村々はもとより、草加や越ヶ谷領の村々もこれに加わったので不動尊境内は毎日参詣人の群衆でうずまった。しかもこれら参詣人はいずれも身につける鉢巻下帯に新しい晒(さらし)木綿を用いたので、晒木綿はどの店でもまたたく間に品切れになったという。このときは満願日にあたる七日目の昼頃、一天俄(にわ)かにかき曇り雷をともなった大雨が降りだしたので、人びとは限りなく喜んだ。その後の天気も順調な経過をたどり、枯死寸前であった稲作は持ち直したが、この間村々からの奉納金がおびただしく不動尊に届けられた。これに対して不動尊でも雨乞い祈禱に費やした費用は金二〇両余に及んだという。
ついで文政四年(一八二一)、この年も五月から日照りが続き、田植えにも差し支える状態で、用水をめぐっての水論騒動が絶えなかった。このときも西方村では寛政六年の前例にならい、五月下旬大相模の不動尊に七日間の雨乞を願い出た。まずこの支度料として金五両を不動尊に納め、祈禱の中日には金一〇両とそうめん一箱を見舞いとして奉納した。西方村ではこの雨乞い費用を各人の経済力に応じ一軒あたり銭五〇文、銭一〇〇文、金二朱、金一分の四段階に分けて徴収したが間に合わず、その不足分は高割合の出金で調達した。ところがこのときは七日間の祈禱中には雨が降らず、後日になって雨があったので、日頃から不動尊を厚く信仰している村びとにとっては、はなはだ心残りであったという。
また文政九年(一八二六)五月も日照り続きで田植えもできない状態だったが、このとき越ヶ谷の町民は久伊豆明神に雨乞いを願い、祈禱の別当僧とともに災いを除くための大般若経を一心に転読し続けた。その精誠が神に通じたのか同月二十一日、忽ち雨が降りだした。これを機に町民有志八五人による中臣祓一万度奉誦が続けられた。これを記念して建てられたのが同神社境内にある「精誠感応」の碑である。
現在河川の上流には、貯水用のダムが幾重にも建設され、年間を通じて一定量の水が流されているので、洪水や用水不足の心配は幾分緩和されたが、昔は水による災害や用水の供給はそのときの天候によって左右されたため、ただ神仏に祈って晴雨の和順を願うほかなかったのである。
(本間清利稿)