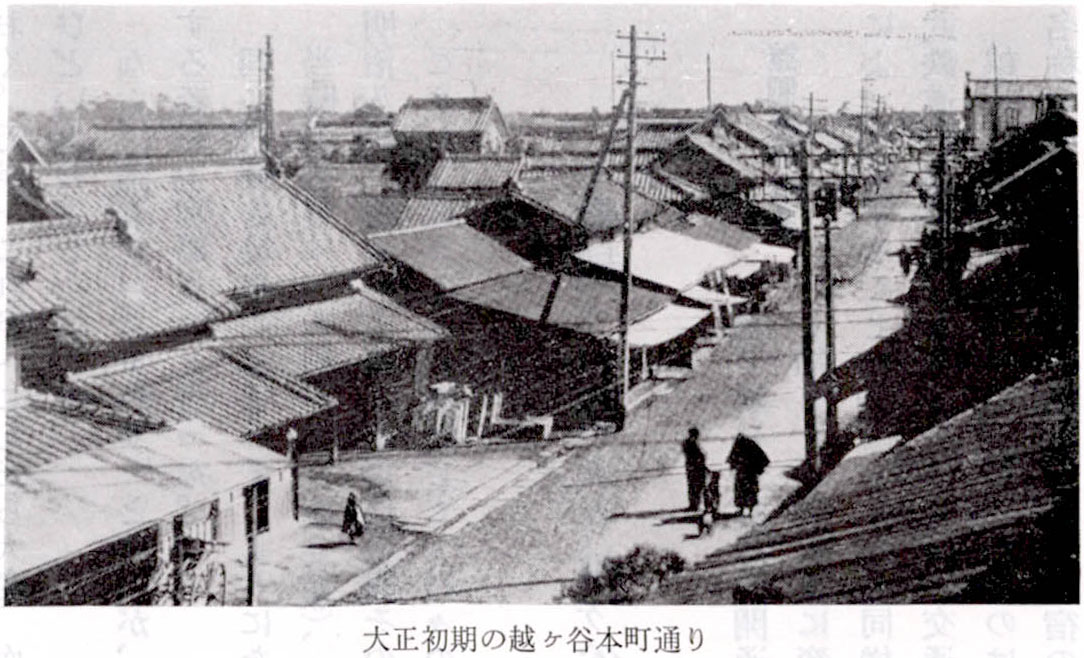宿駅制が廃止された明治五年前後の越ヶ谷町の情況はどうであったろうか。街道沿いに店家が集住し、並行して南北にのびているという景観は従来同様であった。ただ、戸数は幕末以来増加の傾向にあったようで、総戸数は五八〇戸余、うち自己名儀の屋敷を持つ者一二五名、借地人二五七名、店借人は一三三名であった。屋敷持は旧来からの町民で、借地、店借の人々は旧町民の分家か越ヶ谷近在の村々より幕末期に移り住んだ人びとである。このうち二〇〇人余は農業に従事し、農村的な小町場としての越ヶ谷の性格をよく示している。
一方、宿場町として固有な職業である旅籠屋渡世は四人しかおらず馬士稼に従事する者も二人にすぎない。これは越ヶ谷宿としての宿場の機能が、従来大沢町で担当されてきた面が強かったことと関係する。
また、時代の風潮を示す人力車稼が九人いた。人力車が発明され普及するのは明治三年以降、一般的な型は、西洋腰掛台に小車をとりつけて引き歩くもので、最初「人車」と称し、幅二尺余、長五尺五寸の小振りのものであった。明治四年より急速に使用されだし、越ヶ谷でもいち早く取り入れられたものと思われる。
このように宿場固有の職業は少なかったが、旅行者や近在の村びと相手の商売は種々あった。菓子屋二五軒、煙草屋六軒、髪結床七軒、湯屋四軒は煮売・居酒屋業の八軒ともども旅行者とも関係した商売であったろう。だが、石工、大工、左官、建具職などに従事する者三一人、箱、桶、樽屋職の者二〇人等は、宿場町的職業というよりは、地方小都市として近在諸村と関係した職業である。傘、下駄、足袋、ロウソク、鋳掛職など家庭生活の必需品を取り扱う職業も同様で、これらに従事する者二五人、糸綿、仕立物、紺屋、機屋など一八人とともに一般的な地方都市の性格を示すものである。質屋、小間物、呉服、大物渡世の者二〇人も同様であった。
越ヶ谷は東京近郊の農村地帯の町ということから、その特色をみるとすれば、荒物渡世二七軒、肥料商(干鰯、米糠)七軒、青物商二七軒、米穀販売三四軒などの商売がある。これら商家の資料が残されていないので経営内容は不明であるが、おそらく東京への米穀蔬菜の集散的役割りを果たすものであったと思われる。東京近郊の小市場的性格が職業面にも強く表われていたのである。
なお、特徴的な職業としては医師三人、筆学指南が二人おり、雛人形職も六人いる。この職人より農業へ転職した者も七人いた。また「布異国洗張」業が一軒あり、現代流に言えば一種のクリーニング業だと思われるが、当時としてはめずらしい職業であったろう。東京で西洋洗櫂をはじめた最初は明治元年四月頃という。これは越ヶ谷町において人力車稼とともに、職業のうえでいち早く新時代に対応した人であった。
(渡辺隆喜稿)