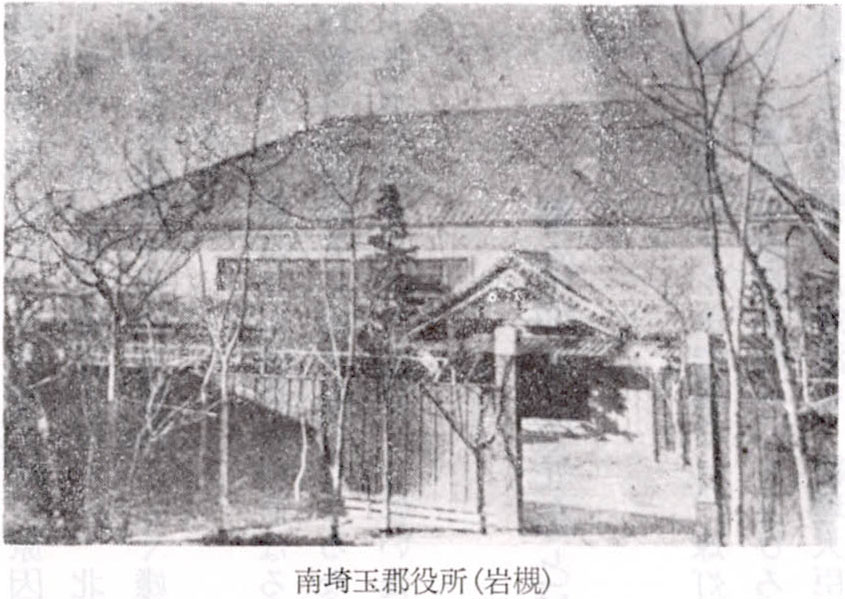町々は緑のアーチで飾られ、球灯は星の如く、山車もねり歩き、あたかも規模の大きな神田明神祭のような雑踏が東京の町々でくりひろげられていたころ、宮中では大元帥の軍服に身をかためた天皇が、皇祖皇宗に誓った憲法を、総理大臣に授与する式典があげられていた。ときに明治二十二年二月十一日、紀元節(神武天皇祭)の日のことである。国を肇(はじ)めた神武即位の日をえらび、この日の憲法勅語は、昔も今も、臣民の忠誠こそが建国のために必要であることを強調している。
この前日、南埼玉郡役所の指令に基づき、市域の町村役場は、発布の当日各戸に国旗を掲揚(けいよう)し、村の鎮守社に幟(のぼり)を立て酒食を供えるよう通達していた。まさに国家建立の天皇と、村々を創造した産土(うぶすな)神とが結びつけられ、祭事(まつりごと)と政治(まつりごと)とは同一の次元でとらえられていたのである。
全国的に好感をもって迎えられたこの憲法を、越谷地域の人々もまた、「開闢(かいびやく)以来ノ精典ト万国無双ノ祝詞」と歓迎している。そして「我朝ハ神国也、我民ハ神民也」として、多くの人びとは神民の義務こそは「皇恩ニ報ヒ」村内の平和を祈願するものと考えていた。その限り、神国思想に基づく村の鎮守への祈願は、国家永久の欽定(きんてい)憲法の理想実現に通じていたのである。
このような風潮のなかで、強大な君権または国権による、民権の侵害を心配した人びとがいなかったわけではない。自由民権運動のなかから民権、つまり基本的人権の尊厳に目覚めた一部の人びとは、この欽定憲法に批判的であった。
憲法発布の直後、大相模村大聖寺で次の如き会合がもたれている。
政治学講談会
演題 大日本帝国憲法
講師 宇川盛三郎君
主催 三郡倶楽部
一種の憲法研究会である。主催は北足立、北葛飾と南埼玉三郡の有志で、越ヶ谷・草加を中心に町村制度を研究していた人びとの政治結社である。越谷では井出庸造(出羽)、島根荘三(大沢)、武内周吉(越ヶ谷)らが発起人となり、川上参三郎(荻島)らも出席し何回か研究会が開かれ、初会には一三五人も参加者があったといわれている。講師はいずれも東京の改進党の有力者であったから、党の基本方針である地方自治の確立とイギリス的な民権主義(皇室は君臨すれど統治せず)を説いていたものと思われる。
このままゆけば、改進党の地盤となった筈の越谷地域が、この時の出席者の一人、川上参三郎を中心にして、翌年より大塚善兵衛・中村悦蔵らを幹部に急速に自由党に接近する。自由党こそかつては激しい民権論を展開していたのである。憲法発布はまた越谷にとって政治上の夜明けでもあった。
(渡辺隆喜稿)