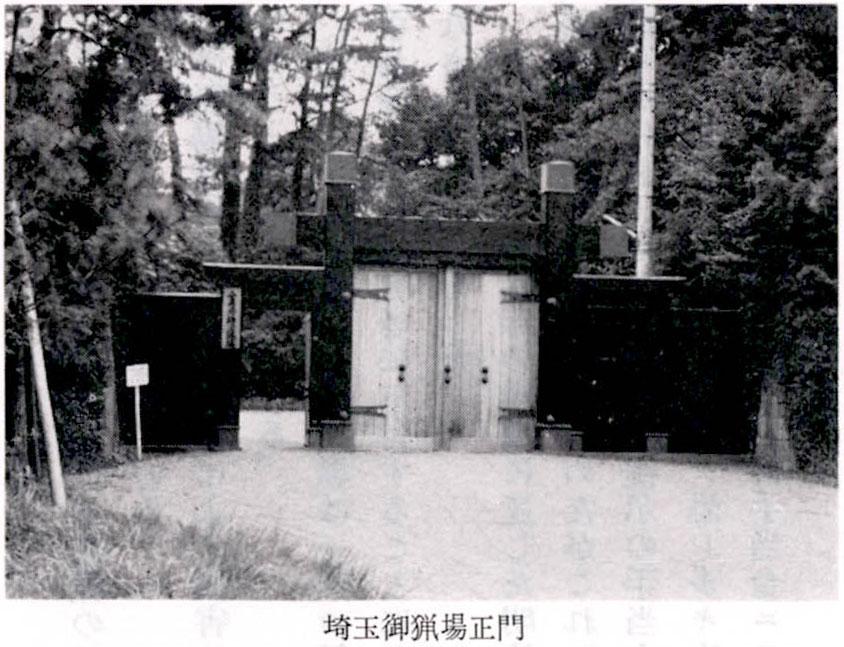御猟場内における鳥猟の禁止は繁殖した鳥類による農作物への被害が多くなるにおよんで問題となっている。
御猟場設定の当初、鳥類による損害は村人にも宮内省でもほとんど無視されていたが、明治二十年頃になると問題となってくる。
明治二十四年には、御猟場は一五ヵ年間の契約制となり、損害賠償の意味で、田畑一反当り金五厘の手当金を土地所有者に下付することになった。これらの条件の受諾も県令および郡長らの説得に応じてなされたものであった。
ところが、一五年の満期に達した明治三十九年には宮内省は手当金を増額して反当り一銭で再度御猟場指定を納得するように求めたがこれに対し、越谷地方の各町村は蒲生の中野文香、越ヶ谷の大塚善兵衛らを代表に選び、宮内省提示の手当金では不足であるとして国庫補助金を申請するにいたった。
「皇室ノ御猟場タルヲ以テ恐レ多キ次第ト存シ奉リ、御請候得共鳥類ノ繁殖年々夥(おびただ)シク随ッテ農作物ノ損害亦頗(すこぶ)ル多ク、到底右御手当金ニテハ害鳥駆除ノ設備モ作物損害ノ補償モ」できないというのである。
近年、土地に対する公租公課は加重され生活困窮の折柄、雁は立稲、乾稲および麦芽を荒した。また雉子は麦、豆および蕎麦を、鳩は豆類および蜀黍(もろこし)を、鷭(ばん)、鷺(さぎ)は早苗田を踏み乱し、ついばみ荒すなどの害がはなはだしかった。
そのため、この損害をめぐってどちらが負担するかで地主と小作人との争論も続出するありさまであったという。
越谷地方の各町村では、十五年間の契約替えを契機に、雀、鳩の自由捕獲の許可、農作物の損害や害鳥予防費として、土地一反歩につき金十銭を要求したのであった。
申請の具体的な経過は明らかでないが、明治三十九年五月十六日越ヶ谷町久伊豆神社境内の藤花園で、官民懇親大宴会が開かれている。これは、御猟場内の各町村長や土地所有者総代が発起人となり、県知事、本県選出衆議院議員、関係郡長、警察署長のほか主猟局長主猟官を招待したものである。
この趣旨は、国庫補助申請一件が増額で落着したことに対し、関係者に謝意を表するためであった。このことからみれば、当時は地元側の要求が一応受け入れられたものと思われる。
(渡辺隆喜稿)