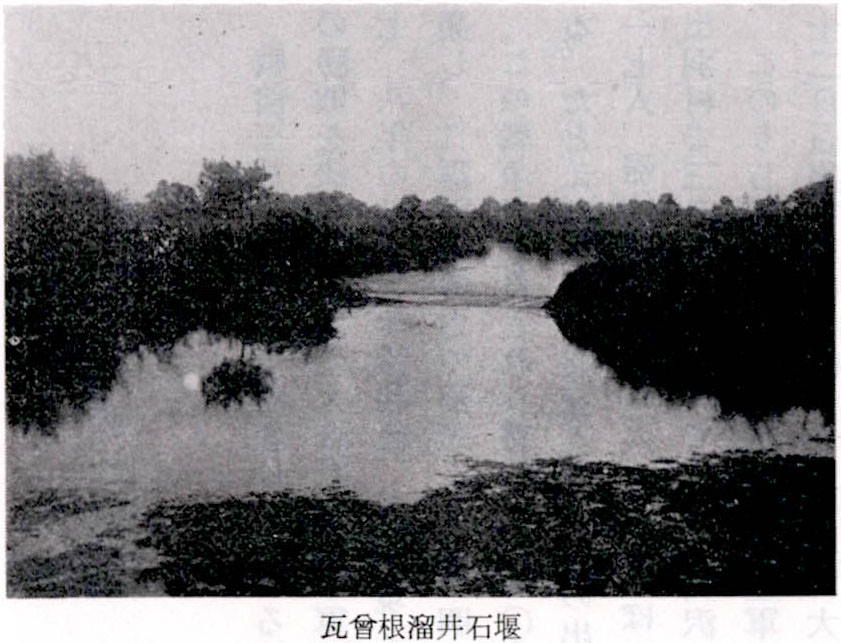水郷越谷が宣伝される時、最初に念頭に浮かぶのは、満々と水をたたえた葛西用水路や、越谷のシンボルともいうべき市役所の建物がそこに影を落としてそびえ立つ姿であろう。水に映し出された近代的建築の巨大な姿は、水の都にふさわしい新名所の一つになった観がある。水郷としての田園風景がすぐれていたことは、すでに越ヶ谷八景の一つに数えられていたことでも知られよう。
だが、鏡のような水面に映し出された風景の美しさとは裏腹に、水郷であるが故に水をめぐっての悩みは深く、かつ大きい。瓦曾根石堰竹流し事件はその典型であった。
葛西用水の水は、かつて石堰によって堰止められていたが、これは単に石堰上流の水を貯溜しているだけではない。用排水の調節をも受け持つこの堰は、江戸時代以来、その設計に独得の工夫がこらされてきた。
竹流し(竹洗い)とは、幅一〇間、高さ四尺五寸の石堰の表に、土を石堰の高さと等しく埋め立て、その土の上に土俵をならべ、生竹をもってこれを差し縫いしたものをいう。これは、ひとたび大水が出た場合は、自然に破壊されて排水機能を円滑にするもので、かつては年に二、三回も破壊されるのが普通であったという。ところが、竹流しの生竹を縫うのに、昔はやはり生竹かもしくは藤蔓(ふじづる)を使ったものが、鉄線が出来てからはこれで縫うようになり、以前より堅固になったため排水が困難になってきていた。
元来、大水の場合の排水には順序として、まず中堤の松圦を開いて排水し、間に合わない場合に石堰表の土俵(竹流し)を取り払い、なお排水しきれない時には石堰を破壊するか新五兵衛堤を決潰することになっていた。
大正二年八月、大雨による出水に際し、瓦曾根溜井管理者である南埼玉郡長が、この石堰上の土俵の取り払いを命じなかったことから、上流各町村に浸水被害が生じて問題が表面化した。
同月二十八日、郡長の石堰巡視に際し、越ヶ谷・大沢両町長は土俵取り払いの請求をしたが、回答がなかったので、帰庁した郡長を再度呼び出して現地の再検分をさせるなど強硬に談判した。結局、中堤の竹草を刈り払って水行をよくするよう指示されたのみで、解決にいたらなかった。このため増水をみかねた大塚越ヶ谷町長は、率先して新五兵衛堤切崩しを図ろうとしたため、ついに東小林と越ヶ谷地区住民の対決に発展し、幸い大事にはいたらなかったもののたいへんな騒ぎであった。
この直後、越ヶ谷・出羽など上流三五ヵ町村長は郡役所に押しかけ、石堰上部の竹流し工事には鉄線や木材を使わぬよう申し入れているが、この事件は明治三十五年の竹流し事件とともに越谷近代史上の大事件の一つであった。
(渡辺隆喜稿)