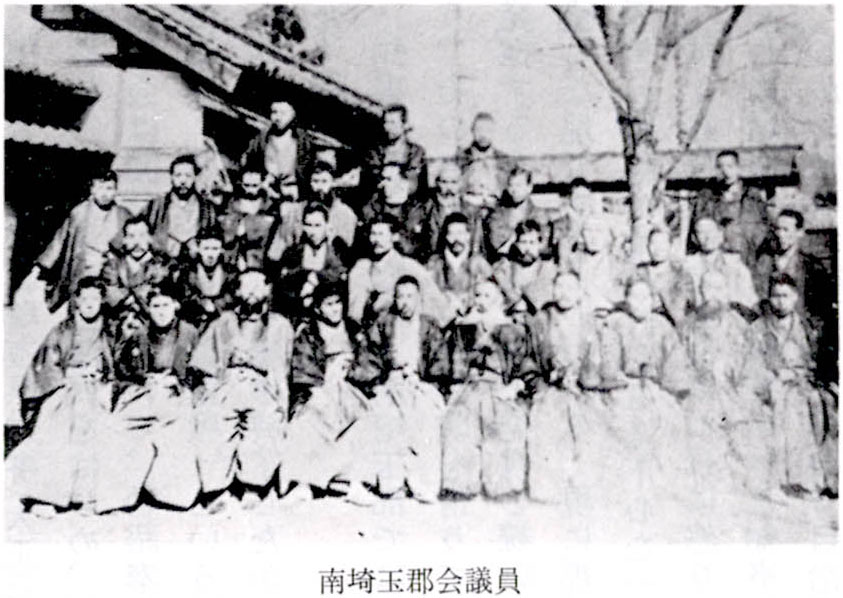大正三年十一月一日、越ヶ谷町尋常小学校校堂で、南埼玉郡教育会の第一五回総会が開催された。
出席者は昌谷彰埼玉県知事(大正三年六月九日任官、同五年十月十三日樺太庁長官に転出)、水谷南埼玉郡長、増林村の今井晃県会議員をはじめ、郡下町村の教員約四百名であった。
総会は開会の辞についで、勅語奉読、会務会計報告、表彰式、知事の「訓示的演説」、伊豆陸軍少将の講演「乃木将軍と要塞戦」という順序で進み、午後四時に散会した。
約六時間の総会も無事終了したかにみえたが、昌谷知事の「訓示的演説」は越ヶ谷町民同志会員をいたく憤激せしめた。
知事の演説内容は「南埼玉郡ではないが、ある村では約千人以上の生徒をもつ尋常高等小学校があり、その教場は二つの寺院を借りて間に合わせている。これは村内が統一しておらず、互に小字根性を発揮するためである」と発言し続いて南埼玉郡の情況に及び、その中で「従来同郡は郡長の排斥運動が盛んな地であるといわれる。現に郡長の弾劾(だんがい)運動が起りつつあると聞くが、かくの如きは先帝陸下(明治天皇)の勅語に現われたる上下心を一にしの聖旨にもとるものである……」と演説した。
越ヶ谷町民同志会員はこれに怒り、昼食休みに「上下心を一にしてというのは、無能不埓の郡長でもこれに屈服せよとの精神か」と知事に抗議の面会を申し込んだがこれは拒絶された。
しかし知事が教育会の総会で自治運動を攻撃するのは失言であるとの非難の声があがった。
後日、記者がこの演説問題につき知事の答弁を求めたところ、知事は、越ヶ谷町民は教育の根本を忘れており、しかも郡長の排斥、弾劾するがごときは不穏当である。だが町の理事者が理性的に町村制の運用を期すのは、賞するに余りあるとの曖昧(あいまい)の答弁をしていた。
この知事の失言事件は、日露戦争後の日本が欧米列強に伍す国力をつけようとし、国民の合意と統合を求めながらも、その実際の場である町村においては自治運動をかえっておさえるという、地方官と政府の矛盾した姿勢をはしなくもあらわしてしまったものである。
当時、越ヶ谷町は戸数割税(町税)の成績が悪いため、均一賦課方式をやめ、大正元年から不均一課税を実施していた。その後県税にもこの賦課方式をとろうとしたが、これが郡長、知事の段階で不許可となり、紛擾(ふんじよう)中であった(越ヶ谷町訴願事件)。
越ヶ谷町民同志会とは、大正二年十二月三日会員百八十名で結成され、役員には小泉市右衛門、山崎恭助等が選ばれていた。
この「知事失言」事件への町民の反応には、当時における越ヶ谷町民の自治意識への高揚がうかがえる。
(小川信雄稿)