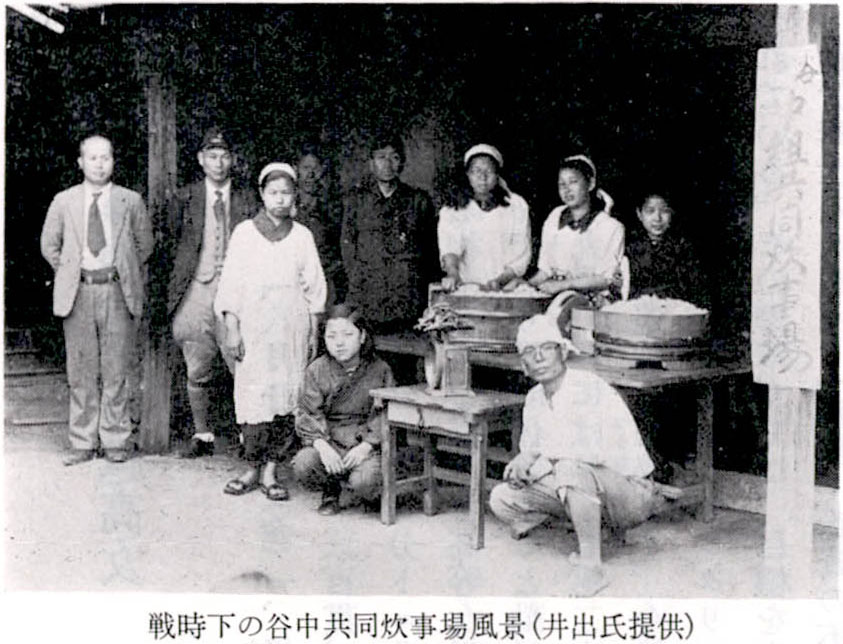昭和二十年八月十五日の太平洋戦争終結から今年で三十四年目を迎える。戦中から戦後にかけての生活物資の欠乏から、耐乏生活の労苦を経験してきた人びとは今でも少なくない。ことに戦前は軍備の拡張と臨戦体制の確立をめざした政府が、一億の国民を戦争国策に結集させるため、昭和十三年四月「国民総動員法」を発令、同時に国民の耐乏生活を強要した国民精神総動員運動を広く展開させた。
次いで具体的な戦争協力体制の推進を目標に同十五年十月、市町村や町内会、部落会などの自治機関を包みこんでの上意下達を主眼とした大政翼賛会を発足させ、強力な全国的組織機構のもとに国民の自由な言論を封じた。こうして国内の戦時体制を固(かた)めた政府は、翌十六年十二月ハワイの奇襲攻撃を機会に太平洋戦争に突入していった。
以来「自粛と自省」「勤労と増産」「滅私(めつし)奉公」あるいは「ほしがりません勝つまでは」などの標語が掲げられ国民の要望や意見はいずれも聖戦の名のもとに封じられたが、人びとも戦時下ではこれが当然と思うようになった。だからといって人びとは日常生活に対する戦時施策に関し、その不満や不合理を全く感じていなかったわけではない。これに表だって抵抗できなかっただけである。
昭和十八年三月、大政翼賛会埼玉県支部推進員による現地調査の結果をまとめた『現地に聞く』という報告書がだされたが、この人びとの不満を表現したものの主なものを掲げると、次の通りである。
(一)配給される日用品などの容器は、全て強制的に回収されるが、農民が供出した米、麦、藷などの空俵は返戻されない。
(二)農村にも時には魚類の配給があってもよい。
(三)我々が常会の席上で「必ず再供出はさせないから、できるだけ供出してくれ」と叫んでも「だまされるものか」という空気が強い。一億一心戦争遂行にまい進しなければならないとき、政治家と国民の間がもっとしっくりしないものか。
(四)供米を促進させるためにも米価は何とかならないか。米一俵と足袋一〇足と同じ価格とは、涙の出る話である。
(五)我が村の供米成績が悪いのは、一、二の不良組合がいるからである。駅やバス停で一、二升のやみ米を持つ者の取り締まりはやさしいが、大口の横流しをしている不良組合を取り締ることはむづかしいとみえる。
(六)工場徴用などで三里以上の距離にある大工場に通勤する者が多いが、皆その顔色はひどく悪い。朝五時に家を出て夜九時に帰るというような遠距離通勤者に対し善処を要望したい。
(七)浴場業者は組合のとりきめといい、三十分を超過する入場者の入場を断っている。子持ちの者は三十分ではどうしようもない。入浴によって心身を安めようとする庶民階級にとって困った問題である。
等々、戦時下のこととて現地の声はきわめて控えめのつつましい不満の表現であったが、不合理や不公平な事柄に対する当時の人びとのやりきれない心情を読みとることができる。
これらは戦時と平時の社会的条件、さらに個々の事例などで現在と大きな違いはあるものの、何時の世にも共通した問題が含まれているとみられよう。要するに当時の人びととて耐乏生活そのものを問題としていたわけではない。不公平や不合理に、いきどおりを感じていたもので、本質的には現在でも共通する問題でもある。
ことにオイル事情の悪化や水飢饉が懸念されている現今耐乏生活そのものはしかたないとしても、むしろ人びとはその不合理や不公平の是正を望むであろう。
(本間清利稿)