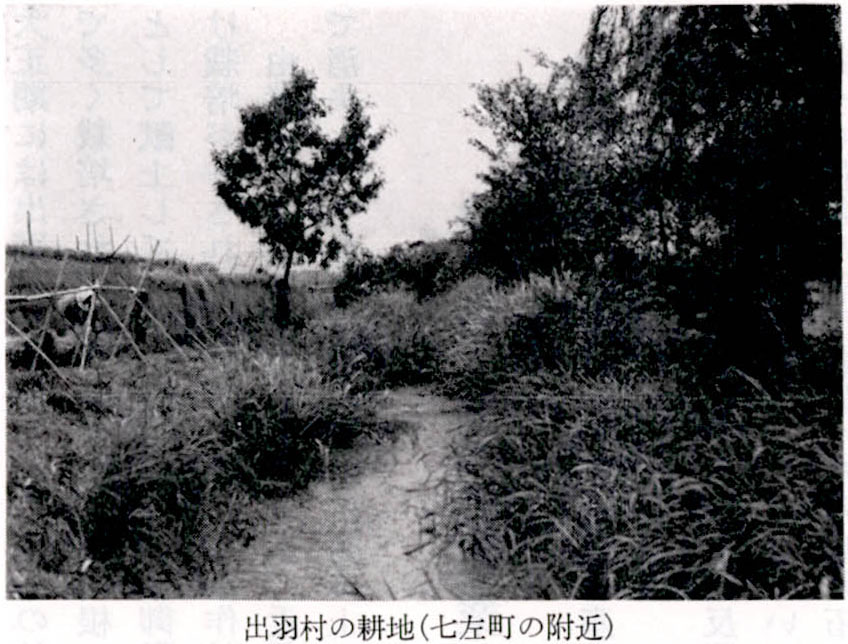数年前、二、三の新聞にとりあげられたのでご記憶の方もおられるであろうか。江戸時代以来、良質米として知られる武州越ヶ谷米のなかでも有名な太郎兵衛糯のことを。
もち肌の美しさ、腰の強さ、舌ざわりの良さ、味の良いことにかけては天下一の品種として長くもてはやされ、大正初期より昭和のはじめにかけて改良された太郎兵衛糯埼一号は、埼玉県奨励品種として名実ともに日本一の品種となったのである。戦時中の食糧増産による質から量への転換は、そのまま今日の作付状況にも反映し、五十年度市域の作付糯米は、約七六%が多収量品種の埼玉糯一〇号となっている。その他の二割もコトブキ糯、なおざね糯である。現在、太郎兵衛糯は出羽地区の二、三軒の農家で自家用に、細々と栽培されているにすぎない。
ところで、この太郎兵衛糯は越ヶ谷糯の一種である。越ヶ谷を中心に二里四方の強埴土に栽培された糯米を通称「越ヶ谷糯」といった。明治前期の越ヶ谷糯は六種類あり、そのうち第一位は太郎兵衛糯、第二はハヤリ太郎糯、第三を御膳糯と称し、このほか飯沼糯、白髪糯、源蔵糯などがある。後期には改良されて明治太郎兵衛糯、玉糯なども栽培されている。
明治二十年ごろ、御膳糯以上の三種は平年作で一反歩当り一石七斗ないし二石一斗の収穫であったが、これは硬米はもちろん他の三種の糯米より収量が少ない。良質にして高価にもかかわらず、この収量の少なさ、病虫害に弱いこと、長稈で倒れやすいことなどが今日の運命をもたらすことになっている。
越ヶ谷糯のうち、もっとも有名な品種は太郎兵衛糯と御膳糯である。太郎兵衛糯は江戸時代初期、四丁野村の名主会田太郎兵衛により早稲糯のなかから改良されたものといわれ、明治・大正期には出羽村より何回か皇室への献納も行われている。御膳糯は大相模地域では太郎兵衛糯についで多く栽培され、江戸時代には瓦曾根の中村彦左衛門家が、毎年上米を精選して将軍家の正月用の餅料として献上していた。とくにこれを御膳細糯といい、この細糯のみは御止め米として中村家を通じてだけ栽培が許されており、他のものが作付けすることはできなかったという。
由緒ある糯米の産地越谷はいま、近郊都市として宅地化の急速に進むなかで、糯米のみならず水田まで消失しつつある。越ヶ谷糯は歴史上の銘柄に終わるのであろうか。
(渡辺隆喜稿)