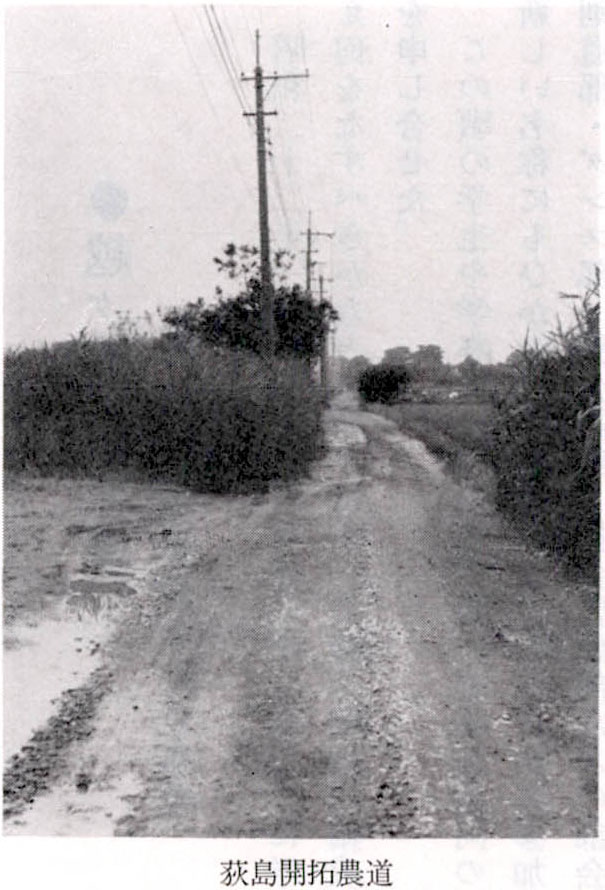埼玉県における戦後の開拓地は生産力の低い洪積台地と、廃川、廃堤等の肥よくな沖積地とに分布する。
沖積地の開拓は、附近の農家の増反用として進められ、旧軍用地や平地林を利用した洪積台地の開拓が、入植開拓により集落を形成していった。
従って荻島の飛行場跡への入植開拓は、沖積地における唯一の開拓地ということになる。
洪積台地での入植生活は、土壌改良と干害、風触害に対する悪戦苦闘の歴史であった。
一方、荻島の開拓地への入植者は比較的めぐまれた土壌と一・五五ヘクタールの耕地規模(洪積台地でさえ一・三ヘクタール平均)によって、順調な発展をとげてきた。
過去、洪積台地の開拓地が、全体の二六%の耕地を失い、入植者の二一%の離脱農家を出してきたのに、荻島の開拓地では、三%の耕地減少と離脱農家ゼロの実績を示している。
現在、一八戸の農家(越谷市一二戸、岩槻市六戸)が二五ヘクタールの田と、三ヘクタールの畑を耕作しているが、その大部分は、専業または一種兼業である。
開拓農家は、食管制度に保護され、経営的にも経済的にも安定した米作を主体に、集約部門の畜産を組み合わせた、日本農業としては、理想的な姿に近い作目編成をとっている。
当然、農業所得は高く、昭和四十四年埼玉県農地開拓課の開拓地営農実績調査によれば、県内全開拓地のうちで第四位を占(し)めている。しかも都市近郊農村のため兼業機会にも恵まれ、農外所得も大きい結果、農家総所得では、児玉の大沢開拓地についで第二位となっている。
荻島の開拓地に限らず、一般に開拓地は経営規模、形態、作目等が類似し、さらに、大型圃場の集中所有開拓地=開拓農家の所有という共通性をもっている。
これらの類似、共通性が、都市化の米価進展と制度の変更に直面して、今後、どのような意味をもつことになるだろうか。注目されるところである。
(新井鎮久稿)
(付記) 現在この開拓地の大部分は県立しらこばと水上公園に開発された。