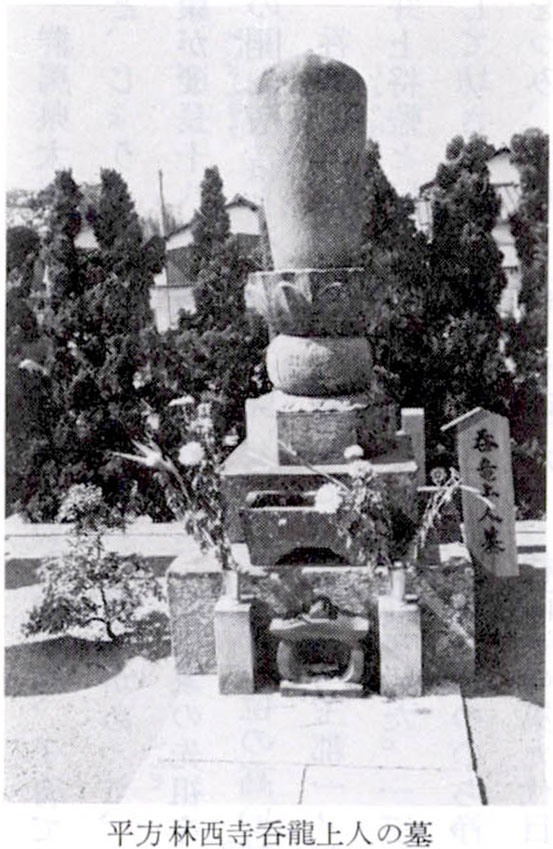群馬県太田市金山の大光院(だいこういん)というお寺は、子育て呑龍さんといわれ、子供を呑龍さんにあずけると、じょうぶにかしこく育つという信仰があって、たいそう評判のお寺でした。呑龍とは、徳川家康が慶長十八年(一六一三)という年に、徳川家の先祖(せんぞ)をおまつりするために、とくべつに建てた大光院の開山僧(かいざんそう)(はじめて寺院を開いた僧)となった位の高い坊(ぼう)さんです。
呑龍は、天文十一年(一五四二)に、武蔵国埼玉郡一ノ割村(現春日部市)の、岩槻太田氏の家臣であった井上将監(しょうげん)という人の次男として生まれました。一三歳のとき平方(現越谷市)の浄土宗(じょうどしゅう)林西寺に入寺して坊さんとなり勉強にはげみました。そののち浄土宗の本山江戸増上寺(ぞうじょうじ)の観智国師(かんちこくし)のもとで修業をつみ、天正十二年(一五八四)から、林西寺の第九代目の住職を勤(つと)めました。
天正十八年、それまで関東を支配していた小田原北条氏にかわって関東に入った徳川家康は、翌十九年十一月、関東の主な寺社に寺社領(じしゃりょう)(寺社の領地)を与(あた)えました。このとき林西寺には高二五石(こく)の寺領が与えられましたが、すぐれた僧で評判の呑龍には、別に高二五石の学問料が与えられました。この間、呑龍は、貧(まず)しい家の子供たちを集めて学問を教えたり、食事を与えたりして面倒(めんどう)をみていましたので、情(なさけ)ぶかい坊さんとしてみんなからしたわれていました。
またある年のこと、この年は春さきから雨が降らなかったので、川の水や井戸水も枯(か)れてしまい、田や畑が地割れして農作物が枯(か)れそうになったばかりか、飲料水にもさしつかえる状態(じょうたい)が続きました。人びとはたいそう困ってしまい、あちこちの神社に雨乞(あまごい)の祈願(きがん)を続けましたが、雨は一こうに降りそうもありませんでした。そこで人びとは呑龍に救(すく)いを求め、雨乞のお祈(いの)りを願いました。呑龍は神仏にお祈りすることは好ましいことではないが、人びとの悲しみを見るにしのびないといい、龍神(りゅうじん)の森で念仏(ねんぶつ)祈願を行いました。
するとこの念仏祈願中、一天にわかにかき曇り、大雨が降りだしました。この雨はそのまま三日間にわたって降り続きましたので、枯れそうになった田畑の作物は一ぺんに生き返りました。それからは、呑龍に対する人びとの尊敬(そんけい)は、ますます深くなったといいます。
そのご呑龍は、慶長五年(一六〇〇)一六年間も住職(じゅうしょく)を勤めた林西寺をはなれ、武蔵国滝(たき)山(現八王子市)の大善寺という寺の住職に移りました。このころ呑龍は、徳川家康の信任(しんにん)ことに厚かった観智国師の片腕(かたうで)として、教化(きょうか)に、伝道(でんどう)に、そして法問(ほうもん)に、めざましい活躍をみせていました。こうして慶長十八年、朱印(しゅいん)高三〇〇石という格式(かくしき)の高い太田大光院の開山僧に選ばれて、大光院に移りました。
当時上州(じょうしゅう)(現群馬県)は凶作が続き、生活に困った人びとがたいへん多かったので、赤子をおなかのなかで殺したり、生まれてきた赤子をしめ殺したりすることが珍しくありませんでした。これを悲しんだ呑龍は、子供を育てられない貧しい家の子供たちをたくさん引き取り、家の手伝いができるようになる七歳ごろまで養育しました。この呑龍に引き取られた子供たちは、みんなすこやかに、しかもかしこく育ったといいます。これがのちに「とり子」とか「呑龍子(どんりゅうこ)」とかいって、帳面(ちょうめん)に幼児(ようじ)の名前をしるして、呑龍の弟子(でし)にすると、幼児はじょうぶに育つという信仰が生まれたわけです。
このように人びとからたいそうあがめられていた呑龍は元和二年(一六一六)という年に大光院をひそかにぬけ出すという大事件を起(お)こしました。それは罪人(ざいにん)をかくまったため、幕府(ばくふ)から取(と)り調(しら)べの呼び出し状が出されたためです。このさき大宮在のある若者が父の病気をなおそうとして、当時禁制(きんせい)(やってはいけないこと)の鶴を殺し、その生血(なまち)を父にのませました。これがわかったため役人に追われていました。若者は知人(ちじん)をたより館林(たてばやし)まで逃げてきましたが、ここでも館林藩(はん)の役人にみつかり、つかまりそうになりました。そこで若者は館林からのがれ、太田の大光院に逃げこんで呑龍に救いを求めました。事情を聞いた呑龍は、若者の親思いの心にうたれ若者を大光院うらの岩(がん)くつ内にかくまいました。
これを知った役人が大光院にきて、若者の引き渡しを求めましたが、呑龍は若者を渡さず、捕(とり)手の役人を門前から追い帰しました。これに怒った館林の城主は、このことを幕府(ばくふ)に訴(うった)え出ました。訴えをうけた幕府は書状(しょじょう)をもって「役人を追い帰した者をこちらに引き渡してほしい。もしその者がわからないときは、大光院の僧をはじめ、門前の百姓(ひゃくしょう)すべてを江戸によこしてもらいたい、こちらで取りしらべをする」といってきました。
大光院の僧たちは驚(おどろ)いて、おろおろしていましたが、呑龍は一度助けるとちかった以上、若者を引き渡すことはできないと言い、その夜、若者の頭をそって弟子にし「わたしたちをさがさないでほしい」という書き置きを残して、若者と一しょに大光院をぬけ出しました。大光院を出た呑龍は、信州浅間山(あさまやま)の山麓(さんろく)小諸(こもろ)の山中に身をかくしましたが、毎日の生活はひどいもので、三度の食事にもことかくありさまでした。しかも小諸の冬はとくにきびしい寒さでした。このときも、むしろをまとって寒さをしのぐという生活でした。
いっぽう幕府は、無断(むだん)で寺をぬけだした呑龍の行動を怒り、呑龍の位階(いかい)をうばったうえ高三〇〇石の寺領をとりあげました。このため一〇〇〇名に及ぶ一山の僧や門前百姓は山を降りなければならなくなり、大光院は無人の寺となりました。こうして四年の歳月が流れた元和六年九月、呑龍の師(し)である観智国師が病いのため死を迎えました。二代将軍徳川秀忠は重臣土井利勝を見舞(みま)いの使者にたて、最後(さいご)ののぞみをたずねさせました。このとき国師は、「何ひとつ思い残すことはないが、ただ一つ大光院住職の呑龍のご赦免(しゃめん)を願いたい」と言い残して死にました。
この遺言(ゆいごん)によってか、翌元和七年一月、呑龍はあしかけ五年目で許され大光院に帰山しました。大光院に帰った呑龍は大光院の復興(ふっこう)につとめましたが、翌八年、僧としては最高の位である常紫衣(紫の僧衣)をたまわりました。小諸でのきびしい生活がたたったのか、呑龍は翌九年(一六二三)八月、「われ命おわるの後は、遺骸(いがい)を火葬(かそう)としないで、本堂の西方の地所に埋葬(まいそう)せよ」と言い残して死にました。ときに呑龍六八歳の夏のことでした。
なお呑龍の供養墓石は、一六年間住職をつとめた平方林西寺にも建てられています。この林西寺も太田の大光院と同じく江戸時代から明治・大正期にかけて、子育て呑龍の信仰が盛んであったお寺です。ともかく貧しい家の子供を引きとって育てたり、名もない若者を救うため、名誉(めいよ)ある高い位(くらい)や、何一つ不自由のない寺院を捨(す)てて、きびしい自然のなかの小諸の山中に生活した呑龍上人は、本当に偉い坊さんでした。