壬生町内を初めて定期バスが走ったのは,1919(大正8)年のことで,石橋自動車商会が5人乗りの車を使い,片道6kmの道を運賃50銭で,石橋と壬生を結びました。1927(昭和2)年には栃木・壬生・石橋を結ぶ「関東バス」が,関東自動車によって運行されるようになり,馬車に代わって壬生町民の足となりました。
このころ,壬生町を通過する鉄道の計画には,壬生と石橋を結ぶ「壬生電鉄」など多くありましたが,実現したのは,東武鉄道による「東武宇都宮線」でした。初めの計画は,東武日光線家中駅と宇都宮市を結ぶものでした。1928(昭和3)年には,家中駅ではなく,新栃木駅と宇都宮を結ぶよう改められ,現在の路線になりました。この鉄道計画について,壬生町も鉄道誘致運動を行いました。このことから,鉄道の開通がこの地方の発展に大きな力になると当時の壬生の人たちが考えていたことが分かります。
東武宇都宮線は,1931(昭和6)年8月11日に開通しました。壬生町内に設けられた安塚・国谷(くにや)・壬生の3つの駅では,祝賀会が開かれ,新しい時代の幕開けを祝いました。鉄道の開通は,壬生町を宇都宮市と結び,さらに東京へと人々の行動範囲を広げました。しかし,このころは日本全体が不景気の中にあり,人々の生活は大変苦しく鉄道の工事も景気対策,失業者対策という面ももっていました。
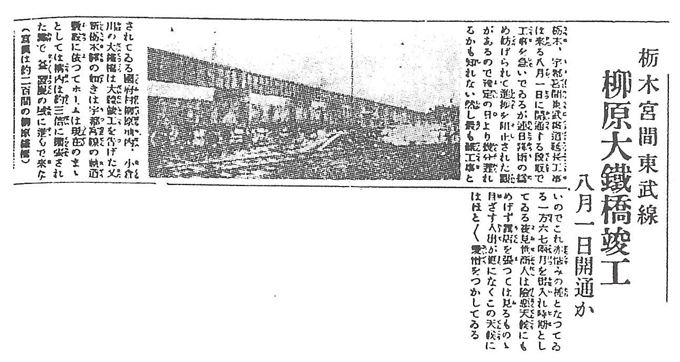
東武鉄道工事風景鉄道開通記事