義務教育である小学校の教育は,明治時代から「教育勅語(きょういくちょくご)」に基づいて行われ,天皇を神としてとらえ,神社や祖先を大切にすることが,教えられました。一方では,大正デモクラシーの動きの中で,一部の学校に「自由教育」が広がり,自発的・自主的な学習態度を育てることが,行われるようになっていきます。
また,このころになると,県内の中等学校への入学試験はきびしさを増し,小学校でも受験のために準備学習を行っていたようです。現在とよく似た受験戦争が,すでに見られたようです。当時は,義務教育を終えるとすぐに働く生徒が多かったので,この子供たちにも教育の場を与えようとする動きも起こりました。
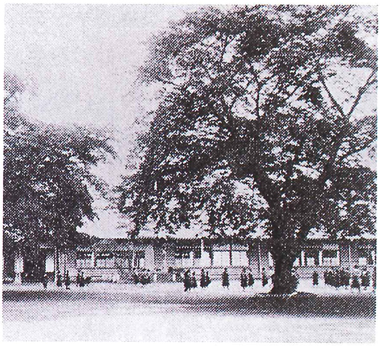
壬生小の風景
これは実業補習学校とよばれ,普通教育の補習とともに,農業など働くために必要な知識や技能が教えられました。壬生町では,農業補習学校が1818(大正7)年に設置されました。壬生農業補習学校は2学級で130名,稲葉農業補習学校は1学級で48名の生徒が学んでいた,という記録も残っています。戦争が近づいてくると補習学校には,軍事教練を目的とした青年訓練所が,あわせて置かれるようになります。