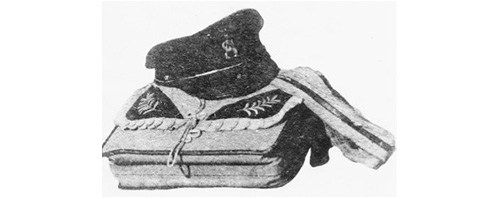日本における洋装は、男性の公的服装として導入され、軍隊から官公吏、警察や鉄道などの職業服へと広がった。明治19年(1886)に東京帝国大学が軍服由来の制帽・詰襟学生服を制服に定めると、他の中等・高等教育機関も男子の洋装制服を採用していった。一方、女性の洋装化は紆余曲折(うよきょくせつ)を経て遅れ、女子学生の洋装制服も大正期まで待つことになる。こうした流れの中、小学校の子どもの服装も、男女それぞれに洋装化していく。
洋装の取り入れは、男子児童の学生帽から始まった。和服に洋式学生帽の和洋折衷は、高価な洋服を制服化するより、まず洋式帽子を制帽として定める学校が多かったために起こったスタイルで、中等学校以上の男子学生に広まっていた。公立小学校もそれを取り入れ、早くも明治21年の桜川小学校の卒業写真には、学生帽をかぶる児童が見られる[図4―8]。
学生帽に徽章(きしょう)や白線をつける小学校もあり[図4―9]、子どもたちも自分たちの学生帽に誇りを持っていた。帽子を語り手にした次の児童作文からは、学生帽に対する深い愛着が感じられる。
和洋折衷スタイル
76 ~ 78 / 321ページ
私は学校ぼうしであります。私は、銀座のぼうし屋にゐたのであります。店にならべられてゐたのであります。八つぐらいのぼっちゃんに、買はれていったのであります。そのぼっちゃまは、学校をやすんだことがありませんでした。また、友だちやなにかの家へあそびにゆく時には、きっと私をつれていってくれます。そのぼっちゃまは、よそにゆく時にもそうであります。
(原文は全文片仮名、南山小学校『南山』第31号、明治44年)
(原文は全文片仮名、南山小学校『南山』第31号、明治44年)
明治末期から大正期にかけて、和服の袴(はかま)ばきで髪に大きなリボンを着ける和洋折衷スタイルの女子児童が見られるようになる。リボンは明治30年代から女学生に人気となり、当時の雑誌の挿絵や小説に頻繁に登場した。また、リボンの流行は、島田髷(まげ)などの日本髪から束髪と呼ばれる洋風スタイルへ髪型が変化したことと関係している。束髪は、簡易で衛生的であり、活発に動いても崩れにくいことから、学校生活に適していたのである。
その流行が、小学校の女子児童にも伝播したのであろう。教室には、大きなリボンを着ける女子児童が並び、三つ編みなどの洋風髪型も見られた。しかし、リボンの流行は長くは続かなかった。小学校の卒業写真をたどると、明治末期からリボンの女子児童が増え始め、瞬く間に全員に広まるものの、大正後期には途絶えてしまう[図4―11]。その後には髪型も変化し、おかっぱ髪が増えていった。
その流行が、小学校の女子児童にも伝播したのであろう。教室には、大きなリボンを着ける女子児童が並び、三つ編みなどの洋風髪型も見られた。しかし、リボンの流行は長くは続かなかった。小学校の卒業写真をたどると、明治末期からリボンの女子児童が増え始め、瞬く間に全員に広まるものの、大正後期には途絶えてしまう[図4―11]。その後には髪型も変化し、おかっぱ髪が増えていった。

[図4-10] 南山小学校の遠足
男子児童は学生帽をかぶって遠足に出かけた。洋服の児童もわらじを履いており、これも和洋折衷スタイル。遠出の時は、靴よりわらじを履くよう指示された。
南山小学校所蔵、明治43年
関連資料:【通史編3巻】2章2節4項 学習の様子