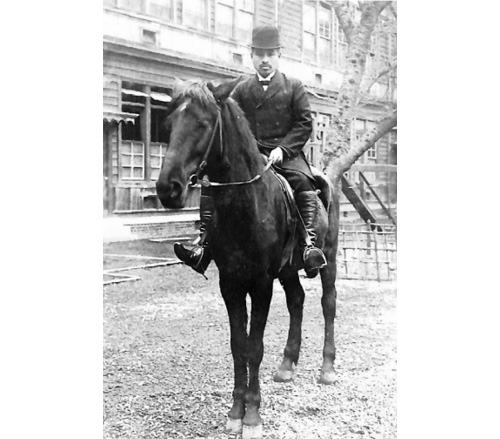翌大正8年には、『東京市白金尋常小学校校報』が発行される。この校報では、どのような内容が伝えられたのだろうか。
創刊号には「大正七年度中に行ひたる校外教授と遠足運動会」などの学校行事の記事、「児童文庫の設置と閲覧の状況」と題した、新設置の図書閲覧スペースの利用状況の記事がある。記事を読んでいくと、校長や教員が主体になる文章が多いのが目につく。例えば、「大正七年度における級長副級長の任命」では、級長・副級長になった児童の氏名が一覧になっている。しかし、添えられている文章は、「これらの児童が級長・副級長に就任した」という主旨ではなく、「各学期の始めに学校長より任命になりました」である。
さらに第2号になると、「皇太子殿下御成年奉祝挙式と奠都(てんと)五十年祭及び市制施行三十年記念日」「井上東京府知事の薨去(こうきょ)と会葬」「駒木根学校長の宮城(きゅうじょう)拝観」「高橋男訓導の伊勢神宮参拝」「駒木根学校長の東京市教員奨学講習」「井上訓導の叙勲祝賀」「市川女訓導の伊勢神宮参拝」などの記事が増える。皇太子の成年式や府知事の葬儀は学校の教育とは関係ないように思われるが、結局は校長や教員が式典に参加したことが述べられている。校長が選ばれて当時宮城(きゅうじょう)と呼ばれた皇居を拝観したことなど、権威主義的な側面を強調する記事も多い。
その一方で、子どもたちの身の上に起きた出来事の取り上げ方は決して大きくない。大正7年から、当時「スペイン風邪」と呼ばれた感染症が流行し、白金小学校では3人の児童が罹患(りかん)して亡くなっている。この事実は「猖獗(しょうけつ)を極めたる流行性感冒の影響」と題した創刊号の記事で「死亡率は児童には僅少と見え三名でありました」と触れられているにすぎない(5)。
校報に見られるのは、教育の主体、学校の主役はあくまでも校長や教師だという主張、校長や教師は皇室や東京市といった権威を背景にして教育を行っているという主張に他ならない。こうした主張は、明治期以来の臣民育成という教育政策に照らして、決して珍しいものとは言えない。だがこの後、校長の交代によって新教育への向きあい方も、権威を背景にした学校運営も、大きく変化することになる。
「校報」の発刊とその内容
142 ~ 143 / 321ページ