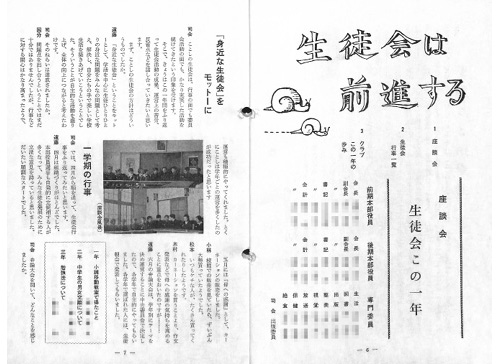昭和34年(1959)年に『高陵』(高陵中学校、3月)、昭和40年に『あさひ』(朝日中学校、3月)、『港南』(港南中学校、3月)が創刊された。また赤坂中学校では昭和32年に『あけぼの』第6号(3月)を発行して以降、校誌が途絶えていたが、昭和39年に『あかさか』と改称して復刊するなど、校誌の発行が増えていった。
昭和34~43年の間、座談会も多くの校誌で継続的に、あるいは断続的に開催された。座談会記録は45本に上る。また、一度に複数の座談会を掲載する号もいくつかあり、生徒同士で、または生徒と教師が語り合う場を積極的に設定していたことがわかる。前の時期と比べると、生徒会・委員会に関する座談会記録が12本と、大きく増えている。多くの中学校が発足から10年を過ぎて生徒会も軌道に乗り、生徒会活動が中学校生活にとっての重要な一部を形成するに至った。その結果、座談会での論点も、生徒会活動が円滑に行われたかどうかに移っていった。
『高陵』第10号(高陵中学校、昭和43年3月)「生徒会この一年」では、「身近な生徒会」をモットーとして「学活を中心に生徒ひとりひとりの身近な問題をみんなの問題として考え、解決し、自分たちの手で楽しい学校生活を築きあげていこう」という方針で活動した結果、生徒会に対する関心が高まり、もろもろ反省はあったものの、全体として行事や各種委員会活動を積極的に行うことができたと総括している。
『高松』第8号(高松中学校、昭和35年3月)「生徒会委員会活動の反省と来年度への期待」では、放送委員会の活動がうまくいかないことが問題視され、委員が突き上げられた。同席していた教員は「僕を含めて先生方の生徒会活動の指導がまずかったということになってくるので必らず(ママ)しも委員長の責任ではないと思います」と助け船を出している。対照的なのが、本章冒頭で紹介した『朝日』第3号(朝日中学校、昭和42年)「よりよい生徒会とは」である。要求を出すルートがないと不満を訴える生徒会長に対し、教員は生徒が生徒会で校内生活について話し合わなかったことを指摘するなど、厳しく指導している。もっとも、あくまで生徒や教師による主観であることにも注意したい。朝日中学校の場合、昭和23年から昭和47年までの間、生徒会を市会に見立てて「朝日市政」と呼んで生徒会活動を行っており、必ずしも低調だったと判断できない(4)。ともあれ両事例とも、円滑な学校教育活動には不可欠なはずの生徒会および委員会が十分に機能していないという現状認識を生徒・教師双方が共有し、その原因について生徒と教師が究明しようとしている様子がうかがえる。また、この時期になると教師の指導的立場からの発言が目立つことも、指摘しておきたい。
この時期は、クラブ活動や学校生活、勉強をテーマとした座談会記録がそれぞれ10本と、急激に増えている。昭和33年に改訂された学習指導要領は、「クラブ活動に全校生徒が参加できることは望ましい」としながらも、「生徒の自発的な参加によってそのような結果が生れるように指導することがたいせつである」と、生徒の自発的参加によるクラブ活動の発展を期待した。『みなと』第9号(港中学校、昭和37年3月)「クラブこのごろ」では、クラブの現状と発展策について話し合っている。順調なクラブが少ないため、強制加入の是非についても論じられた。『あゆみ』第14号(城南中学校、昭和38年3月)「あとはしっかりたのんだぜ‼」でも、クラブ選びを間違えたために練習に出てこなくなった例があるとして、「クラブの選び方は、もつともつと慎重にといいたい」と後輩へアドバイスを送った他、勉強との両立の難しさを述べている。
〔(1) 円滑な生徒会運営を目指して〕
253 ~ 255 / 321ページ
関連資料:【文書】北芝中学校生徒会組織