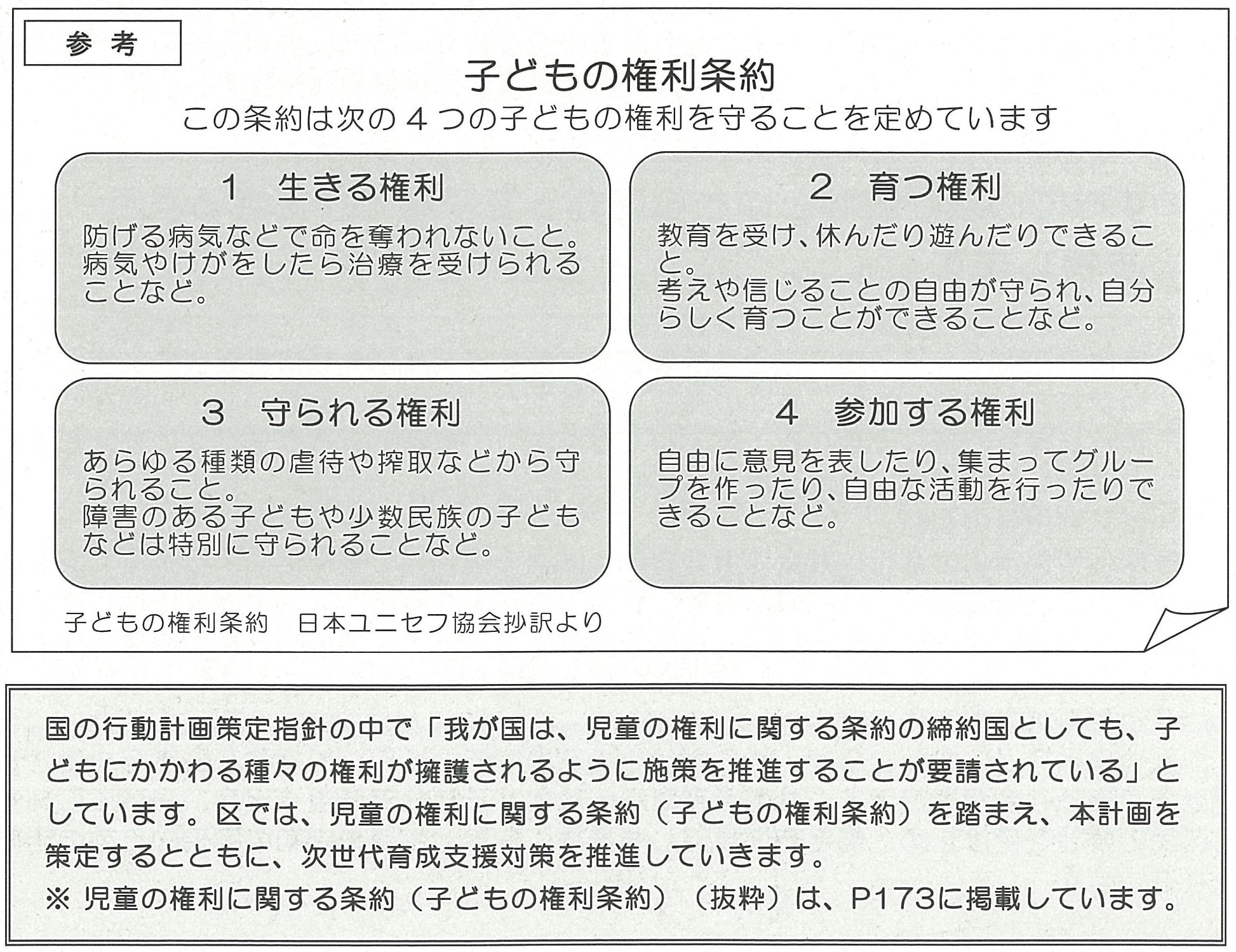1 子どもが将来の夢と希望をもてるよう子育ちを支援します
● 一人ひとりの子どもの個性と能力を伸ばし可能性を広げるために、新しい時代にふさわしい魅力ある教育環境を整えます。また、家庭・学校・地域社会が連携して次代を担う子どもたちが生きる喜びを感じ、将来の夢を描けるような地域社会の環境整備を推進します。
<子どもの視点>
子どもの幸せを第一に考え、子どもの利益が最大限に尊重されるよう、子どもの視点に立った取組みを推進します。
<次代の親づくりという視点>
子どもは次代の親となるものとの認識のもとに、豊かな人間性を形成し、自立して家庭を持つことができるよう、長期的な視野に立った子どもの健全育成のための取組みを推進します。
<地域特性の視点>
区役所・支所改革の実施に伴い、総合支所を中心として、各地区の利用者のニーズや必要な子育て支援策を十分把握し、地域特性に応じた主体的な取組みを推進します。
2 すべての親が安心とゆとりをもって子育てができるよう支援します
● 家庭で子育てをする親、働きながら子育てをする親、様々な支援を必要とする親のいずれも、自助、公助、共助の考え方を基本としながら、安心して、心豊かに、ゆとりを持って楽しみながら子育てができるよう、子育て支援サービスの充実を図るとともに社会環境の整備を推進します。
<サービス利用者の視点>
核家族化や都市化の進行、社会環境の変化、区民の価値観の多様化により子育て支援に係る利用者ニーズの拡大、多様化に、柔軟に対応できるよう総合的な取組みを推進します。
また、利用者が安心してサービスを利用できるようサービスの質や人材の資質の向上に努めるとともに、情報公開やサービス評価の取組みを充実します。
<仕事と生活の調和実現の視点>
性別や年齢などにかかわらず、誰もが自らの意思や能力に応じて様々な生き方や働き方を選択できる社会が理想です。共働き家庭が一般化するなかで結婚や出産、子育てに関する区民の要望を受け止め、働き方の見直しも含め、仕事と生活の調和の実現のための施策を推進します。
<すべての子どもと家庭への支援の視点>
子育てと仕事の両立支援のみならず、子育ての孤立化、不安やストレス等の問題を踏まえ、在宅子育て家庭への支援、虐待等の社会的支援を必要とする子どもと家庭に対する支援の充実を図ります。
3 地域ぐるみで子育て家庭と子どもを温かく見守ります
● 子どもたちは地域の一員であるとともに、未来を創造する大切な「宝」であるという認識のもと、地域全体で子育てをする家庭と子ども自身を温かく見守る環境、子どもを暴力や犯罪から守る環境を整備します。
<社会全体による支援の視点>
保護者、家庭が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識のもと、国や都、区はもとより、企業やNPO等の民間事業者を含め社会全体が協力し、様々な担い手の協働のもとに支援対策を進めていきます。
<地域における社会資源の効果的な活用の視点>
地域においては、総合支所を中心に、町会・自治会、学校、企業・NPO、ボランティア団体、民生・児童委員等様々な地域活動団体が活動しています。また、子育て等を通じて地域貢献を希望する高齢者も増えてきました。さらに、各地区にはまちの歴史や伝統文化に彩られた地域の活動や商店街振興など、様々なコミュニティ活動が行われています。こうした様々な地域における社会資源を十分かつ効果的に活用し、子どもの健全育成や子育て支援を推進します。