【東京タワー】 港区における超高層建築は総合電波塔・東京タワー(昭和三十三年十二月完成、三三三メートル・芝公園四丁目二番)をもって嚆矢とする。大きなビルもなく各テレビ局の専用塔(当時赤坂の東京放送のものを含め東京に三本)程度のものしか見慣れていない当時の人びとにとって、この世界一の自立鉄塔の出現は、建造物の高さにたいするイメージを一挙に変えるものとなった。タワー建設の構想者は、同時に、戦後復興の途上にあった日本国民が自信を取りもどすよすがともしたかったとのことであるが(『東京タワー・一〇年のあゆみ』)、東京タワーはたんに港区のみならず東京ひいては日本の顔として国際的な存在となっていったのである。
鉄塔という性格上、街の変化にどれほどの影響力をもったかは疑問だが、建築後二十年たったこんにちでも夥しい観光客が訪れているのは、自然空間に単純な鉄骨を組み合わせてそびえ立つ形状が、コンクリートの「密室集合体」である超高層ビルなどに較べ、人びとにある種の開かれた印象を与え、親しみを感じさせるとともに、なによりも二五〇メートル上空からの眺望が〝見晴らし〟を好む日本人の興味を誘うからであるのかもしれない。
【世界貿易センタービル】 そして昭和四十五年三月、地上四〇階、高さ一五二メートルの世界貿易センタービルが、国電浜松町駅前の都電車庫跡に建設されたのである。
敗戦直後、一面焼け野原と化した浜松町駅周辺に唯一残されていたこの都電車庫が、進駐軍に接収されて、大型の外車が立ち並び、ガードをくぐった〝倉庫村〟には、金網のバリケードが張りめぐらされ、その入口にはMPが立ち、アメリカ兵が群れをなしていた場所でもあったのだった。
それから、都電の車庫としての全盛時代があり、やがてその都電の廃止とともに、ここが一躍、一五二メートルに象徴される、日本の都市における超高層ビル化のスタートを示すこととなったのである。
その意味では、このビルの計画から完成、そしてこんにちにいたる道すじは、そのまま戦後社会、とりわけ都市の変貌の内実をもっとも象徴的に物語ってくれるものとなったといえよう。
ビル建設のそもそもの発端は、経済界で高度成長期の貿易の拡大にともない国際貿易の総合センタービルの必要性がうたわれたことにあり、象徴的なことにはその敷地として昭和三十年代半ばごろから自動車の増加によって肩身を狭くし後退しつつあった都電の車庫跡が選ばれたのである(昭和三十八年)。また、このビルには、バスターミナル、公共駐車場も用意され、羽田空港とモノレールで直結するなど都市交通の利便も考慮され、たんにビジネスビルという枠にとどまらず、多目的な複合建築物により地域再開発の拠点となることがめざされたのである。
すでに霞が関ビル建設によって、地震と台風の国日本では超高層ビルは建て得ないという神話は打破されていたから、狭域的な都市再開発を空間効率の飛躍的上昇によって実現しようという発想は、必然的なものであった。戦後都市計画が一つの曲がり角にさしかかっていた象徴なのかもしれない。しかし、再開発事業が十分な環境開発をともなわない限り、都市機能の活性化―発展は望めず、病理現象さえひきおこすことにもなりかねない。
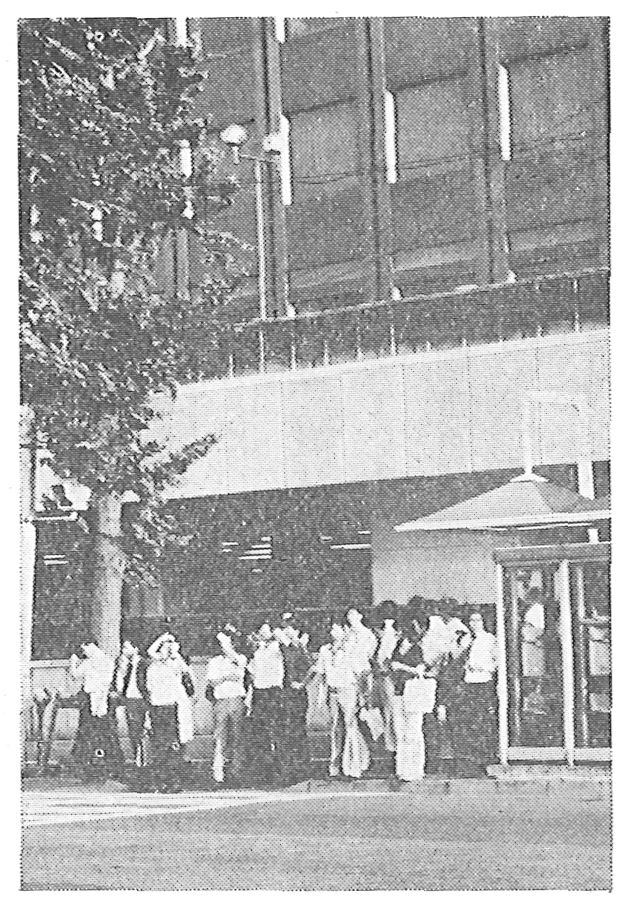
貿易センタービル地下街入口付近
【都市再開発の停滞】 この貿易センタービルについても。当初から懸念されていた周辺道路からのアプローチの問題、浜松町駅間の道路処理の問題、芝大門一帯にいたる近隣地域再開発の必要性など付近の面開発の課題は依然として残されたままになっている。経済情勢の悪化なども考えあわせなくてはならないが、ポツンと立っているこのノッポビルは都市再開発の困難性を体現し、いわば〝未完成品〟のままこんにちに至っているのである。また、その巨大さによる新しい公害としての〝風害〟は、通行人だけでなく付近の商店、浜松町駅構内にまで及んでおり、その景観上の威容も、地上にいる者にはときとして異様な圧迫感を与えかねない。
【「超高層」概念の変化】 市街地の様相を一変させるこうした超高層ビルは、その後も続々と建てられ、街の景観は上へ上へと延びていった。昭和四十七年ごろ、五〇メートル以上の建築物を「超高層」と形容し、ホテルパシフィック(九七メートル・高輪三丁目)、警視庁交通機動隊寮(六一・七メートル・芝浦四丁目)、広尾タワーズマンション(五二・六メートル・南麻布四丁目)などを紹介していた冊子(東京都総務局・観光課刊『観光レクリエーションの手びき・とうきょう』)が、昭和五十一年版において「超高層建築」を一〇〇メートル以上に限定して紹介しているのは、その間の事態の進展をよく物語っているといえよう。すでに高層ビル(マンション)に見下されるようにしてたつ商店(民家)という風景は、港区にかぎらずいたるところの街で見られる風景となっている。一五二メートルの街が人びとに〝詩〟を生むか、それとも〝死〟をもたらすか、いつの日にかわたしたちは問われる日を迎えることがあるかもしれない。それは、誰もが否定しきれないひとつの不安として、街の人びとに抱かれていくであろう。