まず、戦後の港区の工業事情についてながめてみると、工場数において昭和二十四年(一九四九)、六五三工場であり、これを一〇〇とすると昭和五十一年には二、三〇一工場で三五二の数値となる。
同じ年度を従業員数でみると、昭和二十四年一万六、四一三人であったのが、昭和五十一年は四万六二六人で二四八という数値になっている。
表1 戦後の港区工業事情
| 年 次 | 工場数(指数) | 従業員数(指数) | 出荷額(指数) |
| 昭和 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 31年 32年 33年 34年 35年 36年 37年 38年 39年 40年 41年 42年 43年 44年 45年 46年 47年 48年 49年 50年 51年 | 653(100) 573( 88) 1,098(168) 1,335(202) 1,438(220) 1,521(233) 1,579(241) 1,539(235) 1,711(262) 1,731(265) 1,683(258) 1,661(254) 1,582(242) 1,503(230) 2,100(322) 1,930(296) 1,833(288) 2,253(345) 2,119(325) 2,045(313) 2,356(361) 2,176(333) 2,014(308) 2,360(361) 2,129(326) 2,044(313) 1,950(299) 2,301(352) | 16,413(100) 17,870(109) 21,076(129) 24,899(152) 28,157(171) 27,716(169) 30,307(185) 32,123(196) 36,434(222) 39,504(241) 43,089(263) 49,250(300) 49,104(299) 47,783(291) 52,820(322) 49,592(302) 48,978(298) 51,180(312) 49,399(301) 48,320(294) 53,184(324) 51,348(313) 48,387(295) 47,822(291) 43,895(267) 41,623(254) 37,062(226) 40,626(248) | 4,924( 100) 10,018( 202) 21,177( 431) 23,596( 480) 28,530( 579) 34,975( 710) 37,725( 766) 45,717( 929) 59,006( 1,198) 60,432( 1,227) 71,234( 1,447) 92,393( 1,876) 104,586( 2,124) 116,458( 2,365) 124,487( 2,528) 131,433( 2,669) 132,374( 2,688) 155,913( 3,166) 176,596( 3,586) 194,580( 3,952) 237,220( 4,818) 290,256( 5,895) 309,098( 6,277) 339,789( 6,901) 380,882( 7,735) 467,937( 9,503) 478,999( 9,728) 548,052(11,130) |
【港区の工業と省力化】 以上の二つの数値の差から従業員の少ない省力化工場が進出してきていることが指摘できるし、さらにそれを出荷額でみると、昭和二十四年を一〇〇とした場合、昭和五十一年は一万一、一三〇という指数を示しており、工業生産性が非常な勢いで高まってきていることが指摘できるだろう。これは物価上昇率を勘案しても、生産性の向上と省力化工場といった特徴をみせていることにほかならない。そのことは、次のように数値を並べてみると、いっそう明白となる。
すなわち、昭和五十一年には、二十四年の数値にたいして、
工場数………三五二→三・五倍
従業員数……二四八→二・五倍
出荷額………一一、一三〇→一一一倍
といった具合である。
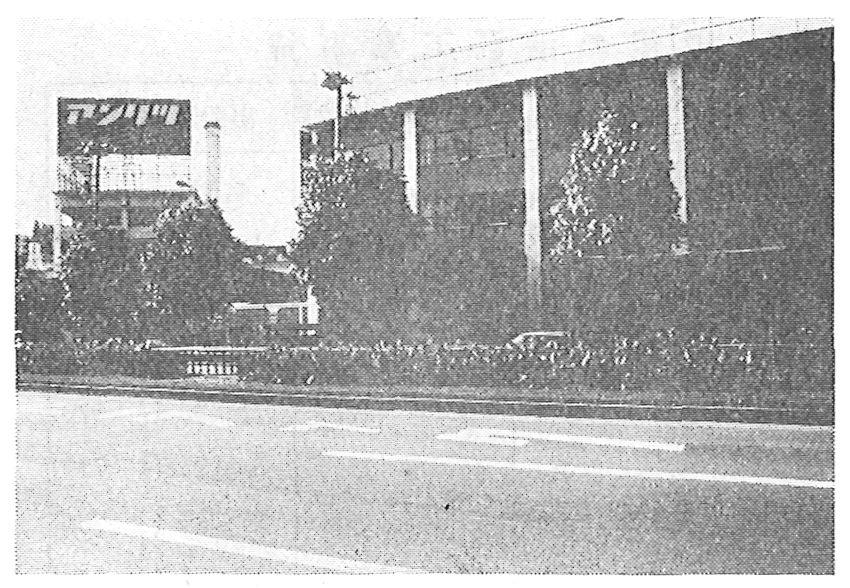
安立電機工場―南麻布4丁目
【四人~九人工場の増加】 つぎに、規模別工場数の推移を昭和三十年を基準にしてながめてみると、事業所数全体では、昭和三十年、一、五七九事業所であったが、昭和五十一年には二、三〇一事業所となり、これは一・五倍となっている。ただし、三人以下の工場数では一・六倍と、全体の増加率とほぼ同数であるが、四人~九人の規模の工場が二倍に伸び、この規模の工場数の増加が著しいことが分かるし、あとはほぼ横ばいであった。
ただ一、〇〇〇人以上の工場数では、昭和三十年にはゼロであったのが、昭和五十一年には六工場であるから、大工場が東京港の地の利を生かして進出してきたことがうかがえる。
表2 規模別工場数の推移
| 年次別 | 事業所数 | 規 模 別 | ||||||
| 3人以下 | 4人~ 9人 | 10人~ 29人 | 30人~ 99人 | 100人~ 499人 | 500人~ 999人 | 1000人 以上 | ||
| 昭和24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 31年 32年 33年 34年 35年 36年 37年 38年 39年 40年 41年 42年 43年 44年 45年 46年 47年 48年 49年 50年 51年 | 653 573 1,098 1,335 1,438 1,521 1,579 1,539 1,711 1,731 1,683 1,661 1,582 1,503 2,100 1,930 1,833 2,253 2,119 2,045 2,356 2,176 2,014 2,360 2,129 2,044 1,950 2,301 | ― ― (4人以下) 460 ( 〃 ) 561 ( 〃 ) 555 ( 〃 ) 571 504 383 407 430 404 367 331 308 395 376 342 486 465 441 530 472 501 661 571 569 615 790 | ― ― (5~29人) 526 ( 〃 ) 651 ( 〃 ) 737 ( 〃 ) 795 464 486 515 475 446 444 443 408 797 766 744 922 868 872 1,036 991 879 1,037 967 941 840 944 | ― ― (30~49人) 52 ( 〃 ) 54 ( 〃 ) 72 ( 〃 ) 82 436 480 558 580 565 555 519 517 606 516 493 577 519 481 534 485 (10人~19人) 321 (10人~19人) 356 402 367 351 407 | ― ― (50人以上) 60 ( 〃 ) 69 ( 〃 ) 74 ( 〃 ) 73 134 156 186 203 215 239 234 209 234 214 194 207 202 188 194 166 (20人以上) 313 (20人以上) 306 141 120 108 117 | ― ― ― ― ― ― 37 30 40 37 48 47 48 52 60 49 49 51 56 53 53 53 ― ― 40 39 29 34 | ― ― ― ― ― ― 4 1 3 3 2 3 2 4 4 5 6 5 4 5 3 3 ― ― 3 3 2 3 | ― ― ― ― ― ― 0 3 2 3 3 6 5 5 4 4 5 5 5 5 6 6 ― ― 5 5 5 6 |
表3 部門別工場数の推移
| 種 別 年 次 | 総 数 | 食 料 品 製 造 業 | 繊 維 工 場 | 衣 服 そ の 他 の 繊 維 工 業 | 木 材 木 製 品 | 家 具 装 備 品 | パ ル プ ・ 紙 ・ 紙 加 工 品 | 出 版 ・ 印 刷 | 化 学 工 業 | 石 油 ・ 石 炭 | ゴ ム 製 品 | 皮 革 ・ 同 製 品 | 窯 業 ・ 土 石 | 鉄 工 業 | 非 鉄 金 属 | 金 属 製 品 | 機 械 | 電 気 機 械 器 具 | 輸 送 用 機 械 器 具 | 精 密 機 械 | 武 器 | そ の 他 |
| 昭和24年 | 653 | 78 | 4 | 11 | 21 | 31 | 4 | 56 | 21 | ― | ― | 5 | 5 | ― | * 7 | ** 168 | 76 | 119 | 35 | 7 | ― | 5 |
| 25年 | 573 | 35 | 5 | 8 | 13 | 63 | 6 | 85 | 23 | ― | ― | ― | 6 | ― | (〃) 12 | (〃) 86 | 97 | 93 | 27 | 7 | ― | 7 |
| 26年 | 1,098 | 65 | 6 | 15 | 48 | 153 | 17 | 152 | 20 | ― | ― | 4 | 6 | ― | (〃) 12 | (〃) 195 | 136 | 161 | 36 | 5 | ― | 6 |
| 27年 | 1,335 | 84 | 7 | 15 | 59 | 210 | 23 | 173 | 25 | 1 | 2 | 6 | 11 | ― | (〃) 21 | (〃) 238 | 138 | 191 | 76 | 19 | ― | 36 |
| 28年 | 1,438 | 90 | 10 | 15 | 69 | 219 | 24 | 177 | 25 | 2 | 1 | 6 | 12 | ― | (〃) 17 | (〃) 294 | 138 | 188 | 77 | 23 | ― | 51 |
| 29年 | 1,521 | 96 | 6 | 32 | 75 | 232 | 26 | 207 | 20 | 4 | 2 | 10 | 12 | ― | (〃) 26 | (〃) 293 | 132 | 197 | 82 | 23 | ― | 46 |
| 30年 | 1,579 | 95 | 6 | 28 | 68 | 255 | 45 | 196 | 24 | 1 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 62 | 25 | 39 | 12 | 31 | 0 | 31 |
| 31年 | 1,539 | 101 | 7 | 28 | 70 | 234 | 46 | 193 | 21 | 2 | 1 | 6 | 13 | 3 | 21 | 261 | 154 | 226 | 58 | 26 | 0 | 67 |
| 32年 | 1,771 | 115 | 8 | 41 | 78 | 244 | 39 | 255 | 22 | 3 | 1 | 9 | 13 | 4 | 19 | 263 | 181 | 255 | 68 | 35 | 1 | 57 |
| 33年 | 1,731 | 114 | 11 | 32 | 71 | 235 | 47 | 252 | 25 | 1 | 2 | 9 | 22 | 4 | 21 | 254 | 181 | 275 | 100 | 28 | 0 | 47 |
| 34年 | 1,683 | 112 | 10 | 35 | 64 | 237 | 40 | 265 | 23 | 1 | 2 | 7 | 19 | 10 | 12 | 244 | 180 | 252 | 88 | 35 | 0 | 47 |
| 35年 | 1,661 | 106 | 10 | 28 | 66 | 218 | 34 | 268 | 24 | 2 | 1 | 8 | 19 | 5 | 16 | 239 | 199 | 249 | 86 | 28 | 0 | 55 |
| 36年 | 1,582 | 94 | 6 | 29 | 57 | 209 | 32 | 244 | 22 | 3 | 3 | 4 | 16 | 7 | 17 | 225 | 185 | 257 | 89 | 30 | 0 | 53 |
| 37年 | 1,503 | 94 | 6 | 27 | 61 | 200 | 33 | 244 | 20 | 1 | 1 | 3 | 16 | 4 | 16 | 224 | 174 | 240 | 70 | 31 | 0 | 38 |
| 38年 | 2,100 | 110 | 13 | 50 | 77 | 248 | 42 | 480 | 35 | 1 | 7 | 11 | 24 | 6 | 21 | 284 | 203 | 303 | 90 | 31 | 0 | 61 |
| 39年 | 1,930 | 98 | 6 | 50 | 65 | 233 | 30 | 453 | 22 | 2 | 4 | 9 | 23 | 5 | 15 | 279 | 186 | 264 | 76 | 36 | 0 | 74 |
| 40年 | 1,833 | 89 | 6 | 50 | 52 | 229 | 31 | 429 | 21 | 2 | 4 | 8 | 20 | 6 | 14 | 253 | 183 | 279 | 57 | 34 | 0 | 66 |
| 41年 | 2,253 | 125 | 8 | 85 | 74 | 260 | 43 | 550 | 22 | 2 | 7 | 10 | 21 | 7 | 23 | 297 | 224 | 288 | 61 | 46 | 0 | 100 |
| 42年 | 2,119 | 118 | 9 | 81 | 66 | 248 | 40 | 528 | 17 | 2 | 8 | 11 | 23 | 4 | 20 | 313 | 193 | 270 | 56 | 35 | 0 | 77 |
| 43年 | 2,045 | 118 | 9 | 75 | 67 | 247 | 41 | 514 | 14 | 2 | 6 | 6 | 21 | 5 | 15 | 280 | 192 | 268 | 60 | 35 | 0 | 70 |
| 44年 | 2,356 | 125 | 10 | 89 | 75 | 241 | 38 | 698 | 20 | 2 | 7 | 8 | 28 | 5 | 16 | 294 | 215 | 293 | 57 | 39 | 0 | 96 |
| 45年 | 2,176 | 115 | 8 | 78 | 68 | 231 | 39 | 646 | 16 | 3 | 8 | 8 | 23 | 7 | 15 | 299 | 190 | 257 | 49 | 31 | 0 | 85 |
| 46年 | 2,014 | 104 | 6 | 73 | 71 | 199 | 29 | 592 | 11 | 2 | 4 | 5 | 24 | 7 | 16 | 297 | 192 | 248 | 41 | 31 | 0 | 80 |
| 47年 | 2,360 | 112 | 7 | 90 | 70 | 226 | 35 | 794 | 17 | 1 | 4 | 8 | 26 | 9 | 12 | 303 | 195 | 275 | 50 | 38 | 0 | 88 |
| 48年 | 2,129 | 100 | 6 | 71 | 68 | 201 | 33 | 704 | 14 | 1 | 6 | 6 | 24 | 6 | 14 | 287 | 196 | 225 | 42 | 35 | 0 | 89 |
| 49年 | 2,044 | 95 | 4 | 71 | 63 | 191 | 29 | 685 | 15 | 2 | 4 | 8 | 20 | 6 | 13 | 269 | 187 | 228 | 35 | 34 | 0 | 86 |
| 50年 | 1,950 | 90 | 2 | 73 | 55 | 189 | 35 | 664 | 13 | 1 | 6 | 4 | 21 | 4 | 14 | 225 | 187 | 194 | 37 | 31 | 0 | 75 |
| 51年 | 2,301 | 102 | 7 | 78 | 62 | 198 | 46 | 914 | 16 | 2 | 10 | 7 | 26 | 18 | 23 | 234 | 171 | 214 | 52 | 31 | 0 | 90 |
(注) *=非鉄金属のうち第一次金属,**=金属製品のうちの第二次金属。
【部門別工場数】 さらに、これら工場を部門別工場数の推移から詳細にみてみると、前述したように出版・印刷業と金属製品工業の発展には著しいものがある。
【都市型工業の成立】 とくに出版・印刷は、昭和三十年には一九六工場であったが、昭和五十一年には九一四工場となり、これは約七倍となっており、都市型工業の発達といった特徴をみせてきたことが指摘できる。