それ以降の港区青年学級の発展・展開は、以下にのべるとおりである。
昭和二十八年開設された青年学級を母体として、昭和三十四年、三田図書館に第二青年学級が開設された(第一、第二日曜日)。
さらに、昭和三十七年、三河台中学校に第三青年学級(第一、第三日曜日)、翌三十八年に三光小学校に第四青年学級が開設された(第一、第三日曜日)。
昭和三十九年、第一・第二青年学級が区役所内の青年館に移り、翌四十年、第三青年学級が城南中学校に移った。
昭和四十年には、障害児学級卒業者を対象とする第五青年学級が高松中学校に開設された(第一、第三日曜日)。そして、昭和四十三年に、第一、第二青年学級が現在の区立青年館に移り、第四青年学級が芝浜中学校に移った。
青年学級は、勤労青年にたいし、「実際生活に必要な職業又は家事に関する知識及び技能を習得させ、並びにその一般教養を向上させる」(青年学級振興法)ことを目的としている。しかし、一九六〇年代後半から、参加者は減少してきている。この原因は、学級内容の問題、雇用主の理解と協力の問題、学級のPRの徹底不足などがあることはもとよりであるが、その基底にはさらに、より体系的な後期中等教育、高等教育の教育要求の高まり、それによる進学率の増加、各種学校の数多くの出現、マスメディアの充実など、学習機会の広範な存在などの要因が大きく影響しているといってよかろう。こうしたことから一学級(すなわち第三青年学級が)廃止となったのは、昭和四十九年度であった。
本区の青年学級は、それぞれの開設の経過からみて、次の三つのタイプにわけることができる。
【青年学級の内容】 第一のタイプは、第一青年学級のように平日の夜に開かれ、一般教養や生活と労働に関する知識を授けることと、仲間づくりのための活動とからなるものである。(昭和五十一年度現在では、第一・第三青年学級がこれにあたる。)
第二のタイプは区内の店員さんを対象とし、月二回日曜日にひらかれる青年学級である。このタイプは都内でもめずらしい。(現在では第二青年学級がこれにあたる。)
第三のタイプは、障害児学級・学校卒業者を対象としたものである。これは、義務教育段階後の障害者の教育機会の一つとして機能している。(現在の第四青年学級がこれにあたる。)
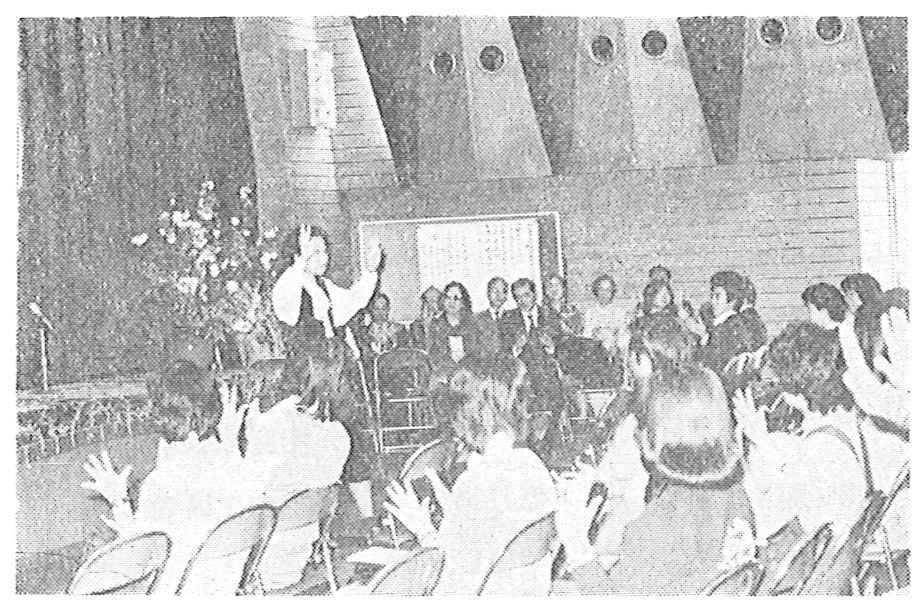
青年学級開級式
現在の講座内容等は表37に示したとおりである。
表37 昭和51年度青年学級開設状況
| 学級 項目 | 第 1 | 第 2 | 第 3 | 第 4 | 備 考 | ||||||
| 場所 | 港 区 立 青 年 館 | 港区立 城南中学校 | <修了者> 最後まで在籍し,実施回数の60%以上の出席者 <精勤者> 修了者のうち,実施回数の90%以上の出席者 | ||||||||
| 期間 | 51. 4.25~52. 3.13 | ||||||||||
| 日時 | 毎週金曜日 午後6:30~ 8:30 | 毎月第2・第4 日曜日 午前10:00~ 午後4:15 | 毎週金曜日 午後6:30~ 8:30 | 毎月第1・第3 日曜日 午後1:00~ 4:00 | |||||||
| 対象 | 区内に在住または在勤の15~25歳の勤労青少年 | 心身障害学級卒業生 | |||||||||
| 内容 | ○一般教養 文学・経済など ○スポーツ バドミントン ○レクリエーション ダンス・ゲ-ム ○話し合い学習青春論・恋愛論など | (クラス) 青年の心理 歴史と文学 簿記 和裁 | ○一般教養 ○サークル運営理論 ○レクリエーション指導技術など | ○生活に必要なもの 話し方・文の書き方・礼儀作法など ○話し合い学習 ○レクリエーション スポーツ・フォークダンスなど | |||||||
| (クラブ) ペン習字 バドミントン ダンス 生花 | |||||||||||
| 合 計 | |||||||||||
| 入級者数 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 |
| 9 | 16 | 34 | 60 | 28 | 30 | 13 | 5 | 84 | 111 | 195 | |
| 修了者数 | 5 | 5 | 16 | 27 | 6 | 12 | 8 | 0 | 35 | 44 | 79 |
| 精勤者数 | 3 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 15 | 29 |
青年学級の発展を考えるうえで、昭和四十四年十二月の港区社会教育委員会議の答申「港区における社会教育の今後のあり方について」の提言は、こんにちでも参考になる点が多い。
答申は港区に在住する青年が約四万人いることを念頭に青年教育の充実・発展を考え、PR方法についても各種の組織(地域組織PTA)を活用し、また、企業主の協力や一般家庭の協力をうることを期待するとともに、青少年指導の民間リーダーの育成、雇用主の理解不足による出席困難の解消、学科自体の魅力をつくることなどを指摘し、改善の方向を示している。さらに施設の充実、社会教育関係職員の「手うす」を改める措置を答申している。
先にものべたように、青年の要求の「多様化」とともに、系統的な青年期教育への要求も強まり、青年学級の参加者は減少しているが、学級生自身の手による自主的活動や学級活動が活発に進められ、学級の改善も行なわれている。昭和四十七年度には、それまで自主的に行なっていた校外授業、運動会、学級祭を、正規のカリキュラムにとり入れるようにしたり、昭和五十一年度には、第一青年学級で専任講師を中心に学級生の要求を生かす方向での自主カリキュラムによる学習を組んだりしている。
表38 青年学級の参加者
| 昭和43年 | 昭和45年 | 昭和48年 | 昭和51年 | |||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 入級 者数 | 232 (38) | 493 (17) | 232 (28) | 420 (16) | 122 (17) | 237 (11) | 84 (13) | 111 (5) |
| 修了 者数 | 109 (38) | 146 (17) | 65 (18) | 91 (5) | 41 (7) | 58 (4) | 35 (8) | 44 (0) |
| 精勤 者数 | 22 (5) | 16 (2) | 17 (3) | 14 (2) | 14 (2) | 14 (1) | 14 (2) | 15 (0) |
(注) かっこ内は,当該数のうちの,障害児学級卒業者数
【青年教室】 「青年教室」は、青年の実情をふまえ、その要求にこたえうるものとして、青年学級とはちがった形態での青年教育の場として開設された。
青年教室は、港区に在住、在勤、または在学する青年が、しごと、勉学の余暇を活用して、生活教養、技術を学び、身につけながら創造性ある、豊かな人間性づくりをめざして昭和四十九年に開設された。
昭和四十九・五十一の両年度における実施状況は、表39のとおりである。
表39 青年教室の実施状況
昭和49年度
| 期 別 | 科 目 | 内 容 | 回 数 | 参加数(延べ) |
| 前 期 | 生 花 | 心で活けましょう | 15 | 323人 |
| レタリング | 美しい文字を | 15 | 313人 | |
| 後 期 | 料 理 | より深い味わいを | 15 | 508人 |
| ダンス | リズムを楽しく | 15 | 618人 |
昭和51年度
| 期 別 | 科 目 | 内 容 | 回 数 | 参加数(延べ) |
| 前 期 | 英会話 | 会話に親しみましょう | 15 | 195人 |
| 生 花 | 心で活けましよう | 15 | 434人 | |
| 後 期 | 青年の心理 | 心の動きについて考えよう | 14 | 31人 |
| やさしい金融の 知識と簿記 | 実社会の中で役立てよう | 14 | 95人 | |
| レタリング | 美しい文字を書こう | 14 | 270人 |
なお、教室の修了者のなかから、さらに学習を続けたいとの希望が出され自主運営によるグループ「港区英会話教室」が生まれる、という新しい芽も出ている。